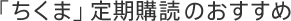鼎談 多面体マラルメの耀きを求めて
清水 徹
SHIMIZU TORU
●明治学院大学名誉教授
菅野昭正
KANNO AKIMASA
●東京大学名誉教授
渡辺守章
WATANABE MORIAKI
●東京大学名誉教授
新しいテクスト研究に立って
菅野 マラルメは戦後になって、新しい書簡や、「リーヴル」、「エロディアード」関係その他の作品についても新しい資料が出た。それらを総合してマラルメを読み直す、あるいは紹介し直すということがわれわれに課せられた使命だったと思います。
書簡、とくに一八六〇年代のカザリス宛書簡などは戦前には知られていなかった。マラルメの詩に対する考え方、世界、そして言語とのかかわり方、マラルメは何を基本的に考えて詩人として出発したのか、六〇年代の書簡がないと、はっきりしない点が多々あったわけですね。今回の『全集』では、書簡に関して大きな試金石を作り出すことができたと思っています。
清水 全集の第一回配本が第Ⅱ巻『ディヴァガシオン他』だった。そのあとでいちばん大きなことは、プレイアード叢書の新版『マラルメ全集』が出たこと。『ディヴァガシオン』を翻訳したときは、まあ渡辺君などは原稿の切り貼りをじかに見て翻訳をしたのだけれど、たとえば松室さんも『詩の危機』の翻訳では「ルヴュ・ブランシュ」誌や「ナショナル・オブザーヴァー」紙などの初出を参照して古いプレイアード版ではわからない切り貼りによる決定稿のつくり方を考えて翻訳し、解題・註解を書いている。今度の全集の最後の配本は『詩・イジチュール』の第Ⅰ巻ですが、新しい全集の編者マルシャルの註が前に比べてずっと詳しくなったことは大きいですね。こうしてやっと、詩をはじめとしてマラルメの全貌が翻訳として提出できた。
渡辺 一九七六年夏に出た雑誌「無限」の座談会もこの三人でやっていて、その時点で私はクローデルについての論文を出し、次はマラルメをやろうと思っていた。ただ、私の関心は、一八八五年以降の晩年の散文、マラルメ自身の言葉を借りれば「批評詩」を書いていくマラルメでした。演劇というか、広く舞台芸術の問題が、マラルメの問題提起のなかで決定的な重要さを孕んでいただろうという見当がついていたからです。演劇のことでマラルメに新しい問題の系を読んだのはクローデルぐらいでしたから。
幸いなことに一九七三年の時点で、パリ大学付属ジャック・ドゥーセ文学図書館に入った「モンドール文庫」を、当時の司書のフランソワ・シャポン氏の好意で調査することができて、まだ「漆塗りの抽斗」のタイトルになっている『パージュ』、『詩と散文』、そしてドマン版の『詩集』の「貼付け」を見ることができた。マラルメは、雑誌等の媒体に発表した原稿を単行本に入れるに際して、書き写すのではなく、該当箇所を切り抜いて大きなアルバムに貼っていく。まさに「コラージュ」であり、エクリチュールの線構造を宙吊りにして、空間的な戯れとして読み直していく。あの作業を見てしまったのが、私のマラルメが生まれる決定的なきっかけでした。
われわれ三人がパリにいたのは六八年の大騒乱のときで、雑誌「テル・ケル」一派が、デリダかぶれでむやみとマラルメの後期の散文を引用した。ところが引用箇所は常に同じだったし、当時のプレイアード版から引いている。自分で一次資料から当たり直す手続きは不可欠だったのです。
マルシャルの学位論文『マラルメの宗教』は一九八八年で、筑摩の『全集Ⅱ』は一九八九年二月ですから、私個人としては、『ディヴァガシオン』関連でマルシャルに負う所はないわけです。彼の「プレイアード版」第二巻は二〇〇三年で、テクストの生成過程やその変形遊戯の意味を深追いはしていませんから、筑摩の『全集』版が、世界で一番詳しく厳密だと言えます。
こんなことを言うのも、近年は日本人で、マラルメについてフランス語で論文を書く若い人も出てきていて、それ自身は結構なことですが、フランス人が日本語の文献なんか読めないという理由で、そういう局面を全く無視して平気でいる。マラルメについては、フランス語で論文を書いているほうが楽だと思う。日本語で論文を書くとなると、引用は日本語になっていなければならないし、そこで訳した日本語が、地の文の日本語とダイナミックに結びつくような詩の翻訳となると非常に難しいからです。
菅野 とくに詩の翻訳についていえば、ひとつの言語、あるいは言語と言語の連辞は、角度を変えると宝石がちがった光を放つように違って見えてくる、つまり多面的であるとマラルメは考えていた。翻訳でそれを全面的に移しかえることはほとんど不可能です。マラルメは翻訳だけでは、確かな姿を伝えることは日本語ではできない。
この全集では註釈をとくに重んじて、マラルメのさまざまな作品に関し、ちがった面から光が当てられるということを明瞭にしようとめざした。それによってはじめてマラルメの新鮮な姿が、かなりの程度見えてくることになるはずです。読者の方が、翻訳だけ読んで「マラルメはわからない」と言っていただいては困るので、それぞれの註釈を丁寧に読んでいただきたい。その上でまた訳に返って、その間の一種の相互作用で読んでいただけるとありがたいなと考えます。
渡辺 晩年のソネのある種のものは、十四行にあまりにも多義的な層が仕掛けられているので、複数の訳文でも作らなければならないものもあります。ただマラルメは、そういうソネであっても、自分で声に出して読む。「エロディアード――舞台」や『半獣神の午後』は、初めに「舞台向け」であったからというだけではなく、身体性を前提にした演戯が、定型韻文の基底部に働いていると、私は考えます。だから、声に出して読めなければいけないと思う。
自分の主要な仕事としてマラルメを選んだ時に、東大の仏文大学院の授業を持っていた。そのときに出ていた世代にはすぐれた学生がいて、「芝居鉛筆書き」から始めて、後期のソネも、『イジチュール』も取り上げて、最後には『エロディアード詩群』と『半獣神』変容をやりました。相互にクリエイティブな刺激になるという幸いな時期だった。『全集』で私が受け持っているかなりの部分は、当時の院生に負う所は多いし、彼らに捧げたいという思いです。
不可解な詩の謎と魅力
清水 マラルメの詩を読むときに、ひとつの詩について、たくさんの註釈がある。それらの註釈を参照しながら、ああでもない、こうでもないと考えていくこと、あれはほとんど快楽だね。これまでフランス、あるいはヨーロッパでいろいろなかたちで書かれた註釈本がなければ、少なくともぼくにはマラルメの詩はわからなかった。「プローズ」や後期のソネなどはひどく難解だから。
ポール・ヴァレリーはマラルメ論をたくさん書いているけれども、彼は「マラルメという人の詩は、その異様なサンタックスによって異様な詩句の存在それ自体が、詩句を繰り返して口ずさむことをいわば強制してきて、その強制をとおして意味がほの見えてくる」ということを言っている。
さすがのヴァレリーもはじめてマラルメの詩を少年の時に読んだ時には、わからなかったらしい。いったいなぜああいう文章、ああいう難しい詩を書くようになったんだろう。
菅野 「ボードレールの墓」に関してヴァレリーは厳しいことを言ってますね。じつに不可解であると。ほかにもそういう感想を持たされる詩がある、と。
では、なぜそういう詩を書くのか――ひとつ考えられることは、われわれが生きている世界と言語との間に、予定調和なんてものはない、世界と世界を考える人間とのあいだに一種の闇があるということを、マラルメはどこかで思い知らされた、まだ若い時に。そこから出発して言語の特性についていろいろ考えていくという過程があり、一方また世界といっても、もちろん毎日生きて、食べて、遊んで、という日常的な世界ではない、もっと広い世界、精神の活動する宇宙の絶対とは何かということを、少し破天荒な形で考えたんでしょうね。そういう世界と言語活動の間の溝が、結局ああいう詩なり散文なりを生み出す大きな動力になったんだと思います。
宇宙の構造というか、宇宙とはなんだろうと考える場合、マラルメは太陽とか月とか、ある意味で簡単な要件で考える面があります。その簡単な構造を突きつめてたとえば太陽神話とぶつかる。夕日の風景を見て、その日没の風景はいったいなんであるか、その謎を考えるのが世界の神秘を解くことなんですね。その突きつめ方と、言語の特性を考えていくということ、それは生涯並行していたと思う。マラルメ自身の悩んだ解決のつかない問題、解決がつかないからこそ追求し、探究する。そういう姿勢で一貫している。それが貴重な意味を孕んだ難解さの根源だと思うんです。
渡辺 『エロディアード詩群』だと、典型的に現れてくるわけだけど、マラルメは一行のアレクサンドランの脚韻の部分の単語だけを置く。サンタックスも意味の繋がりも分からないで、脚韻だけきめていく。考え方としては、アルバムに貼り付けていく作業と同じで、言説の線コードを壊そうとするのでしょう。ヴィクトル・ユゴーの抒情詩のように、アレクサンドランが、ユゴーという人の生理的な排出のようになって出現してくるものは断固廃絶する。それではマラルメの詩に、身体性がないかというとそんなことはない。六〇年代の精神的危機を特徴づけている身体的な症候や、その身体が「詩句」と関わる時に破局に隣接する体験などを考えると、頭脳や精神だけではマラルメは論じられない。『半獣神の午後』に到る変形作業を追い直してみて、それは痛感しましたし、マラルメの詩を理解するひとつのやり方は、声に出して読むことだとさえ思う謂れもそこにあります。極言すれば、音声的パフォーマンスの「譜面」のような局面を持っている。それを極端に突きつめたのが、『賽の一振り』で、マルシャルも期せずして同じようなことを言っている。私自身もゼミでやってみせたことですが、『半獣神の午後』のアレクサンドラン詩句を、サンタックスに沿って解体しつつページの上に並べて行くと、『賽の一振り』のような詩句の空間が現れる。それを、さっきは「譜面」と呼んだのです。
詩句としてのパフォーマティブな要素がマラルメの詩の重要な魅力の一つだということは、強調しておきたいと思います。
清水 『賽の一振り』の翻訳では、一応は見開き二ページの左上から右下へと斜めに読んでゆくことを基本にして考えてゆくんだけれど、そういういわば音声的な流れのなかで、なにしろ星座的にばら撒かれた詩句の逆の斜めや左右の並び方まで考慮しなければいけないのには、困難をきわめましたね。
二十世紀文学を準備したマラルメ
菅野 一九五〇―六〇年代に、ソレルスはじめさっき槍玉にあがった「テル・ケル」一派や周辺の人たちがよく引いていたのは、書簡や「リーヴル」ですね。だいたい皆同じところを引く。しかし、その時期からマラルメの読み方が、フランスの若い作家あるいは批評家の間で変わってきたことは事実です。さらにソシュールを見直す試みが伴なって、マラルメに対するアプローチの仕方が変わってきた。その場合、問題は言語構造。それが文学のあり方の根源に影響して、変革者としてのマラルメの位置がいっそうはっきりしたということもありますね。
清水 逆に、マラルメは二十世紀文学を準備したんじゃないかという感じがします。文学というものに対する考え方がマラルメにおいては、彼がイデーという言葉で表すようなものと深くかかわっている。他方でそういういわば形而上的なものを文学と言語との関係において、二十世紀後半のフランス文学者たちは改めて非常に深く考えるようになった。それはマラルメの直接的な影響であったとまでは言えないにしても、マラルメが確実にその先駆者であったことは事実だろう。
渡辺 マラルメの演劇論などは、長いこと人々は読まなかった。レヴィ=ストロースが最初に日本に来た時に、いま「芝居鉛筆書き」をやっていると言ったら、即座に、「ああ、あの中にはバレエについてすばらしい文章があるね」と言われた。いきなりこういう反応が返って来たのは、私の会ったフランス人として最初です。
七〇年代後半になって、評論家のアルフレッド・シモンが、「太陽劇団」などが実現した「舞台芸術における祝祭性」に着目して、それにマラルメを接続した。マラルメの「未来の群衆的祝祭的演劇」を、舞台創造の現場の問題意識として取り返そうという企てが、ようやく生まれ出した。時代の変革の地平が、一世紀近く前に書かれてほとんど誰も「真に受けなかった」テクストを、忘却の淵から蘇らせたのです。
菅野 今度の全集に関して、「註解をこそ読んでくれ」と言いましたが、訳者によってそれぞれ註解のやり方がちがう。マラルメ山を登るのにいろんな登山道があるように、それぞれの訳者のマラルメの読み方がある。それほど作品は多面的なんです、そこでそれぞれに独特の個性を持ったマラルメ読解になるんでしょう。基本的なところに通底するものはあっても、細部がずいぶんちがうなと思う読者がきっといるでしょう。
根本的な中心をどう訳者が読んでいるか。そのうえで読み方の差異が出てくるということを、ぜひ理解していただきたい。どうしてこんなにちがうのか、その意味を考えてほしいと思います。読解の差を生み出すのは何かというのは、マラルメの本質に関わる重要な問題なんですから。
清水 編集委員は五人だったけれど、全巻完結に時間がかかったために、そのうち阿部良雄・松室三郎と二人が亡くなってしまった。とくに、松室さんは生涯をマラルメの詩一筋に捧げてきたのに、あるいはそのために結局、亡くなったときには、担当分の訳は全部できていたけれども、註釈に関しては彼がいちばん大きなテーマとしていた「エドガー・ポーの墓」の註釈が書かれてなかった。ポーとマラルメとの関係については、彼は本が一冊書けるくらいの造詣があったわけで、その造詣が災いして最後に残ってしまったんですね。
今度の第Ⅰ巻に、われわれ編集委員が全員マラルメについてのイニシエーションを享けた鈴木信太郎先生に献げるという献辞が入っていますけれども、ぼくは個人的には、そこに、この本は松室三郎という男の生涯の願望だったということを小声で言いそえたいと思う。
渡辺 自分のやったことでいうと、やはり『イジチュール』は大変でした。新しいプレイアード版のマルシャル校註版は、このテクストの読解の上で決定的な一歩を踏み出したことには違いない。マラルメの消去した部分でも意味のありそうな部分は、とにかく全て起こして見る、という選択ですから。一次資料との関係で言えば、『イジチュール』だけはマルシャルによるしかない。幸いボニオ資料は、個人の蒐集家からジャック・ドゥーセ図書館に入ったわけですが、ボンヌフォワも告白していたように、ちょっとやそっとの読解では、この「幻想獣」は、取り押さえることなど出来ない。マルシャルのプレイアード新版が、それをようやく実現した。ただ、見開きページに、「起こし」の一応の決定稿と、その「多層的消去を含む草稿状態の復元」を眺めて、一体これがすっと分かる人はいるのか。
この「プレイアード新版」の『イジチュール』も、ポケット・ブック版『イジチュール、ディヴァガシオン、賽の一振り』(二〇〇三年)に入っている。しかし読まされてすっと分かる人がいるのだろうかという疑問と同時に、ボニオ版はともかく八十年間というもの、あれしか読めなかったのだし、ブランショにせよデリダにせよ、読んでいたのはボニオ版でしょう。そこで去年の八月に、マルシャル版の翻訳・註解の校正が始まった頃だったと思います。清水徹さんに、「やっぱり、ボニオ版も訳しておいたほうがいいのじゃないかな」と相談をしようと思ったら、清水さんのほうから「今頃になって酷だけど、ボニオ版も訳しておいた方がよかったんじゃないか」と言われて、ボニオ版は一応の翻訳は作ってあったし、マルシャルの校註版との対比も所詮はしなければならないことなので、一気に訳してしまった。こうして世界中の『マラルメ全集』で、マルシャル版とボニオ版の両方が見られるのは筑摩版だけということになったのです。
菅野 『イジチュール』など、未完の、しかし重要な作品をあんなにたくさん持っている詩人も珍しい。イジチュールがなぜあそこで終わってしまったかという問題は、マラルメ研究の大きなテーマになりうるでしょうね。「リーヴル」だってなぜ完成しなかったのか。未完ないし中絶の作品にあれほど重大な意味があるという人は、ほかにそうはいない。作品の絶対ということを目指しすぎた必然の結果なんでしょうけど。
清水 「リーヴル」に関する断章も、一部分は彼が演劇に関心をもっていた時期につらなる独特な形式の朗読会に関連しているし、残る部分は「世界は一冊の書物に到りつく」という《絶対の書物》についての果てしない瞑想ですね。
ところで、割合最近に〈火曜会〉のことを書いた本が出て、それを読んだんだけど、マラルメという人は、なんというか、人柄のいい人ですね。オネットオムですよ。手紙なんか読んでもそう思わないではいられない。
菅野 たいへん誠実だよね。未刊の作品にしてもできない理想と分かりつつ、不可能であることを充分に見極めたうえで、しかも実践するわけだから。
清水 ヴァレリー、ジッド、プルースト、クローデルの四人がマラルメの門からでたわけだから、それはすごいことですよ。
渡辺 クローデルなんか、およそ気質や言語感覚からして合うはずがないことは、お互いによく知っているのだけれども。後期の散文、つまりマラルメの言う「批評詩」を、クローデルは周期的に読み直す。『ディヴァガシオン』はいつも持ち歩いていて、中国や日本の文化を理解するうえでも、補助線として必ずマラルメがあるんです。
清水 そこはヴァレリーとちがう。ヴァレリーはマラルメの散文については、ほとんど書いてない。ヴァレリーに関しては、むしろマラルメの詩の厳密さとその人柄を語るんだよね。
渡辺 あれだけいろんな人がローマ街のアパートに、毎火曜日に通って……。
菅野 フランス人だけじゃなく、ホイスラーとか、アーサー・シモンズとか、シュテファン・ゲオルゲとか、いろんな国外の連中もきた。よほど、深遠な牽引力を持っていた人なんでしょうね。
清水 マラルメという人には会ってみたかったな。それにしてもふしぎだね、みんなが〈火曜会〉〈火曜会〉と言うけれど、ぼくの読んだ本にしても、外的な事情は書いてある、けれどもそこで何がしゃべられていたかということを書いた人は、ほとんどいないんです。
終わりなき象形文字
渡辺 マラルメの立てた問題意識は、いろんな意味で自分の問題意識をはっきりさせるとか、活性化させるために重要でした。フーコー的に言えば、「問題形成」ですね。
マラルメの散文でも韻文でも、あの特殊なフランス語は、私は好きです。一種の象形文字みたいなものかとも思う。音声も身振りも伴った象形文字です。こっちの記憶の中にあれだけ刻み込まれてくるというのは。およそ突飛な組み合わせのようですが、アルトーの地平を、すでに拓いている。まだまだマラルメについては考えなきゃいけないことがたくさんあると思っています。
清水 座談会のしめくくりとしては、マラルメの中でぼくの好きな言葉をあげたいな。
たとえば、「書くということ」について、「インク壜」の有名な比喩があるでしょう。「透明なクリスタルの底に黒い滴がたまっていて、その黒い滴で白い紙の上に書くことが、つまり書くということだ」という。あれなんぞは、マラルメの人間観、あるいは、宇宙観を非常にはっきりとさせている。
『音楽と文芸』という論文を書いているけれど、マラルメにとって黒いインクの滴による文芸は人間の暗い部分に結びつくものであって、音楽は黄金の燦然たる耀き、詩の音楽が拮抗しなければならぬものだったわけです。そういうことをマラルメは、あのインク壜の比喩で非常にはっきりと表している。
それからもうひとつ好きなのは、現在ということについて、「われわれはいま汽車に乗ってトンネルの中を通っているが、やがてその長いトンネルを出た先には、壮麗な駅に到着するであろう」という言葉ですね。マラルメは自分があくまでトンネルの中を生きている、という意識を持っていた。それはマラルメを理解するうえでずいぶん大きなことなんじゃないかと思う。
菅野 文学とはなんだろうと考えても分からないときにマラルメと出会ってなんとなく分かったのは、マラルメという人は、世界とは何であるかとか、たとえばこの星は何を意味するのか、自分の生きている事実をふくめて、森羅万象を根本的に、根源的に、本質的に考える人だということでした。それからまた、言葉という毎日使っている道具について、これが本当に完全な表現の道具であるのか、豊かな充実したものであるかどうかを徹底的に考えつめる人らしいと思った。要するに、文学に関わるすべての事柄を絶対的な基準で思考する人物なんですね。
そういう本質的な問題に立ち返らせてくれたのは、ぼくにとってはマラルメです。マラルメの存在が、いつも自分の真中か隅のほうか、とにかくつきまとっていてほしいけれども、しかしマラルメのやったことがどこまで理解できているかという自信はいまもってない。余命があるかぎり、どこまで考えることができるか分からないけれども、この全集は終わったけれども、ぼくにとってマラルメはいつまでも終わらないだろうという気がします。
マラルメの不思議なところは、どのソネ、どの散文でも、きょう読んで「ああ、こうなのか」と思いますね。ところが、翌日、また読む、するとちがって見えてくる。日日新しくなる。それがマラルメの豊かさの秘密でもあると思います。
(速記 長尾玲子)
『マラルメ全集 全5巻・完結 最終配本 Ⅰ詩・イジチュール』 詳細
ご注文方法はコチラ
トップに戻る
バックナンバー
- 第638号24年5月号
- 第637号24年4月号
- 第636号24年3月号
- 第635号24年2月号
- 第634号24年1月号
- 第633号23年12月号
- 第632号23年11月号
- 第631号23年10月号
- 第630号23年9月号
- 第629号23年8月号
- 第628号23年7月号
- 第627号23年6月号
- 第626号23年5月号
- 第625号23年4月号
- 第624号23年3月号
- 第623号23年2月号
- 第622号23年1月号
- 第621号22年12月号
- 第620号22年11月号
- 第619号22年10月号
- 第618号22年9月号
- 第617号22年8月号
- 第616号22年7月号
- 第615号22年6月号
- 第614号22年5月号
- 第613号22年4月号
- 第612号22年3月号
- 第611号22年2月号
- 第610号22年1月号
- 第609号21年12月号
- 第608号21年11月号
- 第607号21年10月号
- 第606号21年9月号
- 第605号21年8月号
- 第604号21年7月号
- 第603号21年6月号
- 第602号21年5月号
- 第601号21年4月号
- 第600号21年3月号
- 第599号21年2月号
- 第598号21年1月号
- 第597号20年12月号
- 第596号20年11月号
- 第595号20年10月号
- 第594号20年9月号
- 第593号20年8月号
- 第592号20年7月号
- 第591号20年6月号
- 第590号20年5月号
- 第589号20年4月号
- 第588号20年3月号
- 第587号20年2月号
- 第586号20年1月号
- 第585号19年12月号
- 第584号19年11月号
- 第583号19年10月号
- 第582号19年9月号
- 第581号19年8月号
- 第580号19年7月号
- 第579号19年6月号
- 第578号19年5月号
- 第577号19年4月号
- 第576号19年3月号
- 第575号19年2月号
- 第574号19年1月号
- 第573号18年12月号
- 第572号18年11月号
- 第571号18年10月号
- 第570号18年9月号
- 第569号18年8月号
- 第568号18年7月号
- 第567号18年6月号
- 第566号18年5月号
- 第565号18年4月号
- 第564号18年3月号
- 第564号18年3月号
- 第563号18年2月号
- 第562号18年1月号
- 第561号17年12月号
- 第560号17年11月号
- 第559号17年10月号
- 第558号17年9月号
- 第557号17年8月号
- 第556号17年7月号
- 第555号17年6月号
- 第554号17年5月号
- 第553号17年4月号
- 第552号17年3月号
- 第551号17年2月号
- 第550号17年1月号
- 第549号16年12月号
- 第548号16年11月号
- 第547号16年10月号
- 第582号19年9月号
- 第546号16年9月号
- 第545号16年8月号
- 第544号16年7月号
- 第543号16年6月号
- 第543号16年6月号
- 第542号16年5月号
- 第541号16年4月号
- 第540号16年3月号
- 第539号16年2月号
- 第538号16年1月号
- 第537号15年12月号
- 第536号15年11月号
- 第535号15年10月号
- 第534号15年9月号
- 第533号15年8月号
- 2019年8月号 No.581 目次はこちら
- 第532号15年7月号
- 第565号18年4月号
- 第531号15年6月号
- 第530号15年5月号
- 第529号15年4月号
- 第528号15年3月号
- 第527号15年2月号
- 第526号15年1月号
- 第525号14年12月号
- 第524号 14年11月号
- 第523号14年10月号
- 第522号14年9月号
- 第521号14年8月号
- 第520号14年7月号
- 第519号14年6月号
- 第518号14年5月号
- 第517号14年4月号
- 第516号14年3月号
- 第515号14年2月号
- 第514号14年1月号
- 第513号13年12月号
- 第512号13年11月号
- 第511号13年10月号
- 第510号13年9月号
- 第509号13年8月号
- 第509号13年8月号目次
- 第508号13年7月号
- 第507号13年6月号
- 第506号13年5月号
- 第505号13年4月号
- 第504号13年3月号
- 第503号13年2月号
- 第502号13年1月号
- 第501号12年12月号
- 第500号12年11月号
- 第499号12年10月号
- 第498号12年9月号
- 第497号12年8月号
- 第496号12年7月号
- 第543号16年6月号
- 第495号12年6月号
- 第494号12年5月号
- 第493号12年4月号
- 第492号12年3月号
- 第595号20年10月号
- 第491号12年2月号
- 第490号12年1月号
- 第489号11年12月号
- 第488号11年11月号
- 第487号11年10月号
- 第486号11年9月号
- 第485号11年8月号
- 第484号11年7月号
- 第483号11年6月号
- 第482号11年5月号
- 第480号11年4月号
- 第479号11年3月号
- 第478号11年2月号
- 第478号11年1月号
- 第477号10年12月号
- 第476号10年11月号
- 第475号10年10月号
- 第474号10年9月号
- 第473号10年8月号
- 第472号10年7月号
- 第471号10年6月号
- 第470号10年5月号
- 第469号10年4月号
- 第468号10年3月号
- 第467号10年2月号
- 第466号10年1月号
- 第465号09年12月号
- 第464号09年11月号
- 第463号09年10月号
- 第462号09年9月号
- 第461号09年8月号
- 第460号09年7月号
- 第459号09年6月号
- 第512号13年12月号
- 第456号09年3月号
- 第458号09年5月号
- 第455号09年2月号
- 第457号09年4月号
- 第548号16年11月号
- 第548号16年11月号
- 第454号09年1月号
- 第520号14年7月号
- 対談
- 第509号13年6月号
- 第524号14年11月号
- 第548号16年11月号
- 第565号18年4月号
以前のPRちくま
「ちくま」購読料は1年分1,100円(税込・送料込)です。複数年のお申し込みも最長5年まで承ります。 ご希望の方は、下記のボタンを押すと表示される入力フォームにてお名前とご住所を送信して下さい。見本誌と申込用紙(郵便振替)を送らせていただきます。
電話、ファクスでお申込みの際は下記までお願いいたします。
-
受付時間 月〜金 9時15分〜17時15分
〒111-8755 東京都台東区蔵前2-5-3