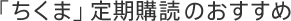筑摩書房70周年記念特別講演 「筑摩選書」創刊への期待/永江朗
筑摩書房は今年、創業七〇周年を迎え、その記念企画として、一〇月一五日、「筑摩選書」を創刊致しました。そこで、社史の執筆をお願いしている永江朗さんに、一連の取材・調査のなかから、「筑摩選書」に至るまでの、小社ペーパーバック教養書の歴史を振り返っていただきました。
「もうからなくていい」
創業三〇周年のとき、和田芳恵さんが『筑摩書房の三十年』という社史をお書きになっています。これは非売品だったので、ほとんど知られてはいないと思いますが、非常に面白い。そして取材をしてみて改めて、筑摩書房は、会社としても非常に面白いということが分かりました。
なぜユニークな会社なのかといえば、まず、創業者の古田晁が、「もうからなくていい。いい本を出せばいい」という人だったのです。最初からビジネス度外視。筑摩書房は一九七八年に倒産しますが、それも当然かもしれない。最初からビジネス抜きなのですから。
では、ビジネス抜きで、どのように成り立つのかというと、企画が失敗するたびに、古田さんは、信州に持っていた山を売っていたらしいです。山林をお金に換えた。わたしは、これは冗談だと思っていました。いわゆる「都市伝説」といいますか、出版界にいろいろある伝説の一つにすぎないだろうと思っていたのです。ところが、いろいろな人に取材をするなかで、古田さんから直接、「山一個、いくらで売ってきたよ」という話を聞いた、そういう具体的な証言も出てきました。
どん底から奈落へ
筑摩書房七十年の歴史の中で、よかった時代というのは、あまりありません。どちらかというと、苦しい時代ばかりです。
『筑摩書房の三十年』は、いちおう一九七〇年までを書いていることになっているのですが、大体五八年くらいで、記述はほとんど終わっています。六〇年代については、一〇ページくらいで飛ばしているのです。その頃までは、どん底時代でした。後に倒産したときに、労務倒産、つまり「給料が高すぎるから倒産したんだ」というように言われたそうですが、給料がよかったのは、たかだか十年ぐらいですね。六〇年ごろまでは、食うや食わずです。
ようやく明かりが見えてくるのが、六〇年代に入ってからです。日本経済もぐっと上向きになり、筑摩書房も出版社としてのブランドイメージを確立していくことになります。
しかし、調子に乗りすぎてはだめですね。一九六六年に古田晁が退任。その後、筑摩書房は、それまでの上り調子だった数年間を、あたかも自分たちの実力で勝ちえた好景気だと勘違いして、いろいろな企画に手を出します。目指すは総合出版社。おそらく、講談社のような出版社にしたいと思っていた経営者がいたのではないでしょうか。
その無理がたたって、七〇年代半ばは、自転車操業というよりもオートバイ操業です。ガソリンがなくなったら、バッタリ。そのバッタリが一九七八年でした。
ところが、全国の書店が筑摩書房を助けよう、救済しようという運動を起こします。マスメディア、特に新聞が、それを報じて、さらに応援が拡がった。それによって、奈落の底から這い上がり、会社更生を果たすことができたのです。
もちろん、時代のタイミングも良かったのだと思います。一九七八年に倒産して、それから十年たたないうちに、日本はバブル経済に入るわけで、それにうまく乗れたということもあります。
大衆的な知識欲に応える
再生にあたっては、ペーパーバックが大きな原動力になったといっていいと思います。
これは裏返していうと、日本の読書界が、一九七〇年代後半から八〇年代、九〇年代という時代の中で、ハードカバーの厚い、重い、重厚長大なものだけではなく、ペーパーバックを読みたい、それを所有したいという方向に、少しずつ変わっていったということでもある。そこに、筑摩書房はうまく乗ることができた。
ただし筑摩書房は、意外に早くからペーパーバックの教養書を手掛けていました。最初が「筑摩選書」。これは一九四八年からスタートしていますが、一九五〇年で終わります。いきなり縁起が悪いですね(笑)。「筑摩選書」に限らず、筑摩書房はどうも見切りが早いのです。まあ、これも、筑摩という会社の素晴らしさのひとつですね。だめなものをだらだら続けて深みにはまるということをしないで、パパッと見切ってしまう。この逃げ足の速さは、美徳といっていい(笑)。
この「筑摩選書」は、おそらく「岩波全書」を意識したのではないかと思います。岩波的な教養とは別の教養を打ち立てたい。筑摩書房には常にそのような気持ちがあったように見受けられるのですが、それが、すでに一九四八年にあった。ちなみにラインナップは、島崎藤村『若菜集』、田辺元の『カントの目的論』、和辻哲郎の『ニイチェ研究』などで、今出しても全然おかしくないシリーズですね。
それから一九六二年に、「グリーンベルト」というシリーズを始めます。このシリーズは新書判です。出版史の中では忘れられたシリーズなのですが、一九九四年スタートの「ちくま新書」に先駆けて、その三十年も前に、新書を手掛けていたわけです。
実はその少し前、五四年に光文社が「カッパ・ブックス」を創刊して大変な話題になりました。「カッパ・ブックス」はアンチ「岩波新書」です。「岩波新書」とは違う、もっと大衆的な知識欲に応えようというのが、「カッパ」でした。「グリーンベルト・シリーズ」も、アンチ「岩波新書」の筑摩書房なりの解答だったといえると思います。吉川幸次郎『漢文の話』、小田実『日本の知識人』など、ラインナップがいいですね。着目点はとてもいいのだけれど、グリーンベルトというネーミングは、どうでしょう。いまいちだと思いますね。筑摩書房、わりとネーミングが下手、といいますか、地味めですね(笑)。
一九六八年には「学問のすすめ」という入門シリーズを始めます。これも筑摩的には「こんな大胆なタイトル付けちゃった!」と思ったのでしょうが、世間では「ちょっと地味めだよね……」という印象だったのでは(笑)。
「筑摩叢書」の達成
一般の読書家にとって最も印象深かったのは、一九六三年にスタートした「筑摩叢書」だと思います。カバーの色合いといい、たたずまいといい、ベテランの書店員だったら、誰もが覚えているでしょうし、多くの人が、一度は「叢書」を読んだことでしょう。話題になったものには、マーク・ゲインの『ニッポン日記』、中村光夫『明治文学史』、唐木順三『無用者の系譜』など。今振り返っても非常に画期的なものでした。
「筑摩叢書」は六三年にスタートして、九二年まで続きました。ただ、叢書は親本があって、それをペーパーバック化する、いわゆるディフュージョン版のシリーズです。必ずしも書き下ろしではなかった。
でもいま振り返ると、これが書き下ろし選書の下地づくりになった、といってもいい。「NHKブックス」「新潮選書」、あるいは「角川選書」といったシリーズものに、大きなヒントを与えたのではないかと思います。
なぜこのとき、「筑摩叢書」を書き下ろしのシリーズに転換しなかったかというと、実は別のシリーズがありました。それが、一九六九年にスタートした「筑摩総合大学」です。これは、六九年から七三年まで続きました。当時の編集者(OB)に取材したところ、二つのキーワードが出てきました。
一つは、ニュー・アカデミズムを標榜していたということ。八〇年代前半に、浅田彰や中沢新一、四方田犬彦らをスターにしたニュー・アカデミズムブーム、日本流のポストモダン・カルチャーのブームが起こりますが、それとは少し違う意味で、いわゆるタコツボ化したアカデミズムを超えて、「越境する知」のようなことを、当時、すでに考えていたのだそうです。
もう一つは何か。「隠しテーマは、打倒岩波書店だった」と、やっぱりそのOBは語っていました。
田中美知太郎『学問論』、都留重人『現代経済学』などがラインナップです。これは、全部で一〇〇タイトルを構想していたそうですが、残念ながら、だんだんうまくいかなくなった。ほとんどが書き下ろし、しかも著者は大学の教師。大学の教員はなかなか原稿を書きませんから、原稿が入らなくなり、定期的に刊行するのが難しくなった。それで、三分の一くらい刊行したところで終わってしまいました。
「筑摩」から「ちくま」へ
ターニングポイントになるのが、一九七八年の「ちくまぶっくす」です。ここで初めて「ちくま」が平仮名になります。その前に「ちくま少年図書館」というのがありますが(七〇年)、大人向けのものとしてはこれが初めて。
これは大変な議論を呼んだそうです。「ちくま」にするなんて堕落である。そのように思った人たちがいた。漢字の「筑摩」を捨てるのか、「筑摩」の歴史を捨てるのか。創業者の古田晁が他界して、すでに五年たっていましたから、「古田精神を忘れたのか」と。それぐらいの大転換だったわけです。
しかしこの後、「ちくまぶっくす」「ちくまセミナー」「ちくまライブラリー」「ちくまプリマーブックス」「ちくま文庫」「ちくま学芸文庫」「ちくま新書」「ちくまプリマー新書」と、ずっと平仮名の「ちくま」が続きます。単純に、ブランドイメージとして、やわらかくしたい、やさしい印象にしたい、ということだけではなくて、時代の空気のようなものを敏感に察知していたのだと思います。
七八年は、奇しくも筑摩書房が倒産した年です。「ちくまぶっくす」のスタートは五月、タイトルが決まったのは、もっと前でしょうから、よもや、その数か月後に会社がつぶれるとは予想していなかったでしょう。
漢字から平仮名への転換が、当時の日本社会の中での教養というもののあり方を象徴しているように思います。それまでの漢字の「教養」ではなくて、平仮名の「教養」、アカデミズムだけでなく、一般大衆のための教養ということを、もっと真剣に考えていくべきではないか。そういった時代の空気・気分を、うまくとらえるようなシリーズを出すことができた。それが成功だったと思います。
たとえば一九八三年に、「ちくまセミナー」から『思考の整理学』という本が出ています。これは後に文庫になって、昨年、ミリオンセラーを達成しました。なんと二十数年かかっています。そのほかにも、「セミナー」「ライブラリー」「プリマーブックス」の中からいくつもの話題作を出すことができたわけです。
生活者の腑に落ちる「教養」
筑摩書房の教養書のペーパーバックシリーズに一貫しているものは何か。つまり、現代の日本人にとって必要とされる教養は何なのだろうか。
それは、従来のアカデミズムの枠に収まっている教養でもなければ、ビジネスマン、サラリーマンに必要とされている教養とも、また少し違う。もう少し、生きることそのものにズシンとくるような、生活者にとって腑に落ちるような教養を、筑摩のペーパーバックのシリーズは、ずっと提供してきたのだと思います。
「筑摩」から「ちくま」への転換、そこにあった「教養」そのものの転換が、「ちくまぶっくす」がスタートした七八年から、この数十年の中に起きました。
日本の社会は、見かけ上どんどん豊かになっていくけれども、いっぽうで、知的なものに対する飢餓感が募っていく。そこで、ペーパーバックのシリーズが入って、一定以上のマーケットを獲得することができました。
重厚長大なゴツイものだけではなく、常に知的好奇心の高い大衆に対して、どのようなものを提供するのかを、真剣に考えてきた。創業者の古田晁がいう「もうからなくてもいいから、いい本を出そう」という精神を受け継いで、読者、大衆、社会の要求に出版社として応えていくには、どうすればいいのか、そういったミッションを真剣に考えてのことでした。
だから、今度の「筑摩選書」の説明を伺ったときに、最初にいだいた疑問は「えっ、今度の筑摩は漢字なの?」これは一般読者にとっても、書店さんにとっても、結構ショッキングなことだと思うのです。この三十年、ずっと平仮名できたのに、なぜ漢字に戻るのか。
しかしだんだんわたしは、漢字のほうがいいかな、と思えてきました。この二十年、三十年、日本の知のありようが、もうかなりいいところまでいったから、別の知のありようを、ピッと立ててほしい。もうポストモダンも終わったのだから、新しい現代的な知を、「筑摩選書」で見せてくれたらと、そのように思いました。
選書ブームか
最近「選書ブームだ」という話を、何か所かで書いたことがあります。「また、ブームを捏造するのか」「実態がないじゃないか」といわれるかもしれませんが、日ごろ全国の書店さんを取材して歩き、バイヤーの方たちのお話を聞いていると、選書のような器に求めるものが非常に大きいと感じます。
ここ十年ほど、ずっと新書ブームが続いています。過去にも何度か新書ブームはありましたが、そのたびに、ある程度飽和状態になると、あっという間に淘汰されてきた。ところが、今回の新書ブームに関しては、撤退するところが少ない。休眠状態のところもありますが、全体としてレーベル数は、どんどん増える一方。新書は果てしなく過飽和し続けているのです。
書店さんでは、もう置ける棚がない。読者はどれを選んでいいのかわからない。その中で、突出した売れ行きのものだけが売れていく。ある種ランキング依存的なマーケットになりがちです。今の日本人が本当に求めている教養のようなものを、ストレートに、「このレーベルでこれを買えば安心だ」と打ち出しているものがなかなかない、という話をよく聞きます。
新書という器は、これはこれで非常に優れたものだと思いますが、もう新書だけでは、今の読者に応えきれないなというのが実感です。
さらに、既存の選書、ブックスの類いは、非常に融通無碍な扱い方ができる教養の器です。それを千円台で買えることは、読者にとって非常にうれしいことです。
「NHKブックス」「新潮選書」「朝日選書」「角川選書」などは、すでにブランドイメージが確立しています。あるいは、講談社「選書メチエ」。「選書メチエ」が出たとき、「これは人文書の価格破壊だ」という声が起こった。価格破壊がいいか悪いかという議論はあるでしょうが、やはり多くの人が、あのような教養書を広く読めるのは、とても素晴らしいことだと思います。 昨年は「河出ブックス」も創刊されて、健闘しています。
改めて見ると、四六判並装という器は、とてもいいなと思うのです。新書だと少し小さい。ハードカバーだと重すぎる。四六判というのは、日本人にとって、紙の本で最もスタンダードな形だと思います。やはり「本」といったときにわたしたちがイメージするのは、四六判なのですね。四六の並装という非常にベーシックなところに立ち返った選書は、とてもいいと思います。
実は書き手にとっても、選書やペーパーバックのシリーズがとてもありがたいのは、書店の棚に長く置いていただけるということなのですね。
また、選書は新書よりも読者層が絞り込まれます。読者を絞ることによって内容の自由度が増す。新書ほどたくさん売らなくても、もっと少ない部数、もっと少ない読者で、でも質の高いものを作り得るのが、選書というスタイルなのです。
(二〇一〇年七月八日、東京国際ブックフェアにて収録)
筑摩選書創刊 特設ページはこちら
ご注文方法はコチラ
トップに戻る
バックナンバー
- 第638号24年5月号
- 第637号24年4月号
- 第636号24年3月号
- 第635号24年2月号
- 第634号24年1月号
- 第633号23年12月号
- 第632号23年11月号
- 第631号23年10月号
- 第630号23年9月号
- 第629号23年8月号
- 第628号23年7月号
- 第627号23年6月号
- 第626号23年5月号
- 第625号23年4月号
- 第624号23年3月号
- 第623号23年2月号
- 第622号23年1月号
- 第621号22年12月号
- 第620号22年11月号
- 第619号22年10月号
- 第618号22年9月号
- 第617号22年8月号
- 第616号22年7月号
- 第615号22年6月号
- 第614号22年5月号
- 第613号22年4月号
- 第612号22年3月号
- 第611号22年2月号
- 第610号22年1月号
- 第609号21年12月号
- 第608号21年11月号
- 第607号21年10月号
- 第606号21年9月号
- 第605号21年8月号
- 第604号21年7月号
- 第603号21年6月号
- 第602号21年5月号
- 第601号21年4月号
- 第600号21年3月号
- 第599号21年2月号
- 第598号21年1月号
- 第597号20年12月号
- 第596号20年11月号
- 第595号20年10月号
- 第594号20年9月号
- 第593号20年8月号
- 第592号20年7月号
- 第591号20年6月号
- 第590号20年5月号
- 第589号20年4月号
- 第588号20年3月号
- 第587号20年2月号
- 第586号20年1月号
- 第585号19年12月号
- 第584号19年11月号
- 第583号19年10月号
- 第582号19年9月号
- 第581号19年8月号
- 第580号19年7月号
- 第579号19年6月号
- 第578号19年5月号
- 第577号19年4月号
- 第576号19年3月号
- 第575号19年2月号
- 第574号19年1月号
- 第573号18年12月号
- 第572号18年11月号
- 第571号18年10月号
- 第570号18年9月号
- 第569号18年8月号
- 第568号18年7月号
- 第567号18年6月号
- 第566号18年5月号
- 第565号18年4月号
- 第564号18年3月号
- 第564号18年3月号
- 第563号18年2月号
- 第562号18年1月号
- 第561号17年12月号
- 第560号17年11月号
- 第559号17年10月号
- 第558号17年9月号
- 第557号17年8月号
- 第556号17年7月号
- 第555号17年6月号
- 第554号17年5月号
- 第553号17年4月号
- 第552号17年3月号
- 第551号17年2月号
- 第550号17年1月号
- 第549号16年12月号
- 第548号16年11月号
- 第547号16年10月号
- 第582号19年9月号
- 第546号16年9月号
- 第545号16年8月号
- 第544号16年7月号
- 第543号16年6月号
- 第543号16年6月号
- 第542号16年5月号
- 第541号16年4月号
- 第540号16年3月号
- 第539号16年2月号
- 第538号16年1月号
- 第537号15年12月号
- 第536号15年11月号
- 第535号15年10月号
- 第534号15年9月号
- 第533号15年8月号
- 2019年8月号 No.581 目次はこちら
- 第532号15年7月号
- 第565号18年4月号
- 第531号15年6月号
- 第530号15年5月号
- 第529号15年4月号
- 第528号15年3月号
- 第527号15年2月号
- 第526号15年1月号
- 第525号14年12月号
- 第524号 14年11月号
- 第523号14年10月号
- 第522号14年9月号
- 第521号14年8月号
- 第520号14年7月号
- 第519号14年6月号
- 第518号14年5月号
- 第517号14年4月号
- 第516号14年3月号
- 第515号14年2月号
- 第514号14年1月号
- 第513号13年12月号
- 第512号13年11月号
- 第511号13年10月号
- 第510号13年9月号
- 第509号13年8月号
- 第509号13年8月号目次
- 第508号13年7月号
- 第507号13年6月号
- 第506号13年5月号
- 第505号13年4月号
- 第504号13年3月号
- 第503号13年2月号
- 第502号13年1月号
- 第501号12年12月号
- 第500号12年11月号
- 第499号12年10月号
- 第498号12年9月号
- 第497号12年8月号
- 第496号12年7月号
- 第543号16年6月号
- 第495号12年6月号
- 第494号12年5月号
- 第493号12年4月号
- 第492号12年3月号
- 第595号20年10月号
- 第491号12年2月号
- 第490号12年1月号
- 第489号11年12月号
- 第488号11年11月号
- 第487号11年10月号
- 第486号11年9月号
- 第485号11年8月号
- 第484号11年7月号
- 第483号11年6月号
- 第482号11年5月号
- 第480号11年4月号
- 第479号11年3月号
- 第478号11年2月号
- 第478号11年1月号
- 第477号10年12月号
- 第476号10年11月号
- 第475号10年10月号
- 第474号10年9月号
- 第473号10年8月号
- 第472号10年7月号
- 第471号10年6月号
- 第470号10年5月号
- 第469号10年4月号
- 第468号10年3月号
- 第467号10年2月号
- 第466号10年1月号
- 第465号09年12月号
- 第464号09年11月号
- 第463号09年10月号
- 第462号09年9月号
- 第461号09年8月号
- 第460号09年7月号
- 第459号09年6月号
- 第512号13年12月号
- 第456号09年3月号
- 第458号09年5月号
- 第455号09年2月号
- 第457号09年4月号
- 第548号16年11月号
- 第548号16年11月号
- 第454号09年1月号
- 第520号14年7月号
- 対談
- 第509号13年6月号
- 第524号14年11月号
- 第548号16年11月号
- 第565号18年4月号
以前のPRちくま
「ちくま」購読料は1年分1,100円(税込・送料込)です。複数年のお申し込みも最長5年まで承ります。 ご希望の方は、下記のボタンを押すと表示される入力フォームにてお名前とご住所を送信して下さい。見本誌と申込用紙(郵便振替)を送らせていただきます。
電話、ファクスでお申込みの際は下記までお願いいたします。
-
受付時間 月〜金 9時15分〜17時15分
〒111-8755 東京都台東区蔵前2-5-3