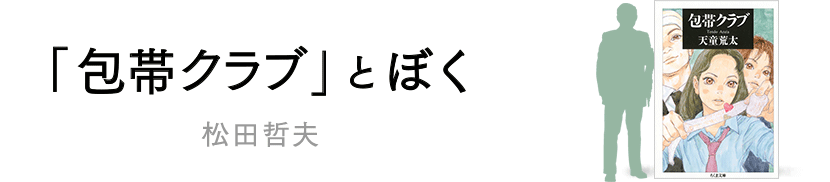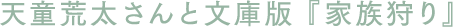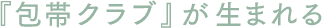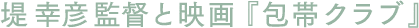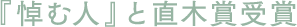そのすこし前のことです。番組開始前に控え室で雑談をしているとき、関根勤さんが「『家族狩り』は、胸が締め付けられるようなすごい小説でしたね」と話しかけてきました。当然、ぼくが読んでいるだろうと思っていたようです。実は、その時のぼくは未読だったのです。恥ずかしいので、ついついそれを言いそびれてしまいました。
それからしばらくして、店頭に天童さんの新刊『永遠の仔』が並びました。「関根さんより先に読まないと」と焦る気持ちで購入しました。
この作品は読み始めると、まず全編にはりつめている緊張感に圧倒されます。そして、こんなに救いのない小説はあっただろうかと思うくらい、胸がキリキリと痛んでくるのです。さらに、下巻の途中からは随所で涙がほとばしり出て、最後に近づいたころには、嗚咽までもらしていました。それなのに、読後にはたとえようもない爽快感があり、その余韻がいつまでも胸の中に響いているのです。
こういう作品を渾身の力を込めて書く作家がいて、それを刊行する編集者(出版社)がいる。同じ出版人として、また一読者として、心から感謝すると同時に、こういう作品が誕生する現場に立ち会えた編集者に嫉妬すら感じました。
一人でも多くの人に読んでもらいたいと、4月17日の「気になる一冊」で、「読んでいると、小説とは思えなくて、現実世界で起こっていることに、その場に立ち会っているような気持ちになりました。ぼくが『ブランチ』に出るようになってから読んだ小説の中では、文句なしのベスト1。今を生きているすべての人たちに読んでもらいたい」と、最大限の讃辞とともに、この本を紹介しました。すると、木村郁美アナウンサーは「登場する人たちを抱きしめたくなった」と、関根勤さんは「これを読んだ後は、他の軽い小説がしばらく読めなくなった」と、ぼくの言葉を熱くフォローしてくれたのでした。