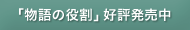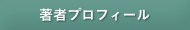『物語の役割』、この小さな本を通じて小川洋子さんは、自らの創作の秘密とともに、人間と物語をめぐる深い考察を語ってくれています。読み進んでいくと、小川さんの紡ぎ出す小説の もつ魅力の源泉がここにあると感じられるはずです。本書にちりばめられた珠玉の言葉、その一部をここに書き抜いてみました。 (編集部)
物語の役割
たとえば、非常に受け入れがたい困難な現実にぶつかったとき、人間はほとんど無意識のうちに自分の心の形に合うようにその現実をいろいろ変形させ、どうにかしてその現実を受け入れようとする。もうそこで一つの物語を作っているわけです。
あるいは現実を記憶していくときでも、ありのままに記憶するわけでは決してなく、やはり自分にとって嬉しいことはうんと膨らませて、悲しいことはうんと小さくしてというふうに、自分の記憶の形に似合うようなものに変えて、現実を物語にして自分のなかに積み重ねていく。そういう意味でいえば、誰でも生きている限りは物語を必要としており、物語に助けられながら、どうにか現実との折り合いをつけているのです。
数学者が、偉大な何者かが隠した世界の秘密、いろいろな数字のなかにこめられた、すでにある秘密を探そうとするのと同じように、作家も現実のなかにすでにあるけれども、言葉にされないために気づかれないでいる物語を見つけ出し、鉱石を掘り起こすようにスコップで一所懸命掘り出して、それに言葉を与えるのです。自分が考えついたわけではなく、実はすでにそこにあったのだ、というような謙虚な気持ちになったとき、本物の小説が書けるのではないかという気がしています。
物語が生まれる現場
私の場合は、映像が頭の中に浮かぶ時には、すでにそれが小説になるというサインなのです。小説は言葉で書かれるものですから、言葉が浮かんでくることが始まりではないかと、最初の頃は思っていたのですが、言葉が浮かんでくるわけではなく、言葉になる以前の段階のものが、まず浮かんでこなくては言葉にならないのです。言葉は常に後から遅れてやってくるという感触です。
ほんとうに悲しいときは言葉にできないぐらい悲しいといいます。ですから、小説の中で「悲しい」と書いてしまうと、ほんとうの悲しみは描ききれない。言葉が壁になって、その先に心をはばたかせることができなくなるのです。それはほんとうに悲しくないことなのです。人間が悲しいと思ったときに心の中がどうなっているのかということは、ほんとうは言葉では表現できないものです。けれども、それを物語という器を使って言葉で表現しようとして挑戦し続けているのが小説なのです。
私は、自分の小説の中に登場してくる人物たちは皆死者だなと感じています。すでに死んだ人々です。だから、小説を書いていると死んだ人と会話しているような気持ちになります。それは、恐ろしいとか気持ち悪いという感触ではなく、非常になつかしい感じです。自分はまだ死んでいないのに、なんだか自分もかつては死者だったかのような、時間の流れがそこで逆転するような、死者をなつかしいと思うような気持ちで書いています。
小説を書いているときに、ときどき自分は人類、人間たちのいちばん後方を歩いているなという感触を持つことがあります。人間が山登りをしているとすると、そのリーダーとなって先頭に立っている人がいて、作家という役割の人間はいちばん最後尾を歩いている。先を歩いている人たちが、人知れず落としていったもの、こぼれ落ちたもの、そんなものを拾い集めて、落とした本人さえ、そんなものを自分が持っていたと気づいていないような落とし物を拾い集めて、でもそれが確かにこの世に存在したんだという印を残すために小説の形にしている。そういう気がします。
私も若い時は、自分自身がいちばん重要な問題でした。自分が何者かということを知ろうとして小説を書いていました。二十年ほど書いてきて自分がそんなにこだわるほどの人間じゃないことがだんだんわかってきました。いったん自分から離れて、自分が想像も予想もしなかったような広い場所に立って世界を観察する。観察者になるという姿勢を持った時、生きている人も死んでいる人も、自分も他人も動物も草も花もみんな、あらゆるものが平等に見えてきた。自分自身に埋没しないという姿勢で、書いていこうと思うようになったのが、この一、二年ぐらいでしょうか。そのことに少しずつ気づきながら、小説を書くことが喜びでもあり、また苦しい作業でもあるということを学んでいる最中です。
物語と私
河合(隼雄)さんは、『ココロの止まり木』という本の中で、京都国立博物館の文化財保存修理所を見学した折、欠けた布を修復する際に補修用の布がもとの布より強いと、結果的にもとの布を傷めることになる。補修する布はもとの布より少し弱くなくてはいけない、という話を聞き、カウンセリングという自分の仕事に似ていると感じた、と書いておられます。補修する側が補修される側より強すぎると駄目なのです。
物語もまた人々の心に寄り添うものであるならば、強すぎてはいけないということになるでしょう。あなた、こんなことでは駄目ですよ。あなたが行くべき道はこっちですよ、と読者の手を無理矢理引っ張るような物語は、本当の物語のあるべき姿ではない。それでは読者をむしろ疲労させるだけです。物語の強固な輪郭に、読み手が合わせるのではなく、どんな人の心にも寄り添えるようなある種の曖昧さ、しなやかさが必要になると思います。到着地点を示さず、迷う読者と一緒に彷徨するような小説を、私も書きたいと願っています。
自分が死んだ後に、自分の書いた小説が誰かに読まれている場面を想像するのが、私の喜びです。そういう場面を想像していると、死ぬ怖さを忘れられます。
だから今日もまた私は、小説を書くのです。
小川洋子さんにフランスから勲章が授与されました
小川洋子さんにフランスから勲章が授与されました
小川洋子さんの作品は、世界10ヵ国以上で翻訳されています。特にフランスでは絶大な支持を得ていて、デビュー作から『博士の愛した数式』までのほとんど全部の 作品が翻訳されています。こうした評価の高さを裏付けるように、2007年1月に、フランス政府から勲章(フランス芸術文化勲章シュバリエ)が授与されました。これは、日本の作家としては、1997年の筒井康隆さんに次いで二人目の栄誉です。
1月18日、在日フランス大使館文化参事官アレクシイ・ラメックさんの私邸でカクテル・パーティのかたちで叙勲式が執り行われました。小川さんを囲んで、各社の担当編集者が列席しました。式は、ラメックさんから叙勲の説明とお祝いの言葉があり、勲章の授与式がありました。それ受けて、小川さんのお礼の言葉がありました。 最後に、小川作品をフランスに紹介することに尽力されてきた日本著作権輸出センター栗田明子さんの音頭で列席者が乾杯しました。
さすがに文化大国のフランスらしく、まったく格式張らない気さくな雰囲気でしたが、それでいて勲章にふさわしい風格も感じられる、素晴らしい叙勲式でした。

小川洋子
オガワ・ヨウコ1962年岡山市生まれ。早稲田大学第一文学部文芸科卒業。88年「揚羽蝶が壊れる時」で海燕新人文学賞を受賞。91年「妊娠カレンダー」で第104回芥川賞を受賞。その後も様々な作品を通じて、私たちを静謐な世界へと導いてくれている。著書に『冷めない紅茶』『ホテル・アイリス』『沈黙博物館』『アンネ・フランクの日記』『偶然の祝福』『まぶた』『博士の愛した数式』『ブラフマンの埋葬』『世にも美しい数学入門』(藤原正彦氏との共著)『ミーナの行進』(谷崎潤一郎賞受賞)などがある。