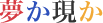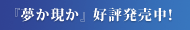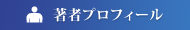吉村さんの死
七月下旬に患つた病気がどうにか恢復して、葉山の家で寛いでゐた日の夜、朝日新聞から電話があり、吉村昭さんの訃を知らされた。
のちに広く知られたやうに、吉村さんは自身の病状を外部に堅く秘してゐたから、その死はまつたく意外であつた。追悼文を書くやうにとの朝日の依頼を、私は引き受けた。吉村さんについて何を語るべきなのか、よく判らなかつたが、ともかく語りたい気持があつた。「吉村昭さんを悼む」と題した文章は、八月七日付の夕刊に載つた。
ぼくはこのごろ故老扱ひされるやうになつちやつてねえ、困つたものだ、と吉村昭さんが苦笑まじりに洩らしたのは、今からもう十数年も前になるだらうか。東京下町の空襲を語る会に招かれて出掛けて行つたら、会場に〈故老に聴く東京空襲〉と大書したポスターが貼つてあつたといふのである。故老なんて言つたら「七人の侍」に出てくる高堂国典みたいな人物を想像してしまひますね、と笑つて調子を合せながら、私は、年齢はともかく、若い世代に体験を伝へる語り部として、吉村さんほどふさはしい人はゐないだらう、と思つた。事実のほかに余計なものを加へず、感傷を歌ひ上げたりもしない作風を連想しての事であつた。
二十代の終り近くから、三十代前半にかけての吉村さんは、丹羽文雄門に学んで身に着けたリアリズムを基本としながら、独特の幻想味を帯びた短篇を書いてゐた。「貝殻」「少女架刑」「石の微笑」── その時分やうやく小説を書き始めてゐた私は、それ等を一歩先を行く人の作品として身を入れて読んだ覚えがある。
それだけに「戦艦武蔵」が発表されたときには、どうして吉村昭がこんな実録風のものを、と訝る気持が強かつた。同じやうに感じた人は他にもゐたであらう。その間の事情を明かした文章がある。「戦艦武蔵」は旧海軍の技術士官から提供された武蔵の建造日誌をもとに、当時を知る技術者にインタヴューを重ねて、エッセイの形で三菱系の会社のPR誌に連載したものだつたが、その内容に注目した雑誌「新潮」編集長の齋藤十一氏が、稿を改めて小説として書くやうに申し入れて来たのであつた。
……それまで私は、フィクションの小説を書くことにつとめ、芥川賞候補に推された作品もそれに類したものであった。戦艦「武蔵」は実在した構築物で、自分の筆はそのようなものを書ける質ではなく最も遠い世界に思えた。
私は、二日間考えに考えぬいた。そのうちに十八歳の夏に突然のように敗戦という形で終った戦争をいつかは書いてみたいと思っていたが、それを「武蔵」に託して書いてみるべきかも知れぬ、という気持も湧いてきた。恐らく無惨な失敗に終るにちがいないが、思いきって書いてみよう、と決意した。(「齋藤十一氏と私」新潮二〇〇一年三月号)
年を経てからの回想だが、今読んでも私は「無惨な失敗」も有り得る、と思ひ定めてなほ新しい分野へ踏み出さうとした三十九歳の作家の胸の震へが伝はつてくるやうな気がする。失敗すれば、作家生命を断たれる惧れすらある事に気が付かない吉村さんではなかつただらう。
さいはひ賭は成功して、作品領域はぐんと拡がり、「殉国」「零式戦闘機」「深海の使者」のやうな一連の戦史小説が書かれた。いづれも関係者から丹念に取材して仕上げた作品である。しかし自筆年譜の一九七三年の項には「多くの証言者の高齢化による死を痛感し、戦史小説の執筆を断つ」と記されてゐる。この決断の背後には、小説とは人間の生きる姿を描くものだといふ単純だが強固な信念があつた事は疑へない。そしてその後は、「長英逃亡」や「桜田門外ノ変」に代表される歴史小説の世界が拓けてくるのである。
吉村さんは進んで己れを語る人ではなかつたが、自作についての苦心談は、時に短い言葉で口にした。生麦事件で薩摩藩士奈良原喜左衛門が、どのやうな技を使つて馬上の英人を斬つたか調べるためにわざわざ鹿児島に赴いた話。或いは刑務所で長い間、列を組み、手を振つて歩くやう義務づけられてゐた無期懲役の囚人が、仮釈放となつてもその歩き方から脱け出せない事実を知つたのがきつかけで小説「仮釈放」の想が成つたといふ話。そんな時の吉村さんは実に楽しさうで、職人が自分の作つたものの出来栄えを無邪気に自慢するやうな趣きがあつた。
訃報を聞いたあと、私は手許にある吉村さんの小説のうち、いくつかの頁を披いてみた。生麦事件の年は「正月以来雨が少く、梅雨の季節になってようやく降雨がみられたが、六月に入ると旱天の日がつづいた」といふ一節に行き当ると、気象の調査に勇んで出掛けて行く吉村さんの、若いころ胸部成形手術を受けたためにやや左側に傾いだ後姿が眼に泛んだ。
「新潮」編集部からも、追悼文を求められた。私はそれにも応じて、吉村昭といふ人の生き方との関連で、かねて気になつてゐた小説について書いた。掲載は十月号、標題は「貫く意志」である。
吉村昭自筆年譜の一九五二年の項に「川端康成の短篇小説に自分の進むべき道を見出し、しきりに筆写する」と誌されてゐる。吉村さんは、尊敬する作家の作品を筆写するかたちで文学修業をした最後の世代の一人だらう。同じ年譜には、「六篇の短篇小説を書く。苦しくはあったが、これが生き甲斐だ、とも思った」(七四年)、「文芸雑誌に七篇の短篇を書く。十日間ほど考えていると、自然に素材が湧いてくる」(八〇年)といつた記述が六ケ所にも見られる。実録小説、歴史小説の作家として盛名を馳せてのちも、自分の本領は純文学にある、と思ひ定めてゐた様子が窺へる。
私淑しただけに、吉村さんの小説には、川端康成に通じる非情さがある、と私は思ふ。ただし川端流の抒情とは縁がないから、吉村さんの非情性はより直截に表現される。
八一年の夏、二歳年下の弟が肺癌を病んで死んだ。その苦しみにのたうち廻る一年間の闘病生活を、たぢろがずに見据ゑた長篇が「冷い夏、熱い夏」である。この小説の真の主人公は、死んで行く弟ではない。作中に〈私〉として現はれる吉村さん自身である。
弟の発病を知つた〈私〉は、医学小説を書く過程で培つた死生観を拠りどころに、弟に癌である事実を絶対に知らせない決意をする。その意志を貫き通すためには、周囲の人間を有無を言はせず従はせなくてはならない。〈私〉は弟の妻に向つて言ふ。──「さとられないようにするのは、並大抵じゃないぞ。あいつの前で涙ぐんだりするな。溜息ももらすな」。
治療に手立てを尽しても痛みが増すばかりの事態に、弟は当然、癌ではないかとの疑ひに苛まれる。「ぼくは肺癌なんでしょう。一年以内に死ぬんですね」と、「異様に光る眼」で医師に迫つたり、「転移しているんだ」と呟いたりする。それでも〈私〉の決心は揺らがない。一人きりの書斎で、むかし大病を患つた自分を辛抱強く看護して呉れた弟の面影を思ひ出して慟哭し、時にはこんなやり方は身勝手ではないかと自省に捉はれながらも、その都度、「気力を失ってはならない」と己れを奮ひ立たせる。
弟への〈私〉の愛情の深さは疑ひやうがないが、その愛情に溺れるわけではない。看護に万全を期す半面、弟の死後についても冷静な思案をめぐらす。出版社の社員の智慧を借りて、葬儀の計画を立て、葬儀社の手配も済ませるのである。作家としての職業的義務もおろそかにはしない。弟が危篤に陥つたちやうどその日に、前から予定されてゐた出版社主催の講演会があつた。〈私〉はすがるやうな眼をする弟をあとに、講演会場に赴く。「弟の傍についていてやりたくとも、私には私の世界がある」。小説の執筆動機についての講演を予定通り進める間、〈私〉は「弟を思いうかべることはなかった。想い出すまいとしていたのではなく、話すことに専念していた」。
このやうな行動をとる〈私〉に向つて、〈私〉の妻が、「あなたは恐しい人だと思う」と言ふ場面がある。その言葉に対する〈私〉の内心の反応は書かれてゐない。ごく短い場面だが、私が記憶に留めてゐるのは、〈私〉の妻と同じ印象を抱いたからだらう。恐しい人。なにゆゑのこれほどの強さなのか。若年の頃の大病で一度は死に瀕し、長く苦しい療養生活に耐へなければならなかつた体験が、吉村さんを鍛へた、とは一応言ひ得るだらう。しかし、むろんそれだけではないだらう。生来柔弱な私は、剛直な人の内面にまで立ち入つて想像する事が出来ない。小説の一節に「生を享けた人間の義務として、肉体の許すかぎりあくまでも生きる努力を放棄すべきではない、と思う」と書かれてゐるが、吉村さんがこの作品を書いた年齢を遥かに越えてしまつた現在でも、それだけの覚悟は到底持てない。
私の知る吉村さんは、自分は〈小心翼々たる小人物〉だとよく口にした。その一例として原稿の仕上りが早い、といふより早過ぎて、新聞小説などは連載開始前に全部書き上げてしまふ事が挙げられた。文士の締切苦については昔から話の種が尽きないが、私たち同世代の小説家が集まつた席でもしばしば話題となつた。そんなとき吉村さんは、原稿を早く渡し過ぎると小物扱ひされるから、書き上げてもしばらく手許に置いて、締切ぎりぎりに渡さうと思ふんだが、それが出来ない、小心者の所以でね、といふやうな調子で面白可笑しく喋つて、笑ひを誘つた。特に締切を守れないので有名な田久保英夫さんとの応酬は、互ひに自分を滑稽化してみせる漫才の趣きがあつて、大いに座を沸かせた。しかし私は、その過剰なまでの律義さが、一たん定めた事、定められた事は、何があつても守らなければならぬといふ頑固な意志の現はれなのには気付かなかつた。
九八年以来、私は、吉村さんの推挽によつて、太宰治賞の銓衡委員を務めてゐる。銓衡に当つて、吉村さんは厳しかつた。或る年の候補作に主人公が人の糞便を食ふ場面があつた。その一行だけで、吉村さんはその作品を断乎として拒否した。ぼくは認めない、と言つたきり口を噤んでしまつた風貌が、今も眼に遺る。
死後三週間余りを経た八月二十四日、吉村さんゆかりの日暮里のホテルで、お別れの会が開かれた。その席で最後の挨拶に立つた津村節子さんは、病に苦しんだ吉村さんが、自ら点滴のカテーテルポートを引き抜いて死んだ事実を明かし、吉村は 〝自決〟 したのだと言はれた。
この発言は反響を呼んだ。中にはしたり気に死者の内心を推測してみせる向きもあつたやうだが、私はそんな真似をしようとは思はない。ただ自決といふ言葉を噛みしめるばかりである。
(高井有一『夢か現か』より)
回り灯籠トップへ

高井 有一
タカイ ユウイチ
(著者近影:坂本真典)