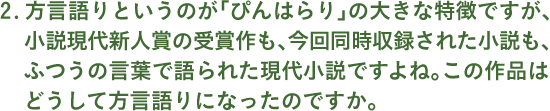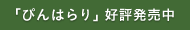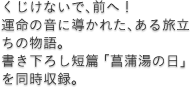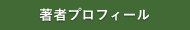「峠の春は」あらため「ぴんはらり」。
主人公の圧倒的な存在感、方言語りの力強さ、そして読む人の心を温かくする明るさ。
高い評価を得た作品にさらに手を入れ完成度を高めました。
書き下ろし短篇「菖蒲湯の日」も同時収録。
初の単行本を上梓し、いよいよ作家の道を歩み始めた栗林佐知さんに、メールインタビューしました。
もともと、字が書けるようになる前から、あやしげな記号で"お話"を書いていて、子どもの頃は「物語を書く以外に、自分の仕事はないだろうな」と思っていたのですが、大人になるにつれ、「ちゃんと普通の人として一般社会で役に立たなくてはダメだ」と、コチコチに考えるようになり、ホントに変ですが「いい大人が昼間から小説を書くなんて『道楽』はいかん!」と決めつけていました。
この「ぴんはらり」のおきみ同様、私は長いこと、「伊達ッコキ」ではダメだ、と思っていたわけです。
おきみは、「12か13か14か5か6か7才」で、自分のキャラをわきまえますが、私は30代半ばで、ようやく「小説を書く」ことを、自分に許してやることができました。
この「許可」の直接のきっかけは、仕事で偶然出会った、ある精神科医の先生の考え方にふれ、この「コチコチ」の思考回路をほぐしてもらえたことが大きいです。
「ぴんはらり」を書こうと思ったのは、昔話・落語などで有名な「松山鏡」の話が気になっていたからです。私はこれを、周囲から疎外され、肯定してくれる人が一人もいなくとも、「誰か(特に母親)に支えられている」と信じ込むことで、たくましく生きられた少女の物語だと思い、そう書こうと思いました。
やっぱり、戦国〜江戸初期の「越後の松山村」がどんな所で、どんな人がどんな暮らしをしていたか、「こんな感じだったろう」という様子をつかまないと、世界が立ち上がらないと思いました。
勉強と想像で物語の舞台をこねあげ、そこで暮らす少女がどんなふうにしゃべるか考えたら、自然にあのようなかたちになりました。
「おきみ」がちゃんといて、それにアプローチしていった、という感じです。
新潟の民話の本をたくさん読み、筆写したり音読したりして"それらしい"方言をつかむことから近づいてゆきました。
新潟県各地の言葉が混ざっていて、正確な旧松之山町の方言ではないと思います。単行本化の時、できるだけ頸城地方の言葉に近づけるよう試みましたが、いずれにしろ、厳密には創作した世界、言葉です。
宇野千代さんの『おはん』を読んで、「こういうのやってみたい」と思ったことも影響していると思います。
小説が好きな方が読んでくださって、「オモシロイ!」と思ってくださったら、なによりです。
さらに、好きになってくれて「自分は、この主人公(特に併録の「菖蒲湯の日」の)ほどバカじゃないけど、なんだか元気が出るなあ」と思ってくれたら、これ以上のことはありません
。
ただ、私の主人公たちは、人さまがらくらく飛び越せる水たまりでアップアップしてしまったり、妙な工夫をして毎日やっと生きてるような「へんてこなやつ」が多いせいか、今までの発表作品(『小説現代』02年5月号、03年3月号掲載)や草稿などを読んでくれた方のなかには、驚くほどの「熱意」をこめて、嫌悪感を表明なさる方も多いのです。
その反面、少数ですが、「これ、私のために書いてくれたのかと思ったよ!」「こういう作品が出てくるのを待ってた」といってくださる人もいます。
意外にも、「この人には共感してもらえるかな」と思った人から大反発をもらったり、主人公とは似てもにつかない美人キャリアウーマンから「おもしろい」と言ってもらえたりします。
どんな方がどんな感想を持ってくださるか、とても楽しみです。ですので、とにかく、たくさんの方に読んでいただけたらと思います。

栗林 佐知
クリバヤシ サチ