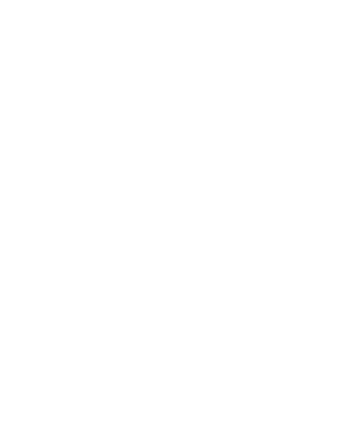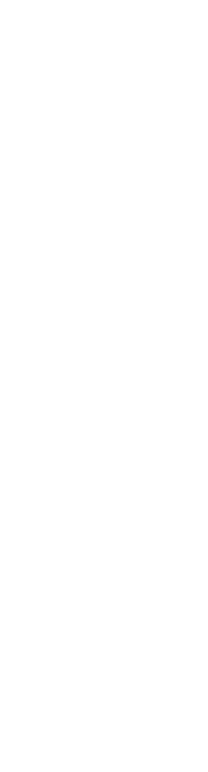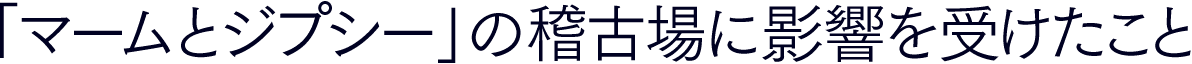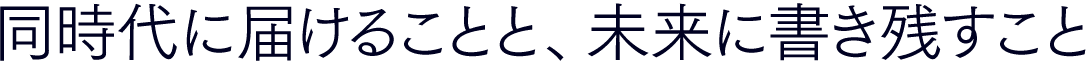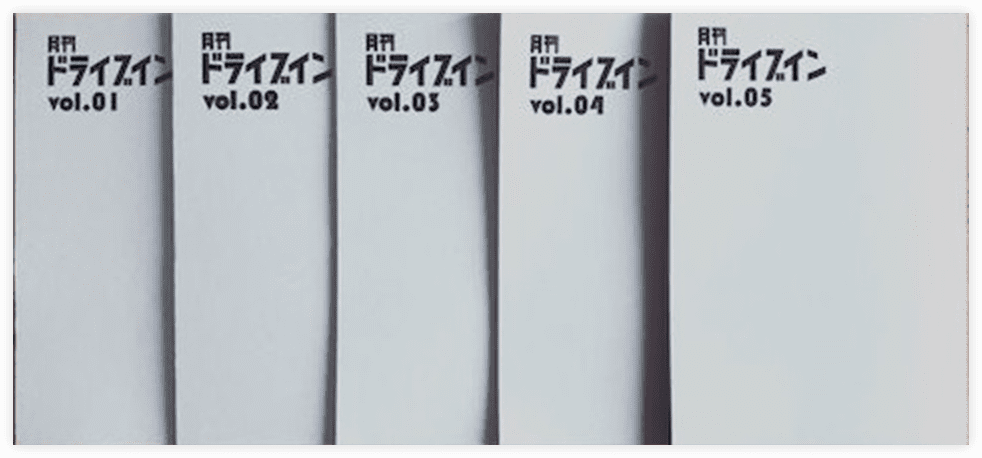- 橋本
- 今回、「本のあるところajiro」でトークイベントを開催することになったきっかけは、お店の方から「いつか弊店で刊行記念のイベントをしていただけないか」とメールをいただいたことにあるんです。そのメールをいただいたその日のうちに「もし福岡でトークをするのであれば、見汐麻衣さんと」と返信して、今日の会が催されることになりました。
- 見汐
- よろしくお願いします。結構飲む人なんですね?
- 橋本
- 結構飲みます。人前で話すのは緊張するからというわけでもないんですけど、ここまでのトークは毎回お酒を飲みながら話していて、今日も飲みながらトークさせていただきます。でも、僕はまだ今日3杯目ですけど、見汐さんはもう結構飲んできたんですよね?
- 見汐
- はい。でも、ちゃんとおしゃべりできると思います。
- 橋本
- 僕が見汐さんとトークしたいと思ったことには、いくつか理由があるんです。この『ドライブイン探訪』は、文字通りドライブインを取材した本なんですけど、僕が最初にドライブインを巡り始めたのは2011年だったんですね。
- 見汐
- それを聞いて、「そんなに前からやってらっしゃったのね」と、びっくりしました。
- 橋本
- 軽バンを持っている友人から「1ヶ月くらい使わないから、取材したいテーマがあれば使っていいよ」と言われて、「じゃあドライブインを巡ってみよう」と旅に出たのが2011年の夏の終わりなんですけど、数枚だけCDアルバムを積み込んで、そのうちの1枚が見汐さんが組んでいた「埋火(うずみび)」というバンドの『わたしのふね』というアルバムで。埋火は福岡で結成されたバンドで、見汐さんも九州にゆかりがあるということもあって、「ぜひ見汐さんと」とお願いしたんです。今日はトークが始まる30分前に見汐さんにお会いしたんですけど、そのときから緊張していて。ここまで『ドライブイン探訪』の刊行記念トークイベントをいくつか開催してきましたけど、ゲストにお呼びしたのは何度も話したことがある方ばかりだったんです。でも、見汐さんとはほぼ話したことがなくて。
- 見汐
- ライブにきてくださる姿をお見かけすることは多々あるんですけど、橋本さんはだいたい飲んでらっしゃるから、話したことはないんです。
- 橋本
- 見汐さんは2017年3月から、高円寺の「円盤」というお店で「うたう見汐麻衣」という企画を隔月で開催されてますよね。『ドライブイン探訪』は『月刊ドライブイン』というリトルプレスが元になっているんですけど、この創刊号が刷り上がったのも2017年3月だったんです。僕はほぼ毎回「うたう見汐麻衣」を聴きに行って、見汐さんの歌を聴きながら考えていたことがあって、その話をぽつぽつできたらなと思っています。
- 見汐
- 私で大丈夫かわからないですけど、よろしくお願いします。
- 橋本
- ドライブインを取材するなかで感じたことはいくつもあるんですけど、その一つに、「歌っていうものは、ドライブインって場所と相性がいいんだな」ということがあって。『ドライブイン探訪』で取材したお店は22軒あるんですけど、そのうち2軒がカラオケを楽しめるお店なんですよ。
- 見汐
- 読みました。最初に『月刊ドライブイン』として出版されていたときに、橋本さんから1冊いただいて、それが面白かったので、他の号も中野にある「タコシェ」というお店に買いに行きました。それがこうして1冊になって読むと改めて面白かったんですけど、そこに歌のことがあって。
- 橋本
- そのうちの1軒は現役のドライブインではなくて、ドライブインをされていた方の息子さんが店を引き継いで、現在はカラオケ喫茶として経営されているお店なんですけど、もう1軒はドライブインとして営業を続けながらも、夕方5時になるとカラオケが歌える店になるんです。そのお店を取材していたときに、歌とドライブインは重なるものがあるなと思ったんですよね。それと同時に、「これまで自分は、『歌とは何か?』ということをあまり考えずに生きてきたな」と思って。そもそも僕はあまり音楽になじみのない少年時代を過ごしていたんですけど、見汐さんは小さい頃から歌に縁があったんですよね?
- 見汐
- そうですね、ありました。私は佐賀県の唐津市ってところで生まれて、小さいときに父親の実家に預けられて育ったんです。そのとき、おじいちゃんおばあちゃんに「幼稚園の皆が持っているオモチャを買って欲しい」と言えなかったんですね。どうしたらいいんだろうと思っていたら、「自分で稼ぎなさい」とおじいちゃんに言われて。そう言われても、「うん?」と思うじゃないですか。まだ3歳とかだったので、「稼ぐって何?」ということがまず一つあって、おばあちゃんに稼ぐってどういうことかと尋ねたら、「老人会で旅行に行くんだけど、そこで歌を歌えばおひねりというものがもらえるから、それでオモチャを買えばいいんじゃないか」と言われたんです。うちのおばあちゃん裁縫の先生をやっていたから、上等な着物をこしらえてくれて、それを着て歌ったんです。そうしたらお金が本当に飛んでくるんです。それでオモチャを買ったときに、「歌えばお金になるんだ」っていうことを刷り込まれたんですよね。今もそれを生業としているんですけど、ミュージシャンになりたいというより、そういう環境の中で歌えばお金になるんだっていうのが小さいときからあって、それをそのまま続けている感じなんですよね。
- 橋本
- そういう場所で歌うとなると、自分はこの歌が好きだから歌うってことよりも、この歌を歌えばおひねりがたくさん飛んでくるなってことが基準になってきますよね。
- 見汐
- 三十何年前のおじいちゃんおばあちゃんは戦争を経験している人たちだから、日本が復興していく中で流行った「戦後歌謡」と呼ばれる歌を歌うと皆さん喜ぶし、泣いたり笑ったりされてたんですよね。それは自分が好きな歌かと問われると、そうではないわけですよ。でも、それを歌うと皆が喜んで、ちり紙に巻かれたお金がたくさん飛んでくる。そこで歌いながら、ただ単純に楽しいなと思ってました。
- 橋本
- その戦後歌謡は、おじいちゃんおばあちゃんたちの記憶が詰まった歌だったということですよね。その歌を耳にすることで過去を思い出して、懐かしくなったり感極まったりして、それでおひねりが飛んでくるわけですよね。もちろん3歳の時点ではそんなふうに言葉で考えないにしても、そういう構造になっているんだということは当時から意識してたんですか?
- 見汐
- うちのおばあちゃんは戦争が終わるまで満州にいて、小さい頃から「満州」という言葉は聞いていたんです。満州から引き揚げてくるときに、大変な思いをした話を聞かされたり、同じような方たちもきっとたくさんいて、たとえば並木路子さんの「リンゴの唄」を歌うと、きっとその人たちの中で思い出す何かがたくさんあって、それで泣いたり笑ったりするんだろうなということは幼心に感じていたんですよね。その思い出が苦い思い出なのか楽しい思い出なのかはわからなかったけど、きっと何かあるんだろうなということは、皆さんの表情を見て思ったりしてました。
- 橋本
- それはつまり、自分は知らない誰かの記憶に触れるってことでもありますよね。それって結構すごいことだと思うんです。幼い頃は無邪気にやっていたとして、成長するにつれて「自分がやっていたのはそういうことだったのか」と気づいて愕然とする瞬間が訪れたりはしなかったんですか?
- 見汐
- 愕然と――。ちょっと話がズレますが、私の母親は飲み屋を経営していたんですけど、母親と一緒にいたいから、週末になると夜は飲み屋で過ごしていたんですね。それはちょうどバブルがはじける前の時期で、ものすごく田舎の店だったけど、繁盛していたんです。そこで歌うと、老人会で歌っていたときみたいにお金がもらえるんですね。お客さんの中にカタギじゃない人がひとりいて、その人は母のことが好きだったっていうのもあるとは思うんですけど、そのお客さんは私の歌を聴くと「明日から頑張ろうってほんとに思うんだ」と言ってくれていて。それを聞いたときに、大人も色々あるんだな、大変なんだなと思ったのはおぼえています。
- 橋本
- なんでその時代の話をしつこく聞いているのかっていうのは、理由があるんです。『ドライブイン探訪』で取材したお店は、少なくとも3回は訪れているんですね。千葉の南房総市に「なぎさドライブイン」というお店があって、そこも最初は普通にお客さんとして訪れて、2回目はちょっと長居をしてお店の方と会話をして、「実はドライブインのことを取材してまして、よかったら今度お話を聞かせてもらえませんか」とお願いをして、3度目に訪問したときに取材をしたんです。そうやって話を聞かせてもらった半年後、バラエティ番組から出演依頼があって、どこか行きたいお店はありますかと言われたので、「なぎさドライブイン」を再訪することにして。ロケの日、お父さんは常連さんを集めてくださっていて、遅れて到着した頃にはもう宴会が始まっていたんですね。到着するなり、お父さんはカメラに向かって「俺と橋本さんは一生の付き合いだから。な、橋本さん!」とおっしゃったんです。そう言われて嬉しくなるのと同時に、びっくりして。だって、3回行っただけなんですよ。「取材したドライブインを3回ずつ訪れている」と言うと、「そんなに丁寧に取材されてんですね」なんて言ってもらえることもありますけど、たった3回なんですよ。それで「一生の付き合いだからな!」とまで言ってもらえるって、一体どういうことなんだろうと。
- 見汐
- 何だろう。この本を読んでいて思ったのは、ドライブインをされてる方たちは橋本さんのように訪れる立場でなく、ひとつの場所に留まって迎え入れる立場じゃないですか。同じ場所で日々の営みというものを粛々と営んでいる側からすると、何度も足を運んでくれる人って憶えるし、興味が湧くと思うんです。母の店で過ごしていたときも、何度も来てくれる人がいたら、「このお客さん何してる人だろう?」と思ってましたもん。
- 橋本
- 『ドライブイン探訪』は、お店の歴史を聞き書きした本でもあるんですけど、お店を営んでこられた方の半生を聞き書きした本でもあるんです。「どういうきっかけで結婚されたんですか?」とか、そういう話も聞いているから、「一生の付き合いだからな!」となるのかもなとは思っていて。
- 見汐
- 身内とも話さないような、自分の歴史を語るんですもんね。著名な人であればよくあることかもしれないですけど。毎日粛々と営みを繰り返す場所に突然取材にきてくれるって、私だったら驚きと、ありがたいなという気持ちも湧くと思いますけどね。
- 橋本
- 今日はずっと、その「なぎさドライブイン」のことを考えていたんです。というのも、今度またバラエティ番組に出演することになって、その番組は千葉出身の方がMCだということもあって、そこでも「なぎさドライブインを紹介するのはどうですか?」と推薦していたんですよね。今日の夕方、スタッフの方からメールが届いていて、「確認のために電話をしてみたら、もう閉店されたみたいです」と書かれていて。『ドライブイン探訪』を出版する前にすべてのお店に電話をかけて、その段階ではまだ営業を続けていると知っていたから、そんなはずないと思ってすぐに電話をかけたんです。そうするとすぐにお店のお母さんが出てくれて、「そうなのよ、もう閉店しちゃったのよ」とおっしゃって。理由を尋ねると、「2月に入ってすぐ、主人が急になくなって、ひとりじゃ続けていくのは無理だから、もう閉めることにしたんです」と。1年前に「一生の付き合いだからな!」と言われたのが最後になって、そのあと「なぎさドライブイン」行けてなかったんですよ。取材したドライブインのうち、ほとんどのお店には出版社から献本してもらっていたんですけど、「なぎさドライブイン」と「ドライブイン扶桑」は比較的近くにあるのと、「一生の付き合いだからな!」と言ってもらったお店には直接渡しに行かなければと思って、本を送ってなかったんです。でも、渡せないままになってしまったんだなっていうことを、今日はずっと考えてました。
- 見汐
- 会いたい人にはね、すぐに会いに行ったほうがいいんだよ。場所もそうだけど、人も永遠じゃないんだもんね。
- 橋本
- ドライブインで「一生の付き合いだからな!」と言われたことは、結構僕の中に残り続けていて、そう言われたからには「取材が終わったからもう行きません」では済ませられないなと思うんですよね。結局、行けないままになった僕が言っても、全然説得力はありませんけど、それでもそう思ったんです。人の心に触れてしまうことって、それぐらいの大きなことだな、と。さっき見汐さんに「どこかのタイミングで愕然としなかったんですか?」と聞いていたのも、それがあるからなんです。歌っていうものには、そうやって人の心に触れてしまう力がすごく詰まっているな、と。
- 見汐
- 自分がライブを観に行ったりしていると、音楽の場合は突然懐にグイッと入ってくる瞬間があるなと思うんですが。映画や本というのは、自分から観ようとしたり読もうとしたりしなきゃいけないけど、音楽は瞬間的に深くまっすぐ感性に刺さることがあるから、すごいものだなと思うんです。話が少し戻りますけど、「リンゴの唄」を聴いて皆が泣くっていうのは、私の歌を聴いて泣いてるんじゃなくて、その歌がきっかけで思い出すことがあるんだろうなと思います。
- 橋本
- 歌にはそういう強さがありますよね。一曲っていう短い単位に詰まっているものもありますし、もっと短く、あるワンフレーズを偶然耳にしただけで思い出されてしまうものがある。歌にはそういう持ち運びやすさがありますよね。それに比べると、本はやっぱり重くて、まずは「これを読んでみよう」と手にとってもらう必要があって、冒頭から順に文字を目で追って読んでもらう必要があって、何か一つの感慨を届けるまでに受け手に労力を払ってもらう必要があって。でも、歌は能動的に聴こうとしなくても、偶然ラジオから流れてきたり、街角で流れてきたりすることで、「ああ、この曲」って思う瞬間もあるじゃないですか。あの持ち運びやすさと、その一瞬で何かに触れることができる強さがあるなと思うんです。
- 見汐
- それは自分がやっているときにも思いますし、人様のライブを聴いているときにも思います。どのタイミングでその曲に出会ったかによって、その曲を聴いたときに甦ってくるものは各々違うんだけど、音楽にはそういうすごさがあると思います。
- 橋本
- 音楽って、もちろんすごく長い曲もありますけど、4分か5分くらいのものがすごく多いですよね。その、5分なら5分にすべてを詰めるってこともすごいなと思うんです。特に歌謡曲であれば、誰かの人生や感慨が数分間に凝縮して詰め込まれていて、その詰め込まれ方がすごいな、と。それはドライブイン巡りをしていても感じるもので、ドライブインは60年代に創業されたお店も多いんですけど、そうすると半世紀近く続いてるわけですよね。そこで「この半世紀って、どんな時間でしたか?」と質問すると、皆さん「あっという間でした」とおっしゃることが多くて。それは僕の質問が誘導してしまっているところもあるのかもしれないですけど、僕からすると、50年って時間は途方もないものに感じられるんですよ。実際、そこには途方もない時間があって、途方もないほどいろんな出来事があったと思うんです。でも、それは括弧に入れて、「あっという間でした」と答えてらっしゃるんだと思うんですよね。その言葉の裏には、何かこう、「人生ってそういうものでしょう」という達観がある気がして。もちろんいろんな出来事があったけれど、それを語りだせばきりがないし、人生っていうのはそういうものだ、と。その達観と、数分間に何かを凝縮して歌にするってことはとても近いことであるような気がするんです。
- 見汐
- 何でしょうね。たとえば自分の人生について取材されて、「今まで何十年生きてきて、どうでした?」と聞かれたら、「あっという間でした」ってなりませんか? 日々いろんなことがあるけど、それは自分が望む望まないにかかわらず、「おぎゃあ」と産まれてきて、産まれてきたからには生きていかなきゃいけなくて、そのなかでいろんなことがあるでしょう? そうしたら、私はもう、「あっという間でした」としか言えないと思ってしまう。
- 橋本
- そのことを考えると、自分はまだ子供なのかもしれないなといつも思うんですよね。「あっという間でした」と言うふんぎりがつかなくて、過去に撮った写真とかを見返しながら、「このときはこうでね」と事細かく言ってしまう気がするんです。でも、見汐さんのライブを観るたびに圧倒されていたのもそこで、「この人はきっと、『あっという間でした』と答えるだろうな」と思っていたんです。ほとんど話したこともないからパーソナリティは全然知らないですし、ライブで歌っている姿しか知らないから勝手な想像に過ぎないですけど、そう答えるだろうなとずっと思っていたんです。見汐さんは、ご自身で作られた歌だけじゃなくて、誰かの歌をライブで歌うことも多々ありますよね。たとえば江利チエミさんの「わたしの人生」という歌も時々歌われてますけど、あの歌詞にもすごくあっけらかんとしたものを感じるんです。そんなふうにあっけらかんとした態度に至れるのは一体どういうことだろうと、ドライブインを巡っているときにも、見汐さんの歌を聴いているときにも感じていたんですよね。
- 見汐
- 基本的に「死ぬまで生きる」ってことしか考えてないからですかね。この世に生を受けること自体自分の意思とはまったく関係のないことじゃないですか。あるときから自意識というものが芽生えて、逡巡しながら暮らしていろんなことがありますけど、過ぎてしまえばないものなんですよ。いくつで死ぬかはわからないけれど、最後は皆死ぬじゃないですか。等しく死ぬんです。そのとき自分が何を思い出すだろうって、酒場で友達と話したことがあるんですね。私はきっと、「大きい風呂敷で経た時間すべてを包んでいるけれど、風呂敷を広げて見てもその中には何もない」ってことしか思わないと思うんですよね。そう話したら、「いや、何かあるでしょ」と言われたんですけど、でもやっぱり、等しく何もないと思うんです。もちろん実際にはいろんな出来事があるし、自分がこの世からいなくなっても自分の作った曲は残るかもしれないけど、生きているうちに見聞きするすべてはその瞬間瞬間で完結するものだと思うので。「何かがあった」ということを包む風呂敷が残るだけで、その風呂敷を広げたら何もないと思う。
- 橋本
- そこで不思議なことが一つあるんですよね。見汐さんは「寿司日記」というブログや、「寿司日乗」という日記を書かれてますよね。そこでは日々の出来事や、日々感じたことを書き綴られてますよね。これは別に、「どういうことだ」と批判してるわけじゃないんですけど、「風呂敷を開くとからっぽ」だと思っているとすれば、何も記録しないってことになりそうな気がするんですよね。
- 見汐
- そうですね。矛盾してるんですが、風呂敷を開いてしまうとからっぽなんだけど、瞬間瞬間で完結するものの中に、強烈に残っている場面があって。友達の笑顔だったり、誰かの後ろ姿だったり、なんでもないことなんですが、人生の中で要所要所にあって、そういうものは記しておきたいと思うんですよね。それは自分で読み返すためにつけはじめたもので、何もないんだけれども、何かがあったことは記しておきたくて。それが未来に対して何かになるわけではないから、結局のところ無駄なんですけど、ただ印象に残っている場面をかいつまんでスクラップする感覚というか、それをやっているんだと思います。
- 橋本
- 僕がドライブインを取材してることも、「そこに何かがあった」ということを書き残しておきたいと思って始めたことなんです。そこで記録しているのは僕自身の人生ではないから、「記録したところで無駄なんですけどね」とは言えないですけど、「それを記録してどうするの?」と言われると答えに困るところはあって。『月刊ドライブイン』を作っていたときは、「このお店に話を聞かせてもらいたい」と思ったら、まずは普通にお客さんとして食事をして、何時間か居座って飲み食いし続けて、少し打ち解けたところで「実はこういう雑誌を作ってまして……」と切り出していたんですね。そこで取材を引き受けてくださったお店があったおかげで『ドライブイン探訪』という本を出版できたわけですけど、取材という言葉を出した瞬間に、それまでにこやかに対応してくださっていたのに表情が曇って、「さっさと帰ってくれ」と言われたこともあるんです。そこまで拒絶されなくとも、「このままひっそり消えていくつもりですから、取材は結構です」と言われることも多かったんですね。そう言われたときに改めて感じたのは、取材するって、すごく余計なお世話でもあるなということで。
- 見汐
- 断る側からするとほんとに余計なことなんだろうね。普通に暮らしているだけだもんね。
- 橋本
- そうやって考えると、一体何をやってるんだろうなと思うこともあるんです。そういうことを考えるたびに思い返すのが、川端康成の「雪国」に登場する一節で。主人公の島村が、駒子という女性が、「十五六の頃から、読んだ小説を一々書き留めておき、そのための雑記帳がもう十冊にもなった」という話を知る場面が出てくるんですよね。その雑記帳に書き留められているのは小説の感想ではなくて、「題と作者と、それから出て来る人物の名前と、その人達の関係と、それくらいのもの」しか書いていないと駒子が言うと、「そんなものを書き止めといたって、しょうがないじゃないか」「徒労だね」と島村が言うんです。僕が何かを書き記していることも、ある視点から見れば、まったくの徒労でしかないかもしれないなと思うんです。そうなってくると、「自分は一体何をやっているんだろう?」と。
- 見汐
- もう、その連続ですよ。この何十年、「何をやっているんだろう?」の繰り返しです。20代のときは「真面目にやることやって年を経れば何者かになれるんだ」と思ってましたけど、そんなことはないんだなと今は思うし。何者にもなれずに死んでいくんだなと。
- 橋本
- お店を経営されている方にも、「何者かになってやろう」という思いで経営されている方もいらっしゃると思うんですね。というか、そういうものだと思っていたんです。就職してサラリーマンになるのではなくて、自分でお店を創業されるからには、そこにきっかけや動機や目標があって始めているのだろう、と。でも、ドライブインで話を伺っていると、「あの時代はドライブインが流行ってたんだよ」とか、「特に理由はないけど、この道路にクルマが走るようになってきたから、ドライブインでもやってみるかって始めたんだよ」とかおっしゃる方が多くて、すごく粛々と営んでこられた感じがしたんですよね。
- 見汐
- 私はお酒を飲むのも、酒場という場所も好きでよく行くんですけど、上野に「多古久」という100年以上やっているおでん屋さんがあるんですね。そこで「100年ってすごいですね」と伝えたら、「たまたま100年続いてるだけだよ」と言われたことがあって。その時、ふと思ったのは、当たり前のように普通に過ごしている一日って、無名なものなんだなと。これは『ドライブイン探訪』を読んでも思ったことですけど、その無名な時間というものは、めちゃくちゃ尊いなと思ったんです。わざわざ遠いところまで、何遍も足を運んで取材して――「変な人だねえ」って言われてたと思いますよ。
- 橋本
- そうですね。それは言われていたと思います。
- 見汐
- 身内でもなく、常連さんでもなく、よその人が興味を持ってきてくれる。それは一つの新しい目線じゃないですか。自分の日々の中にはない目線を持つ人が、違う角度から自分の生活を可視化されたものに変えてくれる。読んでいて泣いてしまう箇所もありました。
- 橋本
- 『ドライブイン探訪』で取り上げた22軒というのは、帯にあるように「戦後のあゆみ」を描くために選んだものではあるんです。でも、それだけではなくて、普通にお店を営んでいる普通の時間をどうにか言葉にできないかってことはずっと考えていて。僕もお酒を飲むのは好きで、よく行く酒場がいくつかあるんですけど、そのうちの1軒は見汐さんもよくいらしているお店で。それは新宿の思い出横丁にあるお店なんですけど、たとえば思い出横丁という場所を取材して雑誌の記事にしようとすると、「懐かしの」だとか「レトロ」だとか「人情」だとか、どうしてもゴテゴテとした形容詞をあれこれつけてしまうことになりがちだと思うんですよね。でも、そうやって言葉で装飾することは、自分がその場所を好ましく思っている理由とは真逆のことであるように思うんです。でも、ただ普通のことを普通に書き綴るのでは誰かに届きづらい部分もあるので、どうすれば言葉にして届けることができるのかってことは、ドライブインを取材しながらずっと考えてましたね。
- 橋本
- 見汐さんは歌を歌うこと、曲を作ることを生業とされてますよね。その一方で、ブログをはじめとして、文章を書かれることもありますよね。自分が普段感じていることと、それを言葉にすることのあいだにはどんな段階があるんですか?
- 見汐
- 文章を書くという行為と、歌詞を書くという行為は自分の中ではまったく違うもので。以前山本精一さん(1986年から2001年まで「BOREDOMS」に参加し、プレイヤー/ソングライター/コンポーザー/プロデューサーとしてワールドワイドに活動を展開)と雑誌で対談させていただいたときに言い得て妙だなと思ったことがあって。山本さんは「歌詞を書くのは落ち穂拾いと一緒だ」とおっしゃっていて。なるほどなぁと思ったんですが。歌詞は「よし、書くぞ!」というよりも、たくさん転がっているものの中から自分が何かを引き当ててて、それを羅列していく作業で、文章を書くという行為はもう少し自分の生活に密着していて、一日の中にハイライトってあると思うんです。何でもないような一日の中にも、何かあると思うんですよね。自分の中で強く印象に残ったハイライトの中に何か大切な、本質的なものがある気がして。文章を書くのは、それを可視化する作業なんだと思います。本質的なものってそういうなんでもないことの中にこそこぼれ落ちるぐらいたくさんあるような気がしていて、自分の場合は一度文章にしてみないとわからないことが多々あるので、続けているだけなんですけど。
- 橋本
- その、歌詞にすることと文章にすることの違いについてもう少し伺いたくて。たとえば、見汐さんが作った「歌女夜曲」という曲がありますよね。この曲は、さきほど話に出たおばあさまから見汐さんが伺っていた話があって、その話をもとに作られた曲ですよね。誰かから聞いた話や、自分の目の前にある話があって、それを歌という形にするのはどういうことなんでしょう?
- 見汐
- なんでしょうね。歌詞に関しては、フィクションを連ねることで見えてくる真実が――事実ではなく真実というものがあると思っていて。事実というのは、日々の連続ですよね。今ここにいることも事実だし、今日こうやって話したことも事実ですけど、それと等しいものではないのが真実だと思うんです。曲を聴くときって、それがフィクションかノンフィクションかなんて考えずに聴きますよね。映画やドラマになると、フィクションかノンフィクションかを先に謳うものが多いですけど、音楽だと全然そういうことがなくて、歌の中には真実がたくさんちりばめられていると思います。
- 橋本
- そう考えたときに、どこに真実を見出すかが気になるんですよね。『ドライブイン探訪』であれば全国に残るドライブインを取材しましたけど、次に出版する『市場界隈 那覇市第一牧志公設市場界隈の人々』という本であれば、6月に建て替え工事を迎える第一牧志公設市場周辺の風景を書き留めようと思って、取材を始めた本なんです。それはいずれも「今そこにある風景を書き記したい」ということで取材したんですけど、僕がすべての風景を記録しようとしているかというと、そんなことはないわけです。このトークイベントが始まる前に、見汐さんが「この通りは、昔はこんな通りでね」と話してくれたじゃないですか。その話を「そうだったんだ」と聞きながらも、じゃあ僕がこの通りの昔と今を取材するかというと、そうではなくて。それは別に、この通りには関心がないってことではなくて、気になっていることがあっても、すべてに目を向けることはどうしてもできなくて、見送ってしまうことがたくさんあるんですよね。そうすると、何を選ぶのかってことになってくるんだと思いますけど、見汐さんがおばあさまから伺っていた話はきっとたくさんあるなかで、その中から何かを選んで言葉にする作業がわるわけですよね。
- 見汐
- ちょっと話が変わるかもしれないですけど、自分が暮らしている街の中で、「あれ、ここ、急に空き地になってる」って場所があるんですよ。そこに何があったか思い出そうとしても、あまりにも当たり前にあったものだから、すぐに思い出せないわけですよ。あるいは、よく行っていたお肉屋さんとか花屋さんとか八百屋さんが、「何十年やってきましたが、この日をもってやめさせていただきます」という貼り紙を出して閉店することもあって。何十年もやってきたのに、貼り紙一枚で終わるのかと思うわけですよ。そういうのを見るたびに――歌にしたおばあちゃんの話もそうですけど、自分がピンポイントで反応したものは、形にしたいと思うんです。それは私のタチだと思います。ただそれだけ。皆さんが暮らしている街の中にも、急に空き地になっている場所ってあると思うんですけど、「ここ、何だったっけ?」と思い出そうとする行為のほうに私は興味があるというか。だから逆に、『ドライブイン探訪』みたいに、ずっとそこにあるものに対して取材されることのほうが、とっても勇気のいることだと思います。
- 橋本
- 取材したお店について書くときも、当たり前ながらかなり気を遣っていたんです。なかなか大変な環境の中を生きてこられた方がいたとして、でも、関係する方たちがまだご存命であると、それをストレートに言葉にすると差し障りがあるだろうなと思うんです。でも、その苦労をなかったことにはしたくないから、じっくり読んでもらうと伝わるように書いていて。たしかに、おっしゃる通り、まだそこにあるものを書こうとすると書きづらいこともあるんですけど、すべてが終わったあとで書くのはどうしても嫌なんですよね。文章にするということは、その文章を書いているその瞬間よりも未来にいる誰かに読まれることを前提としているわけですよね。そうやって未来を意識すると、いつかそれがなくなる日のことも意識してしまうから、だったらまだ目の前にあるうちに書いておきたいんだと思います。
- 見汐
- それ、すごいよね。私は「あるときはただあればいい」と思うから、自分が生きているあいだのことは、そっとしておいてほしい。
- 橋本
- そういう気持ちもわからないではないから、いつも「取材するというのは、余計なことをしているな」と思ってます。
- 見汐
- いや、自分はやらないってだけで、テレビなんかでもドキュメンタリーなんかを観るのは大好きだから、余計なことだとは思わないです。ただ「すごいな」と思って。
- 橋本
- 昨日は福岡から佐賀のドライブイン巡りをして、虹ノ松原の近くにある「ドライブイン鏡山」というお店にもお邪魔したんですね。
- 見汐
- ああ、うちの地元ね。鏡山は皆が遠足に行くところです。
- 橋本
- そこには展望台があって、虹ノ松原と海が一望できたんです。その展望台の近くに巨大な像が立っていて、一体何だろうと思って近づいてみると「松浦佐用姫」と書かれていたんですけど、すごくなんとも言えない表情を浮かべていて。近くにあった説明書きを読むと、佐用姫はある男性と恋に落ちたものの、相手の男性が出征のためにはなればなれになってしまって、佐用姫は鏡山の山頂から舟を見送って、七日七晩泣き続けて――。
- 見汐
- 石になった、と。
- 橋本
- その、「石になる」ってことに置き換えられるのが面白いなと思ったんです。ドライブインはちょっとした名所・旧跡の近くにあることも多くて、言い伝えが残る場所もちらほら見てきたんですけど、そういう伝説はなにかと石になりがちだな、と。それはつまり、強い思いが残り続けたってことを、硬くて風化しづらい「石」というものになぞらえたんだと思うんですけど、それが興味深くて。それで言うと、歌っていうものにも、「石」に近い何かを感じるんですよね。自分の気持ちであれ、誰かの気持ちであれ、それを短い言葉に詰め込んで、タイムカプセルのように閉じ込める。ずっと昔の人の感情が詠み込まれて、それが現代にいたるまで引き継がれてきた短歌も「歌」ですよね。そうやって焼き付ける作業って、すごいことだなと思うんです。
- 見汐
- どうなんでしょうね……。今、noteというサイトで「寿司日乗」という日記をつけてるんですけど、始めてみてわかったのは一日の終わりに日記をつけるって、めちゃくちゃしんどいんです。今日はこんな事がありましたって事だけを綴っているはずなのにいつの間にかその日の自分を反芻して、自己解決しようとして、こんなん毎日やってたら吐きそうと思ったんですよね。だから、日記をつけ始めたことで、「なんとなくやり過ごすのが日常だ」ってことがよくわかったというか、振り返って「あのときはああだった」というぐらいがちょうどいい温度で、毎日のことを一日の終わりに振り返っていたら身が持たないと思ったんです。ドライブインをやってこられた方たちが50年を振り返って「あっという間だった」と言うのも、そう思わないと続けてこれなかったというのもあるんじゃないかと。取材をしていく中で相手の方が口をつぐまれる瞬間とか、無言になる数秒が幾度かあったりしました?
- 橋本
- 口をつぐまれるということはなかったですね。やっぱり、取材する相手の方に、「自分の人生はこれでよかったんだろうか?」と思わせる聞き方はできないですよね。ただ、そういう芯の部分に触れる瞬間はあって、そういうときは口をつぐまれるというよりも、言葉のトーンがとても強くなる方もいらしたんです。トーンの強さということで思い出されるのは、戦争を体験された方たちの言葉で。ここ数年は何度となく沖縄を再訪していて、明日からも沖縄に行くんですけど、沖縄戦を体験された方が当時のことを語られると、やはりトーンが強いんです。あるいは、僕は広島出身で、祖母は被曝してるんですけど、祖母が戦争のときのことを話すときも、やっぱりトーンが強くて。それはきっと、そのときのことが強烈に焼きついていて、そのときのことを繰り返し思い返していて、そのときのことについて考えてきた言葉があるから、強くなっていくんだと思うんです。それは戦争まで遡らなくても、ここ数年で水害に遭われたドライブインを取材したときも、とてもトーンが強かったんですね。その強い記憶を受け取ったときに、自分はどうするかということはずっと考えてました。その強さを、僕がそのまま受け取って、代弁するように文章にすることだってできるけど、それはやってはいけないことだなと。
- 見汐
- この本の中では、橋本さんが取材して感じたことは必要以上に書かれてなくて、事実だけを綴ってますよね。改めてとても面白かったです。
- 橋本
- 今の話と重なることとして、今日は聞いておきたかったことがあるんです。見汐さんが2017年3月から開催されてきた「うたう見汐麻衣」という企画は、平岡精二さんという方が作られた曲を歌うことを一つの軸とするライブですよね。見汐さんは『ひきがたり』というCDもシリーズでリリースされていて、そこにはご自身の歌だけでなく、誰かの歌も歌われています。それで、今回のイベントの告知に向けて、書店の方から「見汐さんの肩書きは」という話が出たときに、よく使われる肩書きとしてシンガーソングライターというのがありますけど、見汐さんはシンガーソングライターという肩書きを使われませんでしたよね。
- 見汐
- 紹介されるときに、一番言われるのはSSW(シンガーソングライター)です。でも、そう言われるたびに「いや、違うんだよな」というのがあって。まあそんなことは私の気持ちの問題であって、人様からすれば何でもいいことですよ。ただ、いつまでたってもしっくりこないというのがあるだけで。
- 橋本
- 見汐さんはおぼえてらっしゃらないかもしれませんけど、いつだかの「うたう見汐麻衣」のあとに、僕がそそくさと帰ろうとしていると、見汐さんが話しかけてくれたときがあって。そこで僕が「僕の中ではもう、安室奈美恵か見汐麻衣なんです」という話をして。
- 見汐
- おぼえてますよ。「なんてことを言う人なんだ」と思いましたよ。「酔っ払ってるのかな?」と。
- 橋本
- 酔っ払っていたのは確かですけど、酔った勢いでいい加減なことを言ったわけではなくて。もうすぐ終わる平成という時代を振り返ると、シンガーソングライターと呼ばれる方が大勢登場した時代で、「私」が溢れた時代だったなという気がするんです。ただ、見汐さんの場合、「私」という容器にこだわっていない感じがすごくあって。安室さんも、数曲だけ自分で作詞されてますけど、あとは誰かが書いた言葉を「私」として歌っているんですよね。
- 見汐
- 安室奈美恵さんは私のような端くれ者からすると素晴らしいエンターテイナーであり、芸能人なので、まったく違うと思いますけど、私の場合、バンドもやっていますけど、それはまたこの「うたう見汐麻衣」でやっている事とは異なるもので。邦楽に限ってですがSSWと言われる人たちの歌を聴けない時期があったんです。「私はこういう人です」「私はこういうこともできます」っていうことのほうを、歌っていることよりも先に感じてしまって、自己実現や自己表現の手段として聴こえてしまう音楽には食指が動かないっていう。歌う人自身が「私を見て!」と言っているように感じることが多くて、歌そのものをちゃんと歌えている人が昨今少ないなと思っていた時期に「円盤」の田口(史人)さんから「歌うということがどういうことかあらためてやってみる企画をやらないか」と言われて始めたのが「うたう見汐麻衣」なんです。実際やり始めて気づくことも沢山あって、自分は歌の媒介であればよくて、そこに関しては自分がどうあるべきなどということは一切ないですね。
- 橋本
- 見汐さんのライブを観ていると、そこに愕然とするんですよね。今回のタイトルである「ただそれだけのこと」というのは、見汐さんが作られた「エンドロール」という曲に登場する言葉です。ある時間に対して「ただ それだけのこと」と形容するというのは、別に投げやりに言っているわけではないと思うので、すごい腹の据わり方だなと思うんです。僕はまだそんなふうに言い切れなくて。
- 見汐
- 何でしょうね。今はもう「ただ死ぬまで生きよう」ってことしか考えてなくて。その中で、自分の作品が誰かの永い友達になってくれたら本望だなということは思いますけど。
- 橋本
- これまでほとんど話したことがなかったのは、その腹の据わり方をうっすら感じていて、それが怖かったのもあるんだと思います。でも、今日、こうしてお話できてよかったです。
- 見汐
- こちらこそ、ありがとうございました。『ドライブイン探訪』、まだお買い求めになってない方はぜひ買ってください。