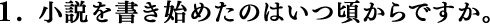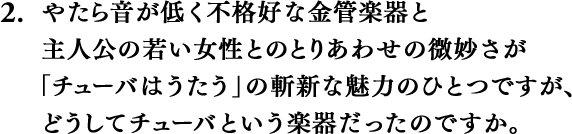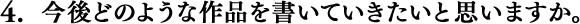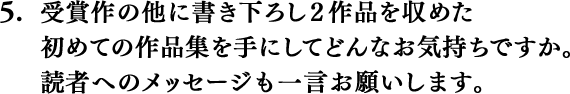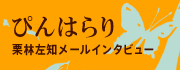第23回太宰治賞受賞作、いよいよ単行本で登場!
チューバ。でかい、重い、音がやたらと低い。この世に楽器はあまたあるのに、なんで私はこんなものを吹いているんだろう──。チューバのごとくでかく、不器用で無愛想な女子が、いつしかこの楽器の音に魅せられ、音楽にのめりこんでいく。そして訪れる奇跡の夜! 音楽のようにうねる文体が選考委員からも絶賛された受賞作に、渾身の書き下ろし作品「飛天の瞳」「百万の星の孤独」を併せて収録。
高校生のころです。偶然手にしたカフカの短編がやけに面白かったのがきっかけですね。
本来はそこで文学少年の道を歩むべきなのでしょうが、他にはろくすっぽ小説も読まず、ひたすらカフカのパチもんみたいな小説を書いていました。なにしろ短いので、あんまり忍耐力がいらないんですよ。だいたいルーズリーフの表裏で書き終わるので、授業時間を有効に活用できましたし。そんなわけで、カフカから小説を書き始めたのはメリットが大きかったです。
カフカの作品って「ぱっと見はマネできそうだけど実はそうではない」小説の典型だと思うんですが、「あーウンこれなら俺でも書けるな」と無邪気に思いこんでしまったから書けたようなもんです。思慮の浅さとモノ知らずとが結合すると、人間よけいな行動をとりはじめるみたいですね。
おおむね「若さゆえの行動力」と好意的に解釈されることが多いですが。
自分が中学校の時に吹いていたことが大きいと思います。当時、チューバという楽器の図体がでかいくせに陽のあたらない肩身の狭さをも身にしみて感じてましたから。
見た目のもっさりさ加減とか、持ち運ぶときの不便さとか、吹いていての目立たなさとか、チューバってつくづく報われにくい楽器だと思うんですよ。この「どうイジってもかっこよくなれない」雰囲気は大切だと思いました。いかにも女の人が吹きたがらなそうな楽器を女の人に吹いてもらうというのも面白そうでしたし。たとえばmit Violaとかmit Kontrafagottでも何とかなりそうですが、そのへんの総体的なかっこわるさに敬意を表して、mit Tubaにしました。
まあ後付けの理屈かもしれないですけど。
昔の雑誌とか新聞が大好きです。時代によって、人間の顔立ちや考え方って全然違うんですよ。最近取り沙汰される「空気」なる概念が、いかに移ろいやすく、曖昧で、後に何をも残すことがないものか思い知らされますね。
ウソだとお思いなら、一九九五年頃のオッサン向け週刊誌でコギャルの生態、一九八五年頃の若者雑誌でおすすめのデートスポット、一九七五年頃の婦人雑誌で結婚準備、一九六五年頃のグラフ誌で夏のリゾートの記事をそれぞれ探してみてください。図書館ですとタダですし、古書店でも一山百円ぐらいです。
あ、小説ですと、比較的海外の作品を読むことが多いです。この広大無辺、複雑怪奇、曖昧模糊な世界というモノにいかにして爪を立てるか、我らと同じ時間に生きている作家たちが払っている努力に対して、畏敬と嫉妬を憶えますね。昨年読んでいちばん面白かった小説、イスマイル・カダレ「夢宮殿」をお勧めしておきます。
いま新幹線の中でこの文章を書いてるんですが、隣では六十ぐらいの老夫婦が熟睡しています。斜め前の四十歳ぐらいの男性は「成功者になる方法」みたいな啓発書を読んでいますが、途中で飽きて寝始めた模様です。反対隣の三十路過ぎカップルは仲むつまじいことこの上なく、男性がエロいギャグをかまして女性のラメ入りマニキュアの爪でつねられたりしています。あ、さっき停まった駅から若い女の子が乗ってきました。ちょっと垂れ目気味ですが、アイラインにただごとならず気合いを入れています。後ろでは多分スキー帰りのオッサンたちがすごく楽しそうに酒盛りをしています。窓の外に目をやると、カレーのチェーン店と車の量販店とパチンコ屋とラブホテルが見えました。もう少し遠くにはマンションが見えて、川に架かる橋が見えます。その川の先には、太平洋が広がっているのでしょう。
そんな小説を書いていきたいです。
「チューバはうたう~mit Tuba」を世に問うてから、思いがけず、幅広い反応をいただいています。これは、大変嬉しい驚きでした。
この作品を分類するならば、音楽小説、楽器小説、女性小説などといろんなラベルが貼れると思います。また、主人公は意固地でありながら純粋であり、屈託を抱えながら一途です。おこがましくも言うならば、多少の多義性を持った作品なのだと思います。なので、さまざまに読み解かれることを祈ってはいましたが、読者の目は作者の期待をはるかにこえて、多角的に、精緻に、このテキストを解き開いてくださったようです。これは、本当に望外の喜びでありました。こうなれば、すでに作品は作者の手を離れているのでしょう。単行本の刊行をきっかけに、この作品が新しい未知の読み手に受けとってもらえるのならば、それが楽しく読まれることを祈るのみです。
併録された「飛天の瞳」「百万の星の孤独」は、新たに書き下ろした作品です。かたや南島の熱帯の密林、かたや北東北の小都市を舞台にしています。紀行小説と群衆劇、むりやりラベルを貼るならば、そういうことになるかもしれません。どちらも際だった事件の一つ起こるわけでもない小説ではありますが、どんな日常にも「物語」は潜み、それは語られる価値をもっているのだと思うのです。また、両者はかなり色合いの違う文体だと思われるかもしれませんが、これは「ものがたること」についての手法をほんのちょっと違えてみただけなのかもしれません。
こちらもあわせて楽しく読んでいただければ、作者として心から幸いに思います。