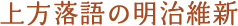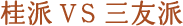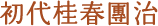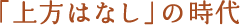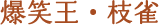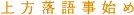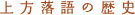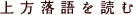神社の境内など屋外で活動を続けていた上方落語ですが、やがて当時の文化人が中心となって、座敷で一般から新作の小咄を募集して披露する素人咄の会が流行しました。この会は安永元年(一七七四)から天明末年(一七八九)まで行われ、多くの小咄本も発行されました。
その後を受けるように、寛政六年(一七九四)に、初代桂文治が登場します。文治は大坂の坐摩神社の境内に小屋を建て、そこで連日、落語を演じるようになります。これが大坂の寄席の始まりとなりました。この席で文治は、落語だけでなく囃子鳴物入りの芝居噺を得意ネタとして演じ、わらべ唄にも「桂文治ははなし家で」と歌われたほど有名な存在だったと伝えられています。そして、この文治が、現在東西に居る「桂」を亭号とする落語家のルーツとなったわけです。
幕末、上方落語は繁栄期を迎えます。「桂」以外にも「笑福亭」、「林家」、「立川」といった一門が並立して、互いにしのぎを削ることになります。この内で「立川」は明治十年前後に姿を消してしまい、残りの三派が明治の上方落語黄金時代を築き上げていくことになります。
そして、現在「上方の古典落語」として演じられている噺の多くが、この時代に創られており、一席の長さも今と同じ三十分前後のものになってきました。
幕末から明治にかけて上方落語の代表的存在というと初代桂文枝の名が挙げられます。三代目桂文治の弟子で、名人と呼ばれていました。十八番ネタの『三十石』を質入れして、質受けするまでは、いくらお客から注文されても決して高座で演じなかったという伝説を残しています。芸の面だけでなく、たいへん人望のあった人で、関西の寄席の楽屋には、文枝の肖像画が飾られていたと申します。
その門下には「四天王」と呼ばれた四人のすぐれた人材が揃っていました。初代桂文之助、桂文都、初代桂文三、初代桂文團治がその四人です。
明治七年(一八七四)に文枝が亡くなると、二代目襲名をめぐって文三と文都が争い、結局文三が勝利を納めます。敗れた文都は「桂」を捨てて「月亭」を名乗り、別派を立てることになります。このトラブルが引き金となって、明治の上方落語界では、さまざまな派が離合集散することになりました。
明治二十六年(一八九三)に至って、月亭派と文團治派と笑福亭派の三派が合流して「浪花三友派」を旗揚げして、文三の二代目文枝が中心となった「桂派」との熾烈な戦いを開始します。この二つの派の闘いのおかげで、明治の中ごろの上方落語界は百花繚乱の黄金時代を迎えることになります。
この両派の特色を簡単に申しますと、「桂派」はあくまでも話芸を重視して、色物もあまり使わず地味な興行を行っていました。それに対して「三友派」は派手で陽気をモットーにした興行で人気を集めていました。東京からのゲストも積極的にどんどん招き、その結果、来阪した東京の落語家の手によって上方落語の多くが東京落語に輸入されるということにもなりました。
二派の闘いは明治の末に「桂派」が「三友派」に吸収されとしまうことで終結することになるのですが、その「三友派」も新興芸能である漫才の勢いに押され、次第に寄席の主流の座から追われてしまう結果を招いてしまうに至ったのです。
そんな時代の流れに最後の抵抗を試みた落語家が初代桂春團治でした。いかにも大阪らしい、濁ってはいるが陽気な声の持ち主で、普通の人間では思いも付かないようなナンセンスなギャグを連発するその高座は、聞いているお客が笑いすぎて「く、苦しい。もう堪忍してくれ」と悲鳴をあげるほどだったと伝えられています。SPレコードでも人気を集め、落語のレコードを出した数では東西を通じてナンバーワンでした。「人生そのものが落語」と言ってもいい人で、多くの伝説を残しています。その破天荒な人生は小説や演劇、映画、歌謡曲にまで採り上げられています。
その初代春團治が昭和九年に没すると、いよいよ寄席は漫才中心となってしまい、落語は添え物的な扱いになりました。その風潮に反旗を翻した五代目笑福亭松鶴は寄席を退き、四代目桂米團治たち同志と「楽語荘」というグループを結成し、「上方はなしを聴く会」という自主公演を続けるとともに、雑誌『上方はなし』を発行。上方落語の保存に死力を尽くしました。
太平洋戦争に敗れ、大阪は焼け野原になってしまいました。十人ほどの人数になっていた上方落語界に、昭和二十二年(一九四七)、四人の若者が身を投じて来ました。彼らは文字通り「食うや食わず」の生活を送りながら、好きな落語を復興させるべく努力を続けました。この若者たちとは笑福亭松之助(後の六代目松鶴)、三代目桂米朝、桂小春(後の三代目春團治)、桂あやめ(後の五代目文枝)。後に「上方落語の四天王」と呼ばれるようになった四人の若き日の姿だったのです。
同年の九月には、彼らの入門を祝うように戎橋松竹という、戦後初の落語定席が開場。翌年には若手のための「落語新人会」も開催されるようになりました。
ようやく光明が見えはじめたかに見えた上方落語界に、過酷な運命が降りかかります。上方落語を伝えていた五代目松鶴、立花家花橘、四代目米團治、二代目春團治などが昭和二十五年から二十八年にかけてバタバタと世を去り、マスコミからは「上方落語は滅んだ」と報道されました。
それでも地道に落語会活動を続けていた若手に希望の光を与えたのが、昭和二十六年(一九五一)の民放発足でした。次第に番組でも採り上げられるようになり、昭和三十年(一九九五)には朝日放送主催の「上方落語をきく会」が定期的に開かれるようになり、現在も続いています。
また、落語家も次第に数を増し、昭和三十二年(一九五七)に「上方落語協会」が発足したときには、老若取り混ぜて二十二人にまでになっていました。
同じ年には京都市が主催する「京都市民寄席」がスタート。こちらも現在まで続く老舗の会になりました。
昭和四十年代になると、おりからの深夜放送ブームで、民放のラジオDJ番組から月亭可朝、笑福亭仁鶴、桂三枝といった落語家のスターが生まれました。これらの人気者たちが招き猫となり、当時の大学生を中心とした多くの若者たちが生まれて初めて落語会に足を運ぶようになりました。そして、人気者を見に来たはずの若者たちは、同じ会に出演していた四天王の芸に触れて、上方落語の奥深さの虜になってしまいます。
そのころ、学生時代を送っていた筆者も、あたかも濃霧の中から突然巨大な氷山が出現したような驚きを受けたことを記憶しています。これが、俗に「落語ブーム」と言われるようになったできごとです。
定席を持たない上方落語の中で、桂米朝は昭和四十一年の祇園祭の宵山の日に京都勤労会館で開催した「米朝スポットショー」を皮切りに、積極的にホールでの独演会形式の公演を全国展開し、上方落語を全国区の芸能に育てあげました。
そして、大阪万博の翌年の昭和四十六年(一九七一)には、朝日放送主催の「一〇八〇分落語会」が開かれ、定員六百人の開場に延べ五千人のファンが詰めかけました。その翌年の二月からは、大阪市南区の島之内教会を会場にして、月に五日間の上方落語定席「島之内寄席」がスタートしています。このころの落語界は活気にあふれていて、どの落語会にも大勢のファンが押し寄せ、テレビやラジオでも落語家が大活躍していました。
上方落語ブームが次第に鎮静して行く中、「上方」という枠を超えた全国区の爆笑王・桂枝雀が頭角を現してきます。確固たる理論のもとに築き上げられた爆笑の世界は、まさに新鮮な驚きを「落語は古臭いもの」と思い込んでいた人たちにも与えてくれました。
これは私の意見なのですが、上方落語は昭和二十年代でいったん滅んでしまったのではないかと思うのです。いったん滅んでしまった上方落語を、米朝をはじめとする四天王たちが現代人の目で再構成しなおして発表したために、昭和四十年代に若者たちが「新鮮な芸」と感じて飛びついたのではないかと思うのです。そして、その「新鮮な芸」として復活した上方落語を伝統として固定化するのではなく、さらに新しい未来の可能性を与えてくれたのが枝雀ではないかと思うのです。
その枝雀を喪った穴はあまりに大きすぎるのですが、嘆いてばかりもいられません。平成十八年(二〇〇六)には、六十年ぶりに落語定席の「天満天神繁昌亭」も開場。文字通り繁盛を続けているようです。後に残された落語家たちの活躍によって、上方落語はこれからも進化をし続けることでしょう。