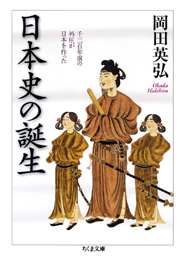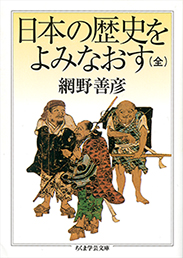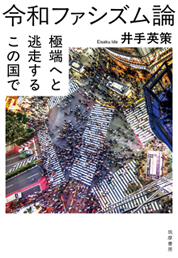広田照幸
( ひろた・てるゆき )1959年生まれ。現在、日本大学文理学部教育学科教授。研究領域は、近現代の教育を広く社会科学的な視点から考察する教育社会学。1997年、『陸軍将校の教育社会史』(世織書房)で第19回サントリー学芸賞受賞。著作に『教育は何をなすべきか――能力・職業・市民』(岩波書店)、編著に『歴史としての日教組』(名古屋大学出版会)など多数。
loading...
陸軍将校もまた、生身の人間だった。日本における天皇制と教育との関わりとはどのようなものであったのか。満州事変から太平洋戦争へと至る、戦時体制の積極的な担い手はいかなる存在であったのか。旧軍関係者への聞き取りを行うとともに、旧軍文書や文学評論、生徒の日記など膨大な史料を渉猟し、その社会化のプロセスをつぶさに浮かび上がらせる。下巻には、「〈第2部〉 陸士・陸幼の教育」第3章から「〈結論〉 陸軍将校と天皇制」までを収録する。教育社会史という研究領域の新生面を切り拓いた傑作。 解説 松田宏一郎
〈第II部〉 陸士・陸幼の教育
第三章 将校生徒の自発性と自治
第一節 はじめに/第二節 天皇への距離/第三節 自治と自発性 第四節 小括
第四章 将校生徒の意識変容
第一節 将校生徒の本務=勉強への専心/第二節 ある生徒の日記から/第三節 小括
第五章 一般兵卒の〈精神教育〉
第一節 はじめに/第二節 徳目から世界観へ/第三節 精神訓話の限界 第四節 将校の自己修養/第五節 身体訓練と監視/第六節 〈精神教育〉の限界と効果
〈第III部〉 昭和戦時体制の担い手たち
第一章 社会集団としての陸軍将校
第一節 はじめに/第二節 昇進の停滞/第三節 俸給水準の相対的低下/第四節 退職将校の生活難問題/第五節 構造的問題 第六節 将校の意識と行動/第七節 小括
第二章 「担い手」諸集団の意識構造
第一節 課題/第二節 憲兵・兵士・在「満支」邦人/第三節 教師/第四節 小括
〈結論〉 陸軍将校と天皇制
第一節 近代日本の陸軍将校/第二節 イデオロギー教育とは何であったか/第三節 「内面化」図式を越えて
註
文献一覧
あとがき
解説 松田宏一郎
本書をお読みになったご意見・ご感想などをお寄せください。
投稿されたお客様の声は、弊社HP、また新聞・雑誌広告などに掲載させていただくことがございます。