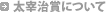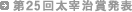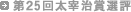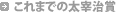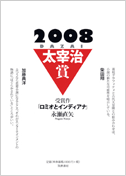2008年5月8日、第24回太宰治賞の選考委員会が、三鷹市の文化施設「みたか井心亭」で開かれました。 選考委員4氏(高井有一、柴田翔、加藤典洋、小川洋子)による厳正な選考の結果、受賞作として選ばれたのは、永瀬直矢「ロミオとインディアナ」でした。 最終候補となった4作品を、選考委員はどう読んだのでしょうか。 4氏による選評です。


新人賞候補作のすべてが優れた作品ではないのはむしろ当然だが、作者の気持ちを感受できれば、評価は別として読むことが苦痛だということはない。しかし今回の三候補作は、そこの言葉がこちらへほとんど届いてこないもどかしさがあった。
何故だろう。単にこちらの感受性が鈍っただけかも知れないが、あえて言えば、この書き手たちは現在の人間の相互関係の希薄さを描こうとして、あるいは無意識にそれを描いていて、結局自分もその蟻地獄の中へ吸い込まれ、他者へ向けての言葉を発することができなくなっているように思える。
小説とは、小さな真実に支えられた壮大なだと言ったのは、バルザックだっただろうか。「夜は朝まで」には人間の周囲に存在するそうした〈小さな真実〉へ視線を向けようとする意志がまったく感じられない。中年男が飛び込み自殺をする冒頭場面でも、急ブレーキを掛けたはずの電車の車体の軋み、飛び散っただろう男の肉片と血の匂い、駆け寄る野次馬たちの好奇心と恐怖の混じり合ったどよめきなどが何一つ存在しないまま、〈僕〉の説明的な言葉だけで、話だけが進む。その話の軸は汐華の「あなたが自殺しないなら、私が自殺する」という〈僕〉への挑発だが、そうした(それ自体としては悪くない)小説的仕掛けも、汐華と〈僕〉の細部の真実があり、二人の関係性の〈小さな真実〉があって初めて小説的力を持ちうるのであって、世間出来合いの苛め体験や優等生の悩みで二人の現状を説明され暗に正当化されても、読者は白ける他ない。
「夏の魔法と少年」は、引き籠もりのような、悠々自適のような、中年に成りかけの青年が、不登校の小学生の甥を兄に押し付けられ、毎日ふたりでコンビニ弁当ばかりを食べながら過ごすひと夏の話だが、外的にも内的にもなかなか小説が動き出さない。全体のおよそ半ば、隣の老女の死を契機に漸く進行し始め、他者との無関係性を享受しているかに見えていた〈私〉が実は関係性を渇望していたという話になる。そういう彼と登校拒否の甥とはいわば最適の共依存ペアとなるはずだが、〈私〉は甥に自立する力を発見して、涙ながらに彼を兄の許へ送り返す—。だが私には、主人公の言葉から関係性を渇望する本当の声が聞こえてくるとは思えなかった。その一因はおそらく、〈私〉が先生や兄へ向ける優越的視線に、作者が何の疑いも示さないところにある。主人公は自分の引き籠もりを悠々自適だと思い込みたがっている。だが作者にとって主人公は、引き籠もりなのか、悠々自適なのか。作者の意識も主人公と同じ曖昧さの中で、気楽に浮遊しているのではないだろうか。
「背守りの花」は、夫を亡くした姉とその中学生の娘、そこに離縁されて戻ってきた三十代の妹が加わった三人の女家族のそれなり穏やかに推移する日常、そこへ加わった猫との交流を描いて、一見、人間関係の希薄さとは逆の状況を描いているかのように見える。だがそれは見せ掛けに過ぎない。例えばそこで繰り返される、あまりに人工的で自己陶酔的な自然描写は、人間の関係性が希薄化曖昧化して把握困難になっている現在の事態を裏側から示している。事実、三人が家族の外で当然持っているはずの人間関係(それは家族の中へも必然的に浸透してくる)、例えば娘の学校生活は完全に無視される。更に家族内においても、理想的だったとされる姉と亡夫の夫婦関係でさえ、ほとんどが一般的な言葉で説明されるだけであって、情景が具象的に描きだされることはない。作者が傾倒しているらしい「細雪」では、谷崎の貪欲な視線が掘り起こした女家族一人一人の生活の具体相こそが小説の内実なのだが。作者は人工的自然描写、単性増殖を続ける金木犀のイメージ、そして女家族のムードに酔って、自分の世界の空虚さに気づくことがない。
受賞作「ロミオとインディアナ」は、一言で言えば現代の高校生活グラフィティだが、そこに不可視空間である古代天皇陵が加わり、その両者が主人公の現実の視線と、更に虚とも実とも定まらぬブログを通して二重に結び付けられたことで、小説の可能性が大きく開けた。
私(惠理)とお節介な友だち真樹の二人を中心にした高校生たちの、一年から二年に掛けての何カ月かの日常。そこには仲間との結びつきもあり断絶もあり、傍から見れば(真樹の妊娠事件も含め)ごくごくありふれた現在の高校生活だが、しかし本人たちにしてみれば生まれて初めての十六歳十七歳だし、決して二度は経験することのない十六歳十七歳でもあって、それなり胸を高鳴らせたり、不安に怯えたり、年齢相応に一瞬、心を震わせたりもする。その両者のバランス、客観的には平凡事が本人にとっては掛け替えのない瞬間だという感覚が、歯切れのいい描写を通して自ずと伝わってくる。仲間の生徒たちだけでも十人を越え、そこに数人の先生たち、更に親たちや鳥打ち帽子の男や警官まで加わってなかなか賑やかだが、ほんの数行で描かれる点景人物でも、例えば倉内に告白して振られた吉田博美が主人公を睨む視線の一瞬の鋭さ、夜中、息子のために警察署に呼ばれて駆けつけた倉内の母親の化粧(彼女の張りつめた人生そのものだ)などなどが読者に鮮やかな印象を残す。
そうした高校生活グラフィティ(落書き)の間を縫って、惠理と倉内の間柄が迷走する。惠理は、すぐに男といちゃいちゃする親友真樹のような女の子を軽蔑している男の子っぽい女の子で、真樹がその惠理に倉内を当てがいたがるのなどはまったくもって余計なお世話なのだが、それがそれで終わらなくなるのは、自分の部屋の向かいに見える古代天皇陵のせいだ。
古代天皇陵の考古学的調査が宮内庁によって拒否されていることは、よく知られている。古代天皇陵はその意味でこの国に内包された不可視空間だが、そこへ不法に潜入した(と称する)男(?)が濠を隔てて住む惠理のブログへ通信を送ってくる。いや、真偽判定できぬブログだけではなく、鬱蒼と繁る木々の間から光の点滅信号さえ送ってくる……ような気がする。
十七歳の惠理は今まで男とのいちゃいちゃなど蹴っ飛ばし、勢いよく、男の子っぽく、すべて割り切って生きてきた。惠理にとって人生は明快だった。だが今や、初めて割り切れぬ状況に遭遇したのである。
ここで小説は、高校グラフィティを越えた向こう側の空間への可能性と出会う。倉内と出掛ける惠理の心の中に、濠の向こうのような未知の空間が開け始めるのかどうか。あるいは惠理は倉内を引き連れ外界への冒険へ乗り出して、神聖空間に潜入した男に遭遇し、世の常識を越えた世界を垣間みるのか。
戦後、子どもだった惠理の父親はそこで釣りをしていたという。不可視空間が脱神秘化された一時期もあったのだ。
残念ながらこの作品は、そうした非日常領域への探索の手前で立ち止まっているが、高校グラフィティと古代天皇陵との組み合わせは、小説の新たな可能性を暗示している。
今回で選者としての私の仕事は終わるが、亡くなられた吉村昭さんをはじめ他の選者の方々との選考は、意見の相違はあっても、いつも何のも混じらない気持ちのよい時間だった。その中でいくつかの、心から支持できる作品に出会えたことも、大きな仕合わせだった。筑摩書房と三鷹市の共催になるこの賞が、今後も優れた作家を見出す場であることを信じて、選評を閉じたい。