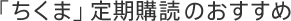日本語で読む 日本語で書く/水村美苗 小池昌代
近代文学を読み継ぐ
小池 水村さんのいままでお書きになったもの、たとえば小説は小説で、大きな読む喜びを与えてくださるものとしてありますが、『日本語が亡びるとき』にはじまって、最近出された『日本語で読むということ』『日本語で書くということ』に入っている評論やエッセイなどもあわせて読むと、それらすべてでもって、文学は文学のなかから生まれてくるものでもあるということを体現してくださっているというふうに思うんです。私ぐらいの年齢になってくると、どんどんいにしえに遡っていきたいという気持ちが出てきますが、若いときは、もっとも新しい現代のものから刺激を受けたいという気持ちが強かった。いま、学生たちと接する機会があって、彼らを見ていると、やはり昔のものが読めないというか、読みたくない、読む気がないという態度があるんですね。
水村 私の書くものを、そんなふうに読んで下さって、とても嬉しい。おっしゃる通りだと思います。『日本語が亡びるとき』を出してから、日本の人文教育に問題があるという思いが、いよいよ深まったぐらい。きちんとした「国語」が流通している国では、ふつうは、明確な理念があるんですよね。現在、国民が使っている書き言葉の黎明期というか、それが確立された時代まで一応遡る。それが、当然のこととして、国語教育の理念となっているのです。ところが、日本ではその理念が共有されていない。非西洋語圏の悲劇の一つかもしれません。若い頃に学校で読ませれば、かんたんに読めるようになるのに、そこまで降りる梯子を外されてしまったようなものです。
小池 私なんかの世代でも、漢文が読めない、古文も遠くなってしまっている。樋口一葉も難しいんです。一葉は、学校教育のなかでは一度も読まなかったんですよ。
水村 思えば、私は、子供のころに日本の外に出ることによって、日本の教育システムを抜けることができたんですね。
小池 抜けたことによって、ようやく「たけくらべ」とか、近代文学をガッチリ読むことができたということなんですね。
水村 少なくとも、何の違和感もなく読めるようになった。書き言葉というものは、あるときに、固定されます。近代に入ってからは、ある国が国家として成立し、本と教育とが行き渡り、「国語」で読み書きされるようになったときですね。そして国語教育の理念は、ふつう、そのとき書かれた、優れた文学を古典とし、そこまで遡ろうというふうに設定されています。あくまで理念ですが、イギリスやフランスだったら十六、七世紀まで。ドイツだったら少なくとも十八世紀、ロシアだったら十九世紀前半まで。日本は十九世紀後半にはもう優れた近代文学があった。西洋の主な言葉に比べれば遅い方ですが、ほかの非西洋圏に比べたらものすごく恵まれているんです。
小池 私は、「たけくらべ」を知らずに大人になって、四十過ぎて読もうと思ったとき、最初は難しくて大変だったんです。でも、朗読CDの助けを借りて、言葉の一つ一つから、本当に細い水脈を辿るようにして入っていくことで、だんだん薄皮を剥がすように馴染んでいって(笑)。その一葉のテキストの中にも、江戸はもちろん、平安時代までもが響いていて……。
水村 ほんとうにそう。近代文学の黎明期に戻ったら、前近代が響いているんですよ。日本語のような非西洋語の場合、それは宝物のようなものです。西洋と別の世界が、息づいているのですから。それでいて、樋口一葉はもう近代人だから読める。
根深いものを育てる
小池 なるほど。そうですね。ひとつの作品の中に、さらに時代をさかのぼった、別の作品が覗く、そういう複雑な響きをもった作品を読む豊かさ、面白さを、何か、か細いながらも伝えていきたいと思うんです。特に古典なんかは、どんなふうに当たりをつけて読んでいったらいいのか。梯子を外されてしまったような人たちにとって、わたしもそうですけれど、水村さんがすごく柔らかい形で登場してくださって、導いてくださったという感じがしています。
水村さんはアメリカで一葉や漱石を読んでいくにあたって、最初からスーッとお読みになれましたか。
水村 まさか(笑)。子供ですもの、わかるところから順番に読んでいっただけです。朧気にわかるものをくり返し読んで。
小池 とりあえず、手に入ったものを、わかるところから読んでいくと。
水村 そうです。あとは総ルビでしたから、子供には助かりましたね。ほかに読むものがないのもよかったと思います。
でも、私のようにほかに読むものがないという状況は例外的ですよね。ふつう十代の子供は、本屋にたくさん出回って、友達が読んでいる本を読もうとして、当然でしょう。そんなとき、教育の場が、唯一、古典に強制的に触れさせられる場だと思うんです。声に出して読んだりもすれば、とってもおもしろい授業になりうるのに。
小池 インターネットの出現というのが大きかったのだと思いますが、英語が世界を覆い尽くしていくなかで、それによって、いわゆる「叡智を求める人」が日本語で本当にこの先も書いていくのかと問いかけておられます。水村さんがいままで培われた近代文学への愛情とか、そういうものによって、ご自身は日本語で書くことを選んでいらっしゃったわけですが、一度も英語で書いてみようとは考えられなかったでしょうか。
水村 それが若い頃は、一度もなかったの。英語がすでに支配的な言葉であるという事実がわからなかったんですね。世の中を鳥瞰図的に見下ろせるだけの知性もまだなければ、そういう鳥瞰図を持てるような階級にも育っていなかったから。ごく自然に日本語で書こうと思っていました。
今、一番怖いのは、ネットの力もあって、日本語を真剣に読む人がいなくなるということなんです。書く以前の問題です。梯子を外されてしまった状態で、今流通しているものだけ読んでいると、根深いところでの愛情が十分に育たない。それが十分に育つような形で日本語を読み継ぐのが、まずは最も大切なことだと思っています。
小池 根深いものが育たないとおっしゃったことは、本当に腑に落ちる言葉ですね。水村さんを特徴づけるものというのは、まさにその根深さのような気がするんです。この人は何か根深いところに接触していて、こういうことを言っている、ということが、読者にわかるんですよ。そういう人の言葉によって導かれ、文学の世界に入ってくる人は、今後もいるような気がします。だから、危機感はありますけど、私は前向きに考えています。
水村 日本語はほんとうに恵まれた言葉なんですよね。五十年後に人口が半分に減ったところで、母語集団がまだ六千万人いる。世界の中で、とても大きい言葉なんです。しかも、GDPが高いから、高い教育を受けた人がほかの国に逃げていかない。
GDPの高さなど、言葉というものを考えるとき、つい考え忘れてしまいますけど、とても重要な要因なんです。このまえセルビアに行ったときに知って驚いたんですけれど、百人アメリカで博士号を取ったとすると、五人も戻ってきてくれないそうです。それに引き替え、例えばノルウェーなどは人口は五百万人もいないのに、GDPの高さによって、教育を受けた人が国内に留まっている。みんな驚くほど英語ができるんですけれど、ノルウェー語の作家はまだ絶望していない。ところが、一人当たりのGDPが日本の三分の一以下しかないセルビアでは、読者たるべき人たちの空洞化が起こってしまっている。作家たちは絶望的な思いで書いているそうです。
世界を見回せば見回すほど、日本語は恵まれていると思います。ただし、忘れてはならないのは、日本語が、とことん孤立した言葉だという点ですね。守るのは、私たちしかいないんです。日本の文部科学省がロクでもない教育で突き進んだら、それっきり。文化というのは、一度亡んだら、それきりですから。基軸言語の英語では、アメリカがロクでもない教育をしたところで、英語を母語とする国が他にあるし、旧植民地で高等教育で使っている国もある。一つの国の教育が失敗しても、どこかではまともな読者が育ってゆく。それが英語の強みですね。しかも、セルビア語だって、分離したばかりのクロアチアやモンテネグロがほとんど同じ言葉を使っている。それに基本的にはスラブ系の言葉ですから、ロシア語ががんばり続ければ、セルビア語が亡んでも、そのまた従兄弟ぐらいは残る。日本語はそういうわけにはいきません。
詩と散文と国語
小池 このあいだ私の詩をインドでヒンディー語にしてくださるといって、あいだに日本の友人が入っていまして、最初は当然のように、日本語とヒンディー語の対訳詩集で、と双方思ったんです。インドでも、日本語を読める人、研究している人は少ないけれどもいる。日本語は私たちのシスターランゲージみたいなものだ、ともおっしゃって。同じアジア圏ということもあるでしょうし、非英語、非普遍語だという意味でもあるでしょう。けれどそのときに、もう一つの考え方が現れた。英語とヒンディー語の対訳詩集にしたほうがたくさんの読者を得られるのではないかという意見が日本側から出たんです。
水村 それはよくわかるんですけど、そうすると、小池さんのオリジナルの詩はどこに行ってしまうんでしょうねえ。
国語について考えるとき、インドは、国語の成立の困難を実によく映し出してくれる国だと思います。旧大英帝国であると同時に多言語国家ですから。小池さんの対訳詩集の問題に顕れているように、誰にでも読める国語というものがない。そして、それらの多言語間の共通語が英語である。
知識階級は英語と母語と二つを知っていいますが、もちろん、この二つは同じレベルでは機能していません。母語集団として一番大きいヒンディー語。文学の言葉として威張っているベンガル語。そのほか、ウルドゥー語やらタミル語やら、数限りなく言葉がある。そして、それらの言葉に共通して言えることは、知識階級では詩文の方が盛んだということです。逆に言えば、知的に高度な散文には圧倒的に英語が使われているということですね。高等教育が英語だから当然なんですけれど。
要は、詩文は母語というか現地語でがんばり、思考する言葉は英語でやろうということになってしまっている。この現象が私たち日本人にとっても人ごとではないのは、これからは、どの国でも、似たような傾向が出てこざるをえないからですね。文学はそれぞれの言葉でやり、そして、学問は英語でやろうという傾向。いわば言葉の分業です。でも、その分業があまりにも極端になると、散文としての文学の質が徐々に劣化していってしまうように思います。
小池 それがインドにも言えると。
水村 インドは、劣化していってしまうというよりも、散文としての現地語が、十分に発達する機会がなかったと言えるでしょう。ですから、知識人はあまり母語で散文は読まない。詩は母語で読み書きされないと意味がないから、特別なわけです。
小池 そうですね。詩は最終的に母語で書くというところに行くと思います。タゴールの詩を読んだとき、面白いことがありました。私はベンガル語はできませんから訳を読むわけですが、ベンガル語の原詩を、岩波文庫では渡辺照宏さんが日本語の文語韻文で訳しているんです。それくらい、ベンガル語の原詩は音楽的らしい。その原詩を、タゴールは自ら英訳した。英訳したからこそ、ノーベル賞に繋がったわけですが、不思議なことに、タゴールが英訳したものは、行分けの韻文でなく、散文詩なんですよ。なぜでしょう。とにかく英語にしたとき、韻文詩が散文詩になってしまった。というわけで、岩波文庫の『タゴール詩集』では、一部の詩について、ベンガル語から訳した韻文訳と、英語の散文詩から訳した散文詩訳と、同じ内容のものが二つ読めます。読み比べると、明らかに散文詩が韻文詩の説明になっていて、わかりやすいけど、つまらないんです。
水村 なるほどねえ。韻文にはなんともいえないものがありますものね。歴史的には、書き言葉というのは、散文のほうが遅れて発達しますでしょう。小さいころは逆に考えていたんですけれど、あるとき、韻文が先行することに気がつき、それは、大きな発見でした。韻文には、英語でネモニック・ディヴァイスといいますが、人間の記憶を助ける働きがある。書き言葉の本質は、残り、広がる、ということにあると思っていますが、韻文は、まさに縛りがあって記憶しやすいがゆえに、口づたえで、残り、広がる。つまり、韻文は、書き言葉が存在するまえの、原=書き言葉だと考えられると思うんです。話し言葉とは断絶した不自然な法則に縛られているので、散文よりも一見人工的な印象を与えますが、実はあの不自然さこそ、ある意味で自然だった。
ですから、逆に、韻文を散文にするというのは、国語が高みに達しないとなかなかできないわけですね。ラテン語が規範的な散文として流通していたころでも、吟遊詩人などがいて、現地語の詩は流通していた。イタリア語の父といわれるダンテの『神曲』も韻文です。でも、そのイタリア語を擁護する文章はラテン語で書いている。まだイタリア語で散文は書けないんですね。国民国家が生まれる頃からしか現地語の散文は生まれず、多くの言語においては、散文は生まれないまま終わってしまう。
小池 なるほど、よくわかりました。
外部にある書き言葉
水村 でも、いったん国語ができてしまうと、その書き言葉が自然なものに思えますでしょう。特に日本のような島国ではそうですよね。アフリカの小さな部落なんかでは、小学校に行っても、共通語を学ばなければならないということで、話し言葉と書き言葉が違うというのは、ある意味で日常的なことなわけですね。でも、私たちは日本語がすでにできてしまったところに生まれ落ちて、書き言葉が外部のものであるということには、全く気がつかない。
小池 言語が外のものであるということがわからないんですよね。
水村 全くわからないと思います。
小池 だから、水村さんは内部にいて、そこから疎外されているようなものに対するシンパシーがおありなんじゃないですか。『日本語で読むということ』に入っている幸田文についての「大作家と女流作家」、よく書いてくださったなという感じでした。あまりこういう形で幸田文のことを書いてくださる方はいなかったと思うんです。
水村 あの人の日本語はすごいですよね。
小池 そうですよね。彼女自身は、「こんなところで私が書いていて、いいんでしょうか」みたいに言って、端のほうで細々とやっているような印象を与えるのに。
水村 国語の高みですよね、やはり。ほとんど外国語は読めなくて、あれだけのものを書けるというのは。
小池 そうなんですよね。
水村 小池さんのお書きになるものは、幸田文にどこか似ているって、いつも思っているんです。それに、小池さんて、とっても寛容なかたですよね。現役の物書きの中には、今回の私の本に怒っていらっしゃるかたたちがいるって聞いています。いまの文学がつまらないなんて、日本でも、世界でも、みんなが言っていることでしかないので、そんなところで反感を覚えるかたたちがいるとは思わなかったのですが。
実は、私が日本語の劣化ということで最初に驚いたのは、昔むかしのことで、十八でボストンに行って、同年代の日本人の日本語に触れたときなんです。今書いていらっしゃるかたなんか、まだ生まれていないころ。日本で教育を受けてきたはずなのにと、本当にショックでしたね(笑)。
小池 私は、一度も外に出て生活したことがないので、日本の風土にはなじみすぎておりますから、逆にそういう反応が出てきて、勘違いされるのではないかと少し危惧していたんです。みんなそれぞれ、ご本を読んで、自分に具体的に引きつけて考えてしまいますから。
水村さんのおっしゃることはまっとうなのですが、べつに、現代文学の個々がどれもダメだということではなく、流れが断ち切れてしまった「現代」というものの貧しさについて危機感を叫ばれた、そのことがうまく伝わっていないもどかしさが、私なんかにはあります。
水村 非西洋の中であれだけの近代文学があるという事実の重み。それについて考えないまま、たった百年前の文学を読めない世代を戦後につくってしまった。取り返しのつかないことをしてしまったのではないかという憂いが根底にあったんです。
小池 これからの英語教育や日本語教育について、ご本の中で書かれていましたが、一部の人にエリート教育的な形で英語を学ばせて、日本語で考えているのと同じぐらいにしゃべれて書けるというのは、ほかの何か大きなものを犠牲にしないと身につかないぐらい、大変なことですよね。
水村 そう。本当に大変なことなんですよ。日本語はまったく違うし、日本にいれば英語は必要ないし。ただ、今後そのような人材は、絶対に必要だと思っています。その上で強調したいのは、母語ができないと、外国語はできないということです。
小池 例えば、そのエリートと作家の一部が重なった場合、直接、英語で書いたり、もちろん翻訳もされて、さらに読者が増えていく。そのような形で作家がインターナショナルになっていくということも、お考えにありましたか。
水村 それはどういうものを書くかによるんじゃあないでしょうか。世の中は全く不公平で、英語圏の人は母語で書き、ほとんど何も犠牲にしないまま世界で読んでもらえる。でも、英語圏の外の人たち、ことに日本のように、はなはだしく違う文化圏に住む人たちは、そういうわけにはいかないでしょう。ファンタジー・ノベルやミステリーなら翻訳可能なものを書けると思いますが、日本語でこそ捉えられる日本の「現実」を捉えたいのなら、翻訳ということは考えないほうがいいような気がします。
小池 翻訳で広がって、読者の数が増えていくということは喜ばしいかもしれませんが、どのように伝わるかが問題ですね。私はもともと読者数が少ない詩の分野で書いていたので、今後もそのわずかな人に向けて書いていくような気がしています。
水村 それでいいと思います。というより、そのほうがいいぐらいだと思います。私の『本格小説』は数カ国語に訳されていますが、それは、通俗的なメロドラマが根底にあるからだと思います。でも、書いているときは、翻訳されるなんて夢にも思わないで書いていた。それが、本当によかったと思っています。今、ある出版社から、次の作品も翻訳したいって言われているのですが、それは、かえって精神的に負担です。日本語を読めない外国の読者を獲得するために、何も自分がやりたいことを犠牲にすることはない。文学なんですから。
その歳、歳の書き方
小池 私、ファンとしては、最初は『日本語が亡びるとき』一冊だけだと思っていたら、サプライズみたいな形で、そのあとバン、バンと『日本語で読むということ』『日本語で書くということ』二冊が出て、すごく満足感があるというか、全体像や経緯が見えてきて面白かったです。二冊とも、それぞれにとても特徴があって。特に『日本語で読むということ』には、水村さんがいままであまり書いていらっしゃらないことがたくさん詰まっています。
水村 そんなふうに言って下さると、ありがたいわ。私は書き始めたのが遅いんですね。いまの人たちは別でしょうけれど、私の世代は、まだ「お嫁さん」になること以外は考えなかった世代だから、みんな遅いんですよ(笑)。だから、体力的限界があるので、書けるうちに長編を書いてしまわなければと思っていたんです。その合間に書いた短いものが、あの二冊に入っています。
小池 水村さんの意外な面が出ていますね。
水村 そうなんです。『私小説 from left to right』は、本当は、理論的な小説なんですよね。見方によっては、自分のことは何も書いていないとも言える。ところが『日本語で読むということ』では、じかに自分を出している文章が入っているんです。しかも、目立たない雑誌に書いたりしているときは、おもいっきり、みたいに(笑)。
小池 パリ時代の話も、寅さんの色気のことも、ジョン・トラヴォルタのことも、いろいろとにかく新鮮なことがたくさんあったわけです、私にとって。
水村 だって、渥美清は色っぽいですよね、妙に。女の人がやたらに寄ってきたというのがよくわかる。あの顔で。
小池 そうですよねー、同感です。ヨーガン・レールの洋服についても面白い書き方をされていましたね、「洋服が布による人体の祝祭だとしたら、着物は人体による布の祝祭である」って。
水村 私は布が好きだから(笑)。
小池 バーネットのところでも、パッと布をかけるだけで世界が刷新されると。こういう形から『小公女』を読んだ人は初めてではないでしょうか。よく残っていらっしゃいますね、そういう部分が。
水村 あの場面は本当に好きです。パリで貧乏生活をしていたとき、部屋の隅の浴槽を隠す衝立があったんですけど、綺麗な布をかけて。いま、私の小さいベッドルームにも、壁に大きく布がかかっているんです。客間にも大きくかかっているし(笑)。
小池 すごく面白かったですよ。こういうエッセイに書いてらっしゃることを小説にお書きになる予定はないですか。
水村 歳をとるにつれて、エッセイ的なものに移って、最後には、もう投げ出したような思い出話というのを書きたいですね。断片だけで成り立っているような……。
小池 そうですよ。『本格小説』も、あるいは『私小説』もそうですが、理念のもとに、カチッと書いておられて、それはもちろん面白いのですけれども、私なんかは、水村さんのフワッと書いたような緩いものを、これからもっと読みたいですね。「理念」を外したようなものを。
水村 あー、嬉しい。私もそういう没理念のものを書きたい。今度、「読売新聞」でやるのは形のある小説ですけど、それでもう最後ですね。年齢的にも。あとは、もう、まとまりがないものをやりたい。日本舞踊なんかは、その歳、その歳の踊り方というのがあるんですね。歳をとったら、もう歳をとっているだけで許されるところもあって。日本文学の良さはそれなんですよ。英語じゃダメなの、すごく理詰めだから。
小池 なるほどねえ。
水村 日本文学の良さは、断片さえよければなんでもいいという闊達さ。
小池 う~ん、楽しみですね。
水村 本当に楽しみです。
(2009・5・22)
水村美苗・作家/小池昌代詩人・作家
『日本語が亡びるとき』
水村美苗著
詳細はこちら
ご注文方法はコチラ
トップに戻る
バックナンバー
- 第640号24年7月号
- 第639号24年6月号
- 第638号24年5月号
- 第637号24年4月号
- 第636号24年3月号
- 第635号24年2月号
- 第634号24年1月号
- 第633号23年12月号
- 第632号23年11月号
- 第631号23年10月号
- 第630号23年9月号
- 第629号23年8月号
- 第628号23年7月号
- 第627号23年6月号
- 第626号23年5月号
- 第625号23年4月号
- 第624号23年3月号
- 第623号23年2月号
- 第622号23年1月号
- 第621号22年12月号
- 第620号22年11月号
- 第619号22年10月号
- 第618号22年9月号
- 第617号22年8月号
- 第616号22年7月号
- 第615号22年6月号
- 第614号22年5月号
- 第613号22年4月号
- 第612号22年3月号
- 第611号22年2月号
- 第610号22年1月号
- 第609号21年12月号
- 第608号21年11月号
- 第607号21年10月号
- 第606号21年9月号
- 第605号21年8月号
- 第604号21年7月号
- 第603号21年6月号
- 第602号21年5月号
- 第601号21年4月号
- 第600号21年3月号
- 第599号21年2月号
- 第598号21年1月号
- 第597号20年12月号
- 第596号20年11月号
- 第595号20年10月号
- 第594号20年9月号
- 第593号20年8月号
- 第592号20年7月号
- 第591号20年6月号
- 第590号20年5月号
- 第589号20年4月号
- 第588号20年3月号
- 第587号20年2月号
- 第586号20年1月号
- 第585号19年12月号
- 第584号19年11月号
- 第583号19年10月号
- 第582号19年9月号
- 第581号19年8月号
- 第580号19年7月号
- 第579号19年6月号
- 第578号19年5月号
- 第577号19年4月号
- 第576号19年3月号
- 第575号19年2月号
- 第574号19年1月号
- 第573号18年12月号
- 第572号18年11月号
- 第571号18年10月号
- 第570号18年9月号
- 第569号18年8月号
- 第568号18年7月号
- 第567号18年6月号
- 第566号18年5月号
- 第565号18年4月号
- 第564号18年3月号
- 第564号18年3月号
- 第563号18年2月号
- 第562号18年1月号
- 第561号17年12月号
- 第560号17年11月号
- 第559号17年10月号
- 第558号17年9月号
- 第557号17年8月号
- 第556号17年7月号
- 第555号17年6月号
- 第554号17年5月号
- 第553号17年4月号
- 第552号17年3月号
- 第551号17年2月号
- 第550号17年1月号
- 第549号16年12月号
- 第548号16年11月号
- 第547号16年10月号
- 第582号19年9月号
- 第546号16年9月号
- 第545号16年8月号
- 第544号16年7月号
- 第543号16年6月号
- 第543号16年6月号
- 第542号16年5月号
- 第541号16年4月号
- 第540号16年3月号
- 第539号16年2月号
- 第538号16年1月号
- 第537号15年12月号
- 第536号15年11月号
- 第535号15年10月号
- 第534号15年9月号
- 第533号15年8月号
- 2019年8月号 No.581 目次はこちら
- 第532号15年7月号
- 第565号18年4月号
- 第531号15年6月号
- 第530号15年5月号
- 第529号15年4月号
- 第528号15年3月号
- 第527号15年2月号
- 第526号15年1月号
- 第525号14年12月号
- 第524号 14年11月号
- 第523号14年10月号
- 第522号14年9月号
- 第521号14年8月号
- 第520号14年7月号
- 第519号14年6月号
- 第518号14年5月号
- 第517号14年4月号
- 第516号14年3月号
- 第515号14年2月号
- 第514号14年1月号
- 第513号13年12月号
- 第512号13年11月号
- 第511号13年10月号
- 第510号13年9月号
- 第509号13年8月号
- 第509号13年8月号目次
- 第508号13年7月号
- 第507号13年6月号
- 第506号13年5月号
- 第505号13年4月号
- 第504号13年3月号
- 第503号13年2月号
- 第502号13年1月号
- 第501号12年12月号
- 第500号12年11月号
- 第499号12年10月号
- 第498号12年9月号
- 第497号12年8月号
- 第496号12年7月号
- 第543号16年6月号
- 第495号12年6月号
- 第494号12年5月号
- 第493号12年4月号
- 第492号12年3月号
- 第595号20年10月号
- 第491号12年2月号
- 第490号12年1月号
- 第489号11年12月号
- 第488号11年11月号
- 第487号11年10月号
- 第486号11年9月号
- 第485号11年8月号
- 第484号11年7月号
- 第483号11年6月号
- 第482号11年5月号
- 第480号11年4月号
- 第479号11年3月号
- 第478号11年2月号
- 第478号11年1月号
- 第477号10年12月号
- 第476号10年11月号
- 第475号10年10月号
- 第474号10年9月号
- 第473号10年8月号
- 第472号10年7月号
- 第471号10年6月号
- 第470号10年5月号
- 第469号10年4月号
- 第468号10年3月号
- 第467号10年2月号
- 第466号10年1月号
- 第465号09年12月号
- 第464号09年11月号
- 第463号09年10月号
- 第462号09年9月号
- 第461号09年8月号
- 第460号09年7月号
- 第459号09年6月号
- 第512号13年12月号
- 第456号09年3月号
- 第458号09年5月号
- 第455号09年2月号
- 第457号09年4月号
- 第548号16年11月号
- 第548号16年11月号
- 第454号09年1月号
- 第520号14年7月号
- 対談
- 第509号13年6月号
- 第524号14年11月号
- 第548号16年11月号
- 第565号18年4月号
以前のPRちくま
「ちくま」購読料は1年分1,100円(税込・送料込)です。複数年のお申し込みも最長5年まで承ります。 ご希望の方は、下記のボタンを押すと表示される入力フォームにてお名前とご住所を送信して下さい。見本誌と申込用紙(郵便振替)を送らせていただきます。
電話、ファクスでお申込みの際は下記までお願いいたします。
-
受付時間 月〜金 9時15分〜17時15分
〒111-8755 東京都台東区蔵前2-5-3