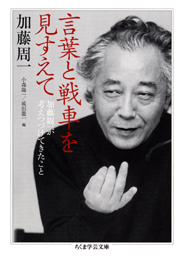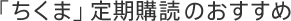鼎談 加藤周一が考えつづけてきたこと
大江健三郎 作家
小森陽一 東京大学大学院教授
成田龍一 日本女子大学教授
加藤周一さんの一周忌にあたり、第61回紀伊國屋サザンセミナー「加藤周一とともに――いま、『日本文学史序説』を語る」が開かれ、大江健三郎さんの基調講演と、小森陽一さん・成田龍一さんを交えた鼎談が行われました。(二〇〇九年十二月十四日)
大江 この人は自分の時代の大きい見事な人だと思ってきた方の訃報に接して、若い時は悲しむだけだった。それが年をとってきて私が経験するのは、驚きに打たれて、ほとんど恐怖するということです。わずかな数の友人や家族とその人のことを話す。「新約聖書・ルカ書」の終り近いところにある通り、「暗い憂鬱な顔をして」。あるいは一人「暗い憂鬱な顔をして」その人のことを思っている。
ところが時が経つと、あのような人に会え、お話を聞くことができたことを、「あの人の言葉を聞く間、我々の心は燃え立ったではないか」(これも「ルカ書」の最後に出てくる言葉です)と考える。
加藤周一さんが亡くなられたときに経験したのは、まさにこの通りでした。
私は新聞に加藤さんへの追悼文のようなものを書きました。そこで加藤さんを「大知識人」と呼んだことが、真面目な雑誌で批判された。それをアメリカのやはり古い友人にグチる手紙を書いていて、さて「大知識人」にあたる英語があるのだろうかと考えました。辞書の例文を見るとsome important figures in European intellectual lifeというのがあった。「大知識人」という表現は単独で存在するのではなく、たとえばヨーロッパの知識人の中に、あるとても重要な人々がいて、その一人が彼だ、というような言い方をするらしい。
そこで私は日本にインテリジェントな人たちの生活というものがあるだろうかと考え、あるとしたら、そこで大切な人物とはだれだろうか、と考え進んで、確実に、加藤さんは日本にありえたインテレクチャルライフのなかのもっとも大切な一人だと思いました。
そうした知識人のことは、『日本文学史序説』に読み取ることができます。
日本最初の知識人――紀貫之と菅原道真
大江 この本で「知識人」という言葉が初めて使われるのは八世紀の山上憶良についてです。大陸文学の教養を持った憶良型の知識人官僚は、しかし単独で、孤立していた。百年たち、そういう人がようやく群を成して現れ始めた。これが九世紀の社会的な特徴の一つだと分析されています。
そのようにして現れてきた知識人に二つの型がある。一つは、藤原氏の一派が権力を独占したために、政治的に没落した貴族のなかから現れた知識人。政治的権力の中心から遠ざけられた紀氏からの、代表的な人が紀貫之だというのです。もう一つは、上流貴族ではなく、比較的下級の儒家から出て、官僚として高位に昇った人物で、祖父の代からの儒者で右大臣となった菅原道真がその典型、と書かれています。
紀貫之は、「万葉集」以後の秀れた歌を全日本の規模で「古今集」に編纂した、きわめて知的な人。「土佐日記」という旅行記も書きました。
八~九世紀の僧、慈覚大師円仁のことも、加藤さんは最初の優れた知識人たちの一人としますが、円仁が書いた「入唐求法巡礼行記」という旅行記には、旅で遭った民衆の苦しい人生が描かれている。しかし紀貫之は、実際の生活のことは書いていない。漢文で書く円仁には、そういうリアリズムが可能だったけれども、紀貫之は、貴族が集まって歌をつくる会合を主宰し、その一人としての旅行記を書けても、民衆の生活を見極めて書くということはなかった。それは日本語と中国語との言語の違いでもあるし、だいたい日本のインテリは、まずリアリズムでないところから出てきたのだ、と加藤さんはいいます。
一方、菅原道真は中国語で優れた詩をつくったわけですが、つまりは彼の中国語の作品を鑑賞し、理解することのできる知識人グループが既にできていたのだという。それは、紀貫之の日本語の歌を受け止めるグループと同じように、九世紀初めのインテリ集団の出現を意味しています。
そこには共通点も相違点もあると加藤さんはいう。「月は鏡のように澄んでいるが、罪の無実を明かしてはくれない、風は刀のように鋭いが、かなしみを破らない、見るもの聞くものみじめであり、此の秋はただわが身の秋となった」、こういう意味の漢詩を、菅原道真は自分の経験に即してつくり出した。他方、紀貫之が「古今集」に択んだ歌には、「月みればちぢにものこそかなしけれ わが身ひとつの秋にはあらねど」(大江千里)というのがある。
状況は対照的です。一方は、政治的に追い詰められて地方に流されたインテリがつくった歌。他方は、宮廷の歌人が歌合で詠ったもの。中国語と日本語という違いもある。にもかかわらず、同時代の詩的表現に明らかに相通うところがあります。
八世紀までは、たとえば「懐風藻」の漢詩と「万葉集」の日本語の歌とを比べても、こうした共通な感情、共通の表現はなかった。ところが九世紀を経て十世紀初めになると、宮廷歌人の大江千里と、追い詰められた官僚で漢詩を書く菅原道真とのあいだに、同時代の人間としての同じ内面が感じられる。こういう作品をつくる者らが知識人であり、一つの時代に、違った教養や職業の立場を持ちながら、ある文化的なものを共有できるということが知識人の条件であると、加藤さんは示しているわけです。
百年前の知識人――石川啄木
大江 では近代に特有の知識人とはだれか。
子規、露伴、漱石、鴎外らも、明治維新、日清・日露戦争という時代の刻印を大きく受けた知識人たちですが、加藤さんが重要視するのはその次の世代、維新から二つの戦争までの時代に生まれ青年になって、不安かつ不幸な時代状況をもろに引き受けた文学者、端的に言えば石川啄木です。
一八八五年に生まれて一九一二年に死ぬ石川啄木は、日清戦争に至る社会の変動を知っている。そして二十代初めに文学者として活動し始めるとたちまち、大きな時代の壁にぶつかってしまった。日露戦争後から十月革命前という、一九一〇年前後の時代の特徴を、もっとも明瞭に書いたのが石川啄木だと加藤さんは考えています。
今から百年ほど前の一九〇七、〇八年には、大学を卒業しても就職がないという、現在の日本と同じようなことが起きていた。石川啄木は、そのことを批判して、「時代閉塞の現状」を書きました。時代が閉じていて若い人が希望を持てない。しかも一九〇五年に日露戦争が終わって新しい経済状況になり、国際関係が進展して、日本では、国家自体が社会を閉じさせるまでの大きな権力をコントロールするようになった。しかし、その制御のまま若者は閉じてはいけない、そこを自由に突き破っていく力を、言葉を、行動を起こさなければいけない、と啄木は書いたわけです。
若者の心をなぐさめる美しい歌をつくりながら、もう一方で大逆事件の幸徳秋水に、すなわち「テロリスト」に共感するものが自分のなかにあると歌うような、そういう知識人の文学者がここで現れた。これが加藤さんの着眼点です。
新聞社にいた啄木は、幸徳秋水が獄中から弁護士に書いた手紙を入手して書き写します。クロポトキンの本を引用しつつ、自分たちアナーキストは天皇家を攻撃しようとしたものではない、と書いた手紙です。啄木はそこに自分の感想を書き加え、クロポトキンの英語の文章も写しています。
外国語を勉強して新しい思想を学ばなければいけないと考えていた、当時の生真面目で不安な青年に、加藤さんは大きな関心を寄せています。啄木は時代の病である肺結核になって、貧しさから死に、家族も滅びてしまう。しかし、違う社会状況であったならばどうなっていたか。
その百年前、ハインリッヒ・ハイネは、同じような閉塞状況のプロシアから逃げ出し得た。ヨーロッパ文化の中心地パリで亡命生活をしつつ、啄木と同じように美しい詩をつくり、激しい政治的言論を展開するジャーナリストとなりました。
もしも充分なお金があって、満足な教育を受け、きちんとした生活ができ、日本が「孤立した島国」でなくて外国に亡命できるような状況だったら、啄木は日本のハイネとして、全く新しい文化状況をつくっただろう、そうした文学者が確実に誕生したはず、と加藤さんは想像します。
啄木が苦しんだ時代が、つい百年前のことにすぎないのを、いまの若いみなさんに考えていただきたいと思います。百年前のことが、いま再現しつつあるのです。
啄木から百年後の現在、新しい閉塞状態がある。そのちょうど中間の時期が一九四五年頃です。戦争に敗けた後につくり上げられた日本には、新しい文化への動きがありました。時代閉塞を打ち破るような可能性があの時代にはあったのだというのが、加藤さんが証言していられることです。
外国語を読み、外国人と議論し、協同の仕事ができる人を、加藤さんは高く評価されました。自分の研究をし、海外での経験も積んで、普遍性を持ったところで世界的に活動できる人こそが知識人なのだと。だから若い人たちは外国に行ってきちんと議論できる者になる必要がある、少なくともそれが知識人となるための第一歩なのだと、自らの人生でそれを証明されました。
かれの原則の一つに、文学作品を高く評価するという態度があります。一人の女性歌人が詠んだ歌、一人の農村の老俳人がつくった俳句を、つねに丹念に読み解いていく。近松門左衛門の浄瑠璃についても、井原西鶴の小説についてもそうです。そういう文学作品には、同時代を生きた人たちの共有する感情があり、それを読み取ることが時代を読み取ること、社会を読み取ること、日本語の実質を読み取ることだ、という確信を具体的に示されました。
『日本文学史序説』について、有名な外国人の文学研究者が「優れた作品だが文化史であって文学史とは言えないのではないか」と批判しました。しかし、それは間違っている。加藤さんのように一つ一つの作品を文学的なテキストとして深く読み取る文化史家・文学史家はいなかった。具体的な読みの上に立った、日本社会、日本文化、日本の歴史についての結論が、この本にはあらゆるページに満ちている。知識人とはどういう条件を持つ者なのか、加藤さんは厳格にかつ寛大に様ざまなタイプを取り上げ、かれらの作品をこのように重んじているのです。
「日本」「文学」「歴史」をどう捉えるか
小森 『日本文学史序説』は、大江さんのお話のように、日本史であると同時に文学史です。政治と文学は対立項ではなく、まさに、最も政治的であることが最も文学的であり、最も文学的であることが最も政治的である。そのように生きた人たちの表現を深く読み取るという、この本の大事な方法論が明らかになってきました。
成田 『日本文学史序説』では、文学という形で構えをつくるけれども、同時に政治の問題を考えている。そして、文学作品を定義しているのは時代時代の状況です。いま「日本」も「文学」も「歴史」も、ある固定的な枠組みで捉えられていますが、加藤さんはその枠組みを規定するものを再検討した。そしてその固定化をつくりあげたのが、近代化の過程における国学と西洋だと考えていました。国学と西洋によって切り詰められた「日本」「文学」「歴史」を書き換えようとしたのだと思います。
大江 「国学と西洋によって」と言い切るのは単純化しすぎではないでしょうか。
近世の始め、徳川政府が、日本が国家としてやっていくための思想としたのが儒学でした。国家の思想としての儒学を修める、権力を持った学者たちがいたわけです。
しかしその儒学にも、時代に沿って変化が生じてきます。例えば、朱子学が文科省の指導要領みたいなものとすれば、それに対して、荻生徂徠のように違った古典の読み取りを考える人がいた。加藤さんは武士の陽明学と捉えています。それは政府の思想とはまた別の影響を知識人たちに与え、日本の思想を揺り動かした。
一方で民衆のあいだには、近世後半別の陽明学が現れた。農民の現実感覚に即した新しい陽明学で、二宮尊徳、安藤昌益、大塩平八郎などの思想です。石田梅岩の心学などは六十数カ所に学校ができるほどの常民の学問の流れとなりました。
そういう二つ、あるいは三つの中国の学問があり、対するものとして国学が現れ、国学者、たとえば本居宣長らの大きな仕事があった。したがって、国学ということを考える場合、日本の複数の儒学、複数の漢学がどのように政府と民衆を刺激したかを考えなければなりません。
また、蘭学を学んだ人もいれば、それをもっとアメリカの学問に近づけた福澤諭吉のような人もいる、緒方洪庵のように医学を行った人もいる。彼らがこぞって明治維新に至る学問のさまざまな流れをつくったのであって、そうした多様な動きがあったのを、「国学と西洋」と単純化することはできないのではないかと思います。
加藤さんは、歴史を考えるうえで文学作品が第一資料として有効だと固く信じていました。歴史のなかに生きた人間の証拠として文学作品を読み解き、その視点から、江戸時代から明治維新に至る展開をうまく広く、魅力的に捉えている。あわせて富永仲基のように、漢学をしつつ、大坂の商人のための学問所で学び、そこでも反逆して困難な人生を歩んだ革命的な学者に、強い関心を寄せられました。
しかし維新後、日清・日露戦争に至ると、国家そのものが一つのはっきりした思想と実践力を持ち始める。一九一〇年に大逆事件と日韓併合が起こります。加藤さんの分析では、日韓併合はアジアにおける日本の侵略的膨張の時代の象徴です。その前に、国内の安全確保のために大逆事件をでっち上げ、日本を天皇の国家として確実に捉え直した。そして米騒動が一九一八年、治安維持法制定が二五年。すなわち一九一〇年からの十年間に日本とアジアとの関係、国内の体制、天皇制の力、民衆の表現の自由の様相が、はっきりと変わったのです。
この時代、文学も明らかに変わった。この時代の変化を加藤さんがどう捉えたかを考えるべきでしょう。
成田 『日本文学史序説』では、時代は世紀割りで考えられています。明治維新後が近代だという形で歴史を切断するのではなく、複数の儒学なり漢学なり国学なりがあり、一方で西洋からさまざまな概念や影響が入ってきて、そのなかから明治維新に向かう力が出てくる。明治維新を、十九世紀という時代のなかでの営みとして捉える。そのように歴史を把握する構想力を、加藤さんは『日本文学史序説』で示しています。
そこには、歴史の断絶説をとっていた従来の文学史の叙述、あるいは歴史学研究に対する厳しい批判が含まれています。
歴史の連続説をとることによって何が見えてくるか。それが日露戦争後の社会、つまり二十世紀とは「日本」「文学」「歴史」にとって何だったのかという問題です。日本の二十世紀は日露戦争とともに明けたわけですが、その日露戦争の結果、国内の治安強化と、対外的な進出、すなわちまさに二十世紀の特徴というものが出てくる。
また、十九世紀、二十世紀と世紀で捉えた瞬間に、基準が一気に世界的なものになる。そのときイギリスは、アメリカは、何をしていたのか。中国は、あるいは東アジアの状況はどうだったか。そういう問題が見えてきます。
小森 世界史との対応関係のなかで日本史をきちんと読み直すことを可能にした、つまりいままでの、日本をめぐる歴史認識のあり方全体を組み替えたといえるわけです。
一九四五年の体験を核に
小森 石田梅岩のお話が出ましたが、梅岩は、町人に対して現世を生き抜く方法を提示する一方で、彼自身の自然観や宇宙観は全くそれとは違い、根源的にヘーゲル的でさえあった。つまり、一人の思想家の営みのなかに極めて異質な、果たしてなぜこれが一人の人間の中に同居しているのかと思われるような特質を読み取り、見抜いていくというスリリングなところが『日本文学史序説』にはあります。こうした加藤さんの着眼点はどこから来るのでしょう。
大江 加藤さんの視点の根には明らかに一九四五年の経験があります。
小森さんと成田さんが編まれた『言葉と戦車を見すえて』はじつにすばらしい本ですが、その軸のひとつ「言葉と戦車」は、チェコスロバキアの危機に際して書かれました。一九六八~六九年、言論の自由のない社会主義国チェコの国民が、民主主義としての社会主義をつくろうとした運動を成功させた。悲劇がそれに続いた。直前にプラハを訪れ、その後をウィーンで見ながら、加藤さんは何を考えていたか。
プラハの街から、思いを遠く故国に寄せなかったわけではない。しかしその故国は、一九六八年夏の東京ではなく、四五年秋の東京であった。そこにも検閲があり、いろいろな不自由もあった。しかしあのときは新聞・放送の大衆報道機関を通じて、政治体制の根本的な変革を公然と論じることもできた。四五年秋には、日本の古代史の事実を(これは天皇制を含みますが)、初めて公然と語ることもできた。希望や計画や、胸にたまる思い、新しいと信じる考えにあふれていた、と加藤さんは書きました。
新しい歴史の出発点として一九四五年を考え、そこから六八年に至り、もう一度日本文学、日本近・現代史、日本全体の歴史、さらにはアジアの歴史を考え直してみる。そのきっかけがチェコで生じた。そこで一九四五年の経験を思い出し、それに励まされる、と加藤さんは書きました。つまり一人の人間・加藤周一が考えたことを中心に、世界の小さな国の小さな街プラハと、東洋の小さな国の小さな街東京を結ぼうではないか、社会主義の未来についてもう一つ別の意見を出そうではないか、と。
加藤さんは、東京での一九四五年の希望に、真剣に向き合い続けた人です。チェコで新しい運動が起これば、強い共感を寄せながら、日本のことも考える、こういう人を誇らしい日本人、世界的な人、本当の知識人だと思います。私はその人を記憶し続けたい。新しい加藤周一が次つぎ現れる、まず若い加藤周一読者が十万人生じるのが、私の希望です。
小森 いまのお話には、非常に感慨深いものがあります。私は一九六五年までプラハのソ連大使館付属八年制学校に通い、日本に帰国後あの事件が起きました。ソ連の教育を受けチェコの友達と遊んでいたわけですから、私の半分が、もう半分に戦車を乗り入れ侵略したような状態だったのです。
そのときの自分の分裂をどう考えたらいいのか。十五歳の私は初めて自分でお金を出して、岩波書店の『世界』という雑誌を買って読みました。そして「言葉と戦車のように考えれば、自分はこの分裂から立ち直れる」という手引をいただいた。
のちにご一緒した北京での講演で加藤さんは、医師だった自分の空襲体験、血液学の専門家として原爆の被害の調査に行かされた経験、そういう状況のなかで、意識的に文学者になることを選択しようと思ったと、中国の学生たちに語っていました。
加藤さんは、戦争に協力したり、それに乗っかっていったりした知識人を非常に厳しく批判しました。その一つが、『言葉と戦車を見すえて』に収録した「知識人の任務」という文章だと思います。
大江 戦争中、日本に言論の自由は何もなかった。そして敗けた。加藤さんは四七年に、人民のなかに入って戦争中のような間違いを起こさないように行動するのが我々知識人の仕事だ、と書きました。それが、「渡辺一夫先生に捧げる」という献辞がある、「知識人の任務」です。
成田 『言葉と戦車を見すえて』は、「言葉と戦車」を軸に、加藤さんの生涯にわたる持論を「知識人論」として整理してみようという意図で編んだものです。加藤さんが問題にしつづけたのは、やはり知識人についてであったと思います。知識人の責任とは何か、知識人として生きるとはいかなることなのか。加藤さんの知識人の責任論は、はっきりと戦争体験に根ざしています。
さらに、「高みの見物」という文章のなかで、知識人たるもの分析をし、正確な認識を持つのは当然であるが、しかしそれが高みの見物であってはいけない、実践的に役立つ知識というものを考えなければいけないのだ、ということを書いています。
加藤さんの文章は、分析と実践という二重の複眼的な視線で読む必要があります。『日本文学史序説』も日本文学史でありつつ、加藤さんの実践としても捉えることができる。そうした複眼的な懐の深さがますます必要な時代です。単線的に二者択一で考えていては、凄まじく変化しているこの世界の状況に対応できない。そのことを加藤さんの仕事から学ぶべきでしょう。
小森 大江さん、実は『日本文学史序説』の最後は大江さんで終わっているんですね。
大江 私が読んだのは、最初の版で、そこに私は出ない、出るのは文庫版(笑)。まず私や井上ひさしは指針をあたえられた。私は、渡辺一夫という、一九四五年にはっきり出直すことを決心した知識人を裏切るまい、その渡辺さんをまっすぐ継がれる加藤周一の考え方に結びつきたいと考えて、文学をやってきました。
加藤さんは「知識人の任務」で、大きな戦争に反対を表明せず、敗北までついて行った無力な日本の知識人を救い直す道はあるかと考える。そして、人民のなかに己を投じ、人民とともに再び立ち上がるほかに道があり得るだろうかと問いかけています。こういう若い、激しい書き方は、加藤さんの仕事全体の流れを見ると、あるいは少し馴染まないかもしれません。
しかし人間は、非常に調子の高い言葉で語るときもあるし、深く沈み込んで、それこそ「暗鬱な顔」で考えるときもある。その両者を一貫することをねがって、まともな人間は生きていく。
加藤さんは、八十代になって「九条の会」をつくる中心となり力を注がれた。私も加藤さんと一緒に働けた。加藤さんの文章を読み、直接に話を聞いて心が燃え立ったことを、私は伝えつづけるでしょう。
加藤周一の本
『日本文学史序説』 詳細

ご注文方法はコチラ
トップに戻る
バックナンバー
- 第640号24年7月号
- 第639号24年6月号
- 第638号24年5月号
- 第637号24年4月号
- 第636号24年3月号
- 第635号24年2月号
- 第634号24年1月号
- 第633号23年12月号
- 第632号23年11月号
- 第631号23年10月号
- 第630号23年9月号
- 第629号23年8月号
- 第628号23年7月号
- 第627号23年6月号
- 第626号23年5月号
- 第625号23年4月号
- 第624号23年3月号
- 第623号23年2月号
- 第622号23年1月号
- 第621号22年12月号
- 第620号22年11月号
- 第619号22年10月号
- 第618号22年9月号
- 第617号22年8月号
- 第616号22年7月号
- 第615号22年6月号
- 第614号22年5月号
- 第613号22年4月号
- 第612号22年3月号
- 第611号22年2月号
- 第610号22年1月号
- 第609号21年12月号
- 第608号21年11月号
- 第607号21年10月号
- 第606号21年9月号
- 第605号21年8月号
- 第604号21年7月号
- 第603号21年6月号
- 第602号21年5月号
- 第601号21年4月号
- 第600号21年3月号
- 第599号21年2月号
- 第598号21年1月号
- 第597号20年12月号
- 第596号20年11月号
- 第595号20年10月号
- 第594号20年9月号
- 第593号20年8月号
- 第592号20年7月号
- 第591号20年6月号
- 第590号20年5月号
- 第589号20年4月号
- 第588号20年3月号
- 第587号20年2月号
- 第586号20年1月号
- 第585号19年12月号
- 第584号19年11月号
- 第583号19年10月号
- 第582号19年9月号
- 第581号19年8月号
- 第580号19年7月号
- 第579号19年6月号
- 第578号19年5月号
- 第577号19年4月号
- 第576号19年3月号
- 第575号19年2月号
- 第574号19年1月号
- 第573号18年12月号
- 第572号18年11月号
- 第571号18年10月号
- 第570号18年9月号
- 第569号18年8月号
- 第568号18年7月号
- 第567号18年6月号
- 第566号18年5月号
- 第565号18年4月号
- 第564号18年3月号
- 第564号18年3月号
- 第563号18年2月号
- 第562号18年1月号
- 第561号17年12月号
- 第560号17年11月号
- 第559号17年10月号
- 第558号17年9月号
- 第557号17年8月号
- 第556号17年7月号
- 第555号17年6月号
- 第554号17年5月号
- 第553号17年4月号
- 第552号17年3月号
- 第551号17年2月号
- 第550号17年1月号
- 第549号16年12月号
- 第548号16年11月号
- 第547号16年10月号
- 第582号19年9月号
- 第546号16年9月号
- 第545号16年8月号
- 第544号16年7月号
- 第543号16年6月号
- 第543号16年6月号
- 第542号16年5月号
- 第541号16年4月号
- 第540号16年3月号
- 第539号16年2月号
- 第538号16年1月号
- 第537号15年12月号
- 第536号15年11月号
- 第535号15年10月号
- 第534号15年9月号
- 第533号15年8月号
- 2019年8月号 No.581 目次はこちら
- 第532号15年7月号
- 第565号18年4月号
- 第531号15年6月号
- 第530号15年5月号
- 第529号15年4月号
- 第528号15年3月号
- 第527号15年2月号
- 第526号15年1月号
- 第525号14年12月号
- 第524号 14年11月号
- 第523号14年10月号
- 第522号14年9月号
- 第521号14年8月号
- 第520号14年7月号
- 第519号14年6月号
- 第518号14年5月号
- 第517号14年4月号
- 第516号14年3月号
- 第515号14年2月号
- 第514号14年1月号
- 第513号13年12月号
- 第512号13年11月号
- 第511号13年10月号
- 第510号13年9月号
- 第509号13年8月号
- 第509号13年8月号目次
- 第508号13年7月号
- 第507号13年6月号
- 第506号13年5月号
- 第505号13年4月号
- 第504号13年3月号
- 第503号13年2月号
- 第502号13年1月号
- 第501号12年12月号
- 第500号12年11月号
- 第499号12年10月号
- 第498号12年9月号
- 第497号12年8月号
- 第496号12年7月号
- 第543号16年6月号
- 第495号12年6月号
- 第494号12年5月号
- 第493号12年4月号
- 第492号12年3月号
- 第595号20年10月号
- 第491号12年2月号
- 第490号12年1月号
- 第489号11年12月号
- 第488号11年11月号
- 第487号11年10月号
- 第486号11年9月号
- 第485号11年8月号
- 第484号11年7月号
- 第483号11年6月号
- 第482号11年5月号
- 第480号11年4月号
- 第479号11年3月号
- 第478号11年2月号
- 第478号11年1月号
- 第477号10年12月号
- 第476号10年11月号
- 第475号10年10月号
- 第474号10年9月号
- 第473号10年8月号
- 第472号10年7月号
- 第471号10年6月号
- 第470号10年5月号
- 第469号10年4月号
- 第468号10年3月号
- 第467号10年2月号
- 第466号10年1月号
- 第465号09年12月号
- 第464号09年11月号
- 第463号09年10月号
- 第462号09年9月号
- 第461号09年8月号
- 第460号09年7月号
- 第459号09年6月号
- 第512号13年12月号
- 第456号09年3月号
- 第458号09年5月号
- 第455号09年2月号
- 第457号09年4月号
- 第548号16年11月号
- 第548号16年11月号
- 第454号09年1月号
- 第520号14年7月号
- 対談
- 第509号13年6月号
- 第524号14年11月号
- 第548号16年11月号
- 第565号18年4月号
以前のPRちくま
「ちくま」購読料は1年分1,100円(税込・送料込)です。複数年のお申し込みも最長5年まで承ります。 ご希望の方は、下記のボタンを押すと表示される入力フォームにてお名前とご住所を送信して下さい。見本誌と申込用紙(郵便振替)を送らせていただきます。
電話、ファクスでお申込みの際は下記までお願いいたします。
-
受付時間 月〜金 9時15分〜17時15分
〒111-8755 東京都台東区蔵前2-5-3