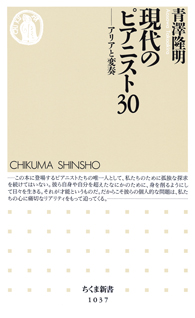筑摩書房 INFORMATION&TOPICS
15.02.16
ピアニスト「アンデルシェフスキ」、インタビュー(聞き手:青澤隆明氏)
09.02.12
津村記久子さんインタビュー
祝!芥川賞受賞!

2005年、太宰治賞でデビューした津村記久子さんが、この度、「ポトスライムの舟」(「群像」)で第140回芥川賞を受賞されました。そこで、デビューから今日まで、どういう思いで、どういうペースで小説を書きつがれてきたのか、聞いてみました。
…………………………………………………………………………………………………………
――先日、デビュー作の『君は永遠にそいつらより若い』を重版しましたが、あらためて読んでみてどうでしたか? 結局とくに直さずそのまま重版ということになりましたが。
あれはあれで、あの緩さとか細かさでいいなって思ったので。『太宰賞2005』から単行本にする段階で、高井有一先生に、ここしょうもないなーって言われたところは切ったんですよ。それでまあいいかなと。
――温水ゆかりさんが「PR誌ちくま」の書評で、「一作ごとに進化を遂げている」と書かれていましたが、ご自分ではどうですか? 私は進化したなって思います?
うーん。でも、考えるようにはなりましたね、いろいろ。いちばんその基礎になったんが「群像」の最初の30枚(『カソウスキの行方』収録の「花婿のハムラビ法典」)です。短編を書いたことがなかったので、すっごいむずかしかったんで。それからだいぶ組み立ててやるようにはなったんです。
◆
年に2本長編を書こう、3年はがんばろうと決めていた
――太宰治賞受賞は4年前でしたよね。
そうです。27のときです。
――その頃は、というか今もですが、会社に行きながら書いていたんですよね。
年に2本長編を書くって決めて、毎日書いてました。何月何日までに何枚書くとしたら、日割りにして1日に何枚やけど、でも土日を休みたかったら、何枚とか、ずーっと考えて。
――それはいつ頃から?
26からです。3年と思ってました。29までやろうと思ってて。まあ、みんな3年て言うから私も3年でというだけなんですけどね。
――それで27で受賞。早いですよね。応募は何回目だったんですか?
2回目です。最初は「小説すばる」で、それが三次選考まで残って、「1176中の12番」になったわけです。そのことをたぶんね、私、芥川賞をとったことより誇らしげに話すと思うんですけど。(笑)大学生のときに書いたものを、26のときにリライトして出したら、残ったんですよ。このときと、太宰賞の最終選考に残りましたという連絡を筑摩書房さんからもらったときが、作家生活でいちばん嬉しかったことじゃないかと思います。
――いちばんはじめに認められた瞬間ですものね。
そうです、そうです。
――でも「小説すばる」で三次選考まで残ったんだから、太宰賞はけっこう行けるかな、という気分だったでしょう?
いやーそんな気分、なかったですけど。まあ、そんなあかんことはないやろ、みたいな。ただ、一次落ちはふつうにあるやろと思ってました。……私そのあとに、年2本ということは下半期も書いていたわけで、下半期のものを別のところに応募して、一次通過しませんでしたよ。
――え? ほんとうに?
なんやこれって思って。それが7月くらい。
――はじめて知りました。それって応募したのはいつですか?
太宰賞の最終選考に残った頃ですね。残ったといってもそんな、入賞することもないやろ、ということもあったし。だからやっぱり出しとこ、と思って。
――受賞が決まったのが5月で、授賞式が6月で、そして7月に一次選考に落ちた。(笑)
たぶんそのショックで、なんかなんにも書いてなかったのかもしれません。賞をとってからは、とくに仕事のない時期が続いてて。
◆
仕事が来た! それもまず「群像」から
――編集者だってまず作品を読まなきゃいけないし、すぐのご連絡はちょっと。
7月8月とかずっと、なんも仕事なくて、頼まれるままに大学のエッセイとか書いていて。で、9月に「群像」がエッセイ書きませんって言ってきはって。うわーうそー、来たー、うそやでーって。「群像」ですからね、講談社の。
――ほかにありません。(笑)
えらいびっくりしました。そこからバタバタ仕事をもらい始めるんですよ。ぜんぶ覚えてるんです。10月に上京して営業旅行に行って……といっても、筑摩書房さんと講談社さんに行くだけなんですけどね。そこで「群像」で短編書きませんかってなった。仕事やーって思って。で、12月の頭ぐらいに「小説すばる」からインタビューを受けて、そのちょっと後ぐらいに筑摩さんからウェブの連載しませんかって来た。すごいすごい、仕事やーって。それからもうちょっとしてからまた「小説すばる」から小説書きませんかって言われて。もうそれでいいと思ってました。
――それでいいって。(笑)あとから宿題がいっぱい来たってことじゃないですか。
なにをしてたんですかね、その最初の5、6、7、8は。12月〆切で30枚ぐらいの仕事が来てただけやったから、なんの仕事も持っていない頃に長編を書こうって思って。筑摩の担当さんも見せたら邪慳にはせえへんやろ、みたいな。で、2本書いて1本ボツでも落ちこまへんような心構えで考えたんが、『ミュージック・ブレス・ユー!!』なんです、じつを言うと。賞とっていちばん最初に考えたんがあれやったんです。
――あの作品で野間文芸新人賞を受賞。受賞インタビューでも、そう言ってましたよね。でもその頃、デビュー作の本作りがあったはずですが。
ああ、そうそう、ゲラ見てましたね。見てたけど、でもあのときの見方って、ほんとに見てたんですかっていうぐらいの感じやったですしね。ファックスも持ってなかったから、電話でやりとりして。これはどうしますか、これはどうしますか、ってずっと聞かれて、担当さん嫌になってきたんか、ファックス買ったほうがいいと思いますよって言われて。(笑)賞金で。……買いましたよ、ファックス。
――いいですねー初々しくて。
ほんま、なにしてたんやろ。
◆
長編か短編か、純文学かエンターテインメントか
――年に2本長編ということは、短編はまったく?
一回も考えたことがなかったです。だから「群像」から頼まれたとき、本を買いました。阿刀田高さんの『短編小説のレシピ』。
――泥縄ですねー。
結局読まなかったんですけどね。あとで読みました、書き終わってから。面白かったです。
――この間、「anan」のインタビューで推薦していた3冊の本はどれも短編小説集でしたよね。読むのは短編がお好きなんですか。
あれは、冬場にちょっとした時間に楽に読める本、というコンセプトで選んだので。ほんまに重い長編も好きですし、両方好きです。
――ぜったい長編!と思っていたわけではなく、たまたま短編が頭になかったと。
なかったですね。応募したい賞がエンターテインメントのものが多くて、そうすると基本的に150枚とか受け付けなくて、300枚以上とかなんですよ。だから長編になってて。松本清張賞とか600枚とかでしょ。太宰賞がいちばん中間の枚数なんです。「文學界」は100枚、「群像」は250枚、「小説すばる」は300枚からで、太宰賞は300枚。
――じゃあ太宰賞を選んでくれたのは枚数の問題なんですね。(笑)
枚数もありますし、なんかその、ちょうど出したいときに太宰賞の〆切が近かったというのがあって、ああ筑摩やと思って出した、というか。いまでも、新人賞の広告見ますよ。ここいいなあ、とか。
――もう応募できないですよ。
ねえ。でもなんかあったらこまるし。さすがにね、ここのところ見なくなりましたが、見なくなったのは去年ぐらいからですよ。仕事いつなくなるかわからへんし。そしたらまた、応募するしかないじゃないですか。新人からやりなおし、かなあと。いろいろと控えてましたよ、リストに、鮎川哲也賞は何枚、とか。(笑)
――最初が「小説すばる」ですし、純文学よりもエンタメのイメージだったんですね。
それこそ、そんな深遠なテーマを持っていないので。エンタメのほうが読むのも好きですし。というか、そういうジャンル分けがあることすら、あんまり考えたことがなかったです。海外文学ばっかり読んでたから。SFかミステリーかみたいなのは分かるんですけど、あと、白水uブックスとか読んでました。ああいうのがいったいどういうものかわからんと、ただ小説として読んでたんで。
――文芸雑誌は?
読んでなかったです。途中で終わるしなあと思って。連載は買いつづけんとだめですからね。
――でも「芥川賞」。純文のど真ん中になっちゃいましたね。
びっくりですよね。でもまあ、いただく仕事全部が純文というわけではないですからね。純文とエンタメと、だいたい交互ぐらいに来ているんですよ。
――そのことは別に、ご自分のなかでは矛盾なく? 雑誌によって書くものは変えてるんですか?
ある程度変えますけど、雑誌と言うより、編集者さんによって変えてますね。たとえば「野性時代」の担当さんとかだったら、男の人だから、男の子の話を書いたときに、この人のところで通ったら、まあ大丈夫やろ、そんなに嘘くさいわけでもないやろ、変やったら訂正してくれるやろし、とか。
◆
ちょっと笑える部分は入れたい
――この担当さんだったら、ちょっとエンタメに近いものにしようとか、そんなふうにも考えますか?
いや、それはほぼないような。最近ほんと、なくなりましたね。「カソウスキの行方」ぐらいから区別しなくなりました。しないほうがいいってなって。
――それはどうしてですか?
「十二月の窓辺」という、「ポトスライムの舟」といっしょに今度、単行本に収録される「群像」にのせた小説があって、それは私は純文学やと思って書いた小説なんです。モラルハラスメントの話なんですけど、あまり受けんかったような気がして(笑)。
――読者に?
いや、担当さんに。その前に書いた「花婿のハムラビ法典」がなんかドタバタした話やったし、そういうので長いのを期待していたら、なんか暗ーい話が来た、みたいな感じがあって。
――でもご自分では別に、「十二月の窓辺」は暗くてあまりうまくいかなかったな、と思ったわけじゃないんでしょう。
暗いなあとはちょっと思ってましたけど。どうかなあ、失敗作だとは思わなかったけれど、好かれたいなあとは思ったんですよ。
――せっかくなら楽しんでもらいたいと。
まあべつに楽しくない小説もありますけどね、『アレグリアとは仕事はできない』に入れた「地下鉄の叙事詩」みたいな。
――あれ、面白かったじゃないですか。
二番目の人とか、だいぶ変なこと言いますからね。
――べつに、コミカルなだけが面白いということじゃありませんから。
まあねえ。ただ、ちょっと笑える部分を入れたほうがいいなあ、というのはありますね。そのほうが話としてのバランスがとれる、というのもありますし。
◆
進化してる?
――津村さんは、すこし引いた視線で書かれるから、そこから面白さが出てくるんじゃないですかね。入り込んじゃった、狭いところだけで描かれると、ものすごくシリアスになってしまうから。
ものすごく入り込んだモラハラのしんどさ、みたいなものがあったから、まあ、入り込んだしんどさでいいんですけどね。なんかやっぱり書いとかなあかん小説ではあったんですよ、「十二月の窓辺」は。いちばん怨念のあるものとして、最初の会社はあったので。
――なるほど。でもそれを経て、今はちょっと楽しいところがある小説がいいかな、というところに来た。
そういうことです。
――やっぱり、進化してるじゃないですか。
進化というか。なんていうか、商売……セールストークを覚えた、みたいな感じですよ。どっちかと言うと。
――書くということが、ただ自分の作業であるだけじゃなくて、読んでくれる相手がいるんだ、ということですよね。
そうですね。それは思いますね。
――プロというのはそういうものだ、と。
ねえ。そうだったらいいんですけどねえ。(笑)
…………………………………………………………………………………………………………
『君は永遠にそいつらより若い』(「マンイーター」改題)
詳細はこちら
『アレグリアとは仕事ができない』
詳細はこちら
カテゴリー
バックナンバー
- 2024年 03月( 5)
- 2024年 02月( 2)
- 2023年 10月( 3)
- 2023年 09月( 1)
- 2023年 08月( 1)
- 2023年 07月( 1)
- 2023年 06月( 4)
- 2023年 05月( 4)
- 2023年 04月( 1)
- 2023年 03月( 6)
- 2023年 01月( 3)
- 2022年 11月( 1)
- 2022年 09月( 1)
- 2022年 08月( 1)
- 2022年 07月( 1)
- 2022年 06月( 3)
- 2022年 05月( 2)
- 2022年 04月( 1)
- 2022年 03月( 4)
- 2021年 12月( 3)
- 2021年 11月( 2)
- 2021年 09月( 2)
- 2021年 08月( 3)
- 2021年 07月( 2)
- 2021年 06月( 1)
- 2021年 05月( 1)
- 2021年 04月( 3)
- 2021年 03月( 2)
- 2021年 02月( 1)
- 2021年 01月( 1)
- 2020年 12月( 1)
- 2020年 11月( 1)
- 2020年 10月( 2)
- 2020年 09月( 3)
- 2020年 08月( 1)
- 2020年 06月( 2)
- 2020年 05月( 2)
- 2020年 04月( 2)
- 2020年 02月( 1)
- 2020年 01月( 4)
- 2019年 12月( 1)
- 2019年 11月( 3)
- 2019年 10月( 3)
- 2019年 09月( 1)
- 2019年 07月( 1)
- 2019年 06月( 2)
- 2019年 05月( 6)
- 2019年 04月( 2)
- 2019年 03月( 4)
- 2019年 02月( 5)
- 2018年 12月( 4)
- 2018年 11月( 4)
- 2018年 10月( 4)
- 2018年 09月( 1)
- 2018年 06月( 2)
- 2018年 05月( 5)
- 2018年 04月( 1)
- 2018年 03月( 3)
- 2018年 02月( 1)
- 2018年 01月( 3)
- 2017年 12月( 3)
- 2017年 11月( 2)
- 2017年 10月( 2)
- 2017年 08月( 2)
- 2017年 07月( 2)
- 2017年 06月( 1)
- 2017年 05月( 4)
- 2017年 04月( 1)
- 2017年 03月( 4)
- 2017年 02月( 1)
- 2017年 01月( 6)
- 2016年 12月( 2)
- 2016年 11月( 2)
- 2016年 10月( 3)
- 2016年 09月( 3)
- 2016年 08月( 4)
- 2016年 07月( 2)
- 2016年 06月( 4)
- 2016年 05月( 6)
- 2016年 04月( 2)
- 2016年 03月( 3)
- 2016年 02月( 4)
- 2016年 01月( 2)
- 2015年 12月( 5)
- 2015年 11月( 2)
- 2015年 10月( 4)
- 2015年 09月( 1)
- 2015年 08月( 2)
- 2015年 07月( 5)
- 2015年 06月( 4)
- 2015年 05月( 8)
- 2015年 04月( 4)
- 2015年 03月( 4)
- 2015年 02月( 2)
- 2015年 01月( 1)
- 2014年 12月( 5)
- 2014年 11月( 2)
- 2014年 10月( 4)
- 2014年 09月( 2)
- 2014年 08月( 2)
- 2014年 07月( 3)
- 2014年 06月( 5)
- 2014年 05月( 3)
- 2014年 04月( 5)
- 2014年 03月( 7)
- 2014年 02月( 3)
- 2014年 01月( 5)
- 2013年 12月( 4)
- 2013年 11月( 3)
- 2013年 10月( 2)
- 2013年 09月( 7)
- 2013年 08月( 2)
- 2013年 07月( 8)
- 2013年 06月( 2)
- 2013年 05月( 2)
- 2013年 04月( 3)
- 2013年 03月( 6)
- 2013年 02月( 2)
- 2013年 01月( 4)
- 2012年 12月( 2)
- 2012年 11月( 3)
- 2012年 10月( 5)
- 2012年 09月( 2)
- 2012年 08月( 2)
- 2012年 07月( 6)
- 2012年 06月( 3)
- 2012年 05月( 4)
- 2012年 04月( 4)
- 2012年 03月( 3)
- 2012年 02月( 2)
- 2012年 01月( 2)
- 2011年 12月( 1)
- 2011年 11月( 2)
- 2011年 10月( 2)
- 2011年 09月( 4)
- 2011年 08月( 5)
- 2011年 07月( 3)
- 2011年 06月( 4)
- 2011年 05月( 2)
- 2011年 04月( 3)
- 2011年 03月( 5)
- 2011年 02月( 4)
- 2011年 01月( 2)
- 2010年 11月( 1)
- 2010年 10月( 5)
- 2010年 09月( 5)
- 2010年 08月( 6)
- 2010年 07月( 10)
- 2010年 06月( 2)
- 2010年 05月( 2)
- 2010年 03月( 4)
- 2010年 02月( 8)
- 2010年 01月( 6)
- 2009年 12月( 7)
- 2009年 11月( 4)
- 2009年 10月( 6)
- 2009年 09月( 6)
- 2009年 08月( 4)
- 2009年 07月( 6)
- 2009年 06月( 8)
- 2009年 05月( 3)
- 2009年 04月( 4)
- 2009年 03月( 4)
- 2009年 02月( 12)
- 2009年 01月( 11)
- 2008年 12月( 5)
- 2008年 11月( 6)