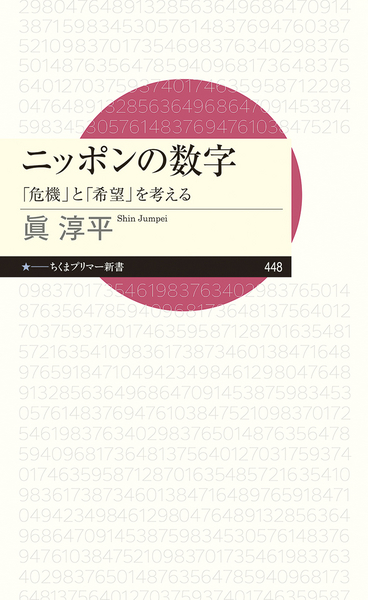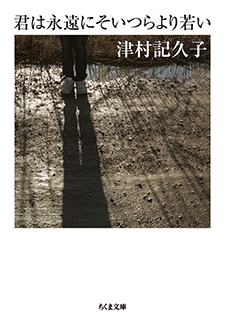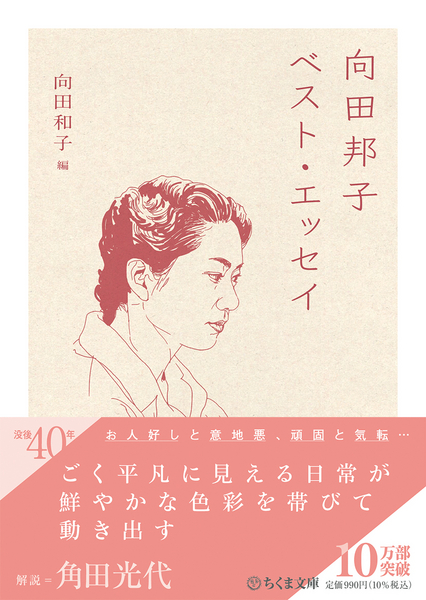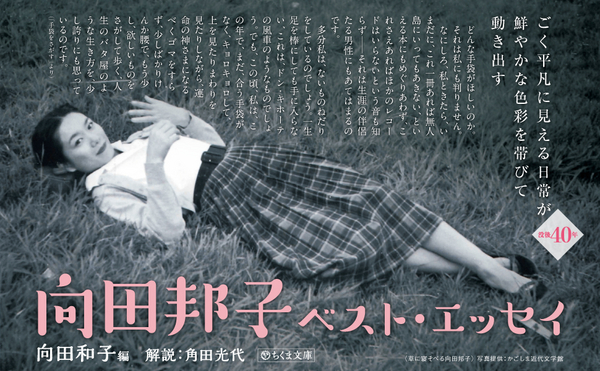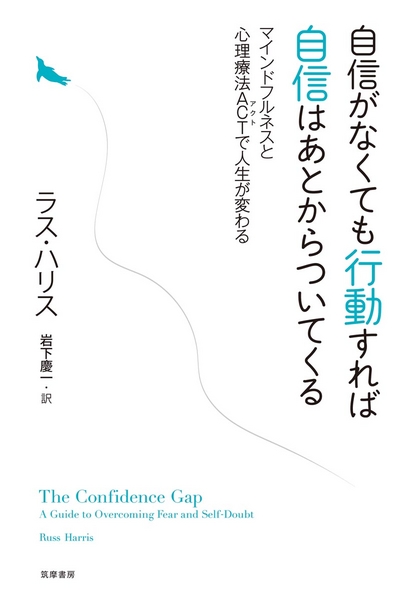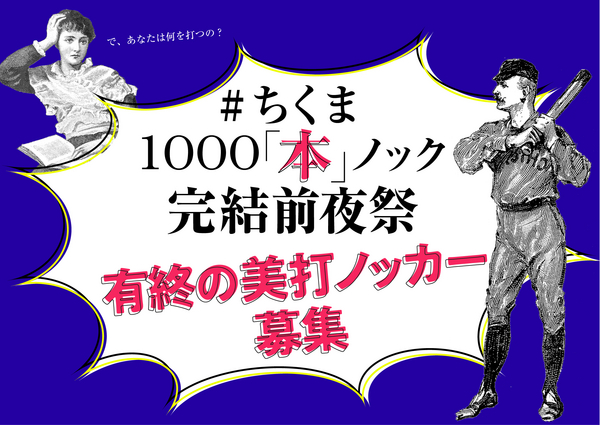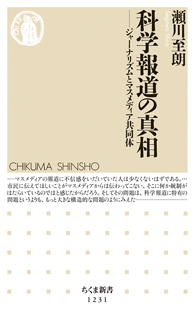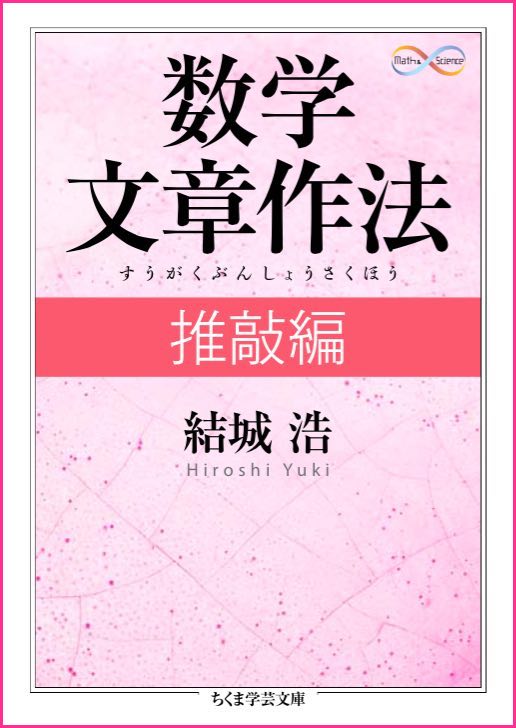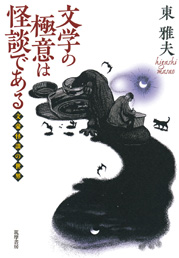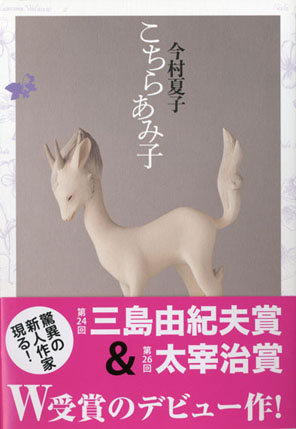筑摩書房 INFORMATION&TOPICS
24.06.21
第41回太宰治賞 作品募集
第41回太宰治賞の作品募集要項はこちらをご覧ください。
24.05.10
第40回太宰治賞受賞作が決定いたしました!
眞淳平『ニッポンの数字――「危機」と「希望」を考える』(ちくまプリマー新書)の【出典・参考文献一覧】はこちらから無料でダウンロードできます。(A4判PDFで49ページあります)
■眞淳平『ニッポンの数字――「危機」と「希望」を考える』(ちくまプリマー新書)詳細
23.06.22
第40回太宰治賞 作品募集
23.05.11
第39回太宰治賞受賞作が決定いたしました!
23.04.21
野々井透著『棕櫚を燃やす』が第36回三島由紀夫賞候補に選ばれました
22.06.21
第39回太宰治賞 作品募集
22.05.11
第38回太宰治賞受賞作が決定いたしました!
21.08.02
映画「君は永遠にそいつらより若い」一般試写会に5組10名様ご招待!
本作の公開に先がけ、下記日程において一般試写会の実施が決定しました。
合わせて、5組10名様を試写会へご招待いたします。
津村記久子の初の映画化作品として話題を集める本作をいち早くご鑑賞頂ける貴重な機会となりますのでお見逃しなく!皆様のご応募を心よりお待ちしております。
【応募方法】
1. 筑摩書房公式twitter (https://twitter.com/chikumashobo)をフォロー
2. こちらのツイートをリツイート
〆切:8月16日(月)
※当選のご連絡はtwitterのDMにて差し上げます
【試写会情報】
『君は永遠にそいつらより若い』一般試写会
日時:8月28日(土)15:15開場/15:30上映開始 (本編118分)
場所:TCC試写室(東京都中央区銀座8丁目3番先 西土橋ビル102号(地下1階))
【ご注意事項】
※当選者ご本人を含む2名様のご招待となります。
※都合により、イベントが中止、日程変更となる場合があります。予めご了承ください。
※開映後のご入場は固くお断りいたします。
※場内での録音・録音機器の使用を固く禁止致します。
※会場までの交通費、宿泊費などは、当選者様ご自身のご負担となります。
※当選の途中経過や当選結果に関するお問い合わせは承ることができません。
※都合により、締切日よりも早く応募を締め切る場合がございます。予めご了承ください。
【新型コロナ対策に伴う注意事項】
※本イベントは、新型コロナウィルス対策の下で実施いたします。
※当日、ご体調の優れない方はご来場をお控え頂きますようお願い致します。
※マスク着用、事前に手指消毒をお願い致します。
※下記症状のある方はご入場をお控えいただくよう、ご協力をお願い致します。
1:ご来場前に検温を行い、37度以上の熱がある場合
2:喉・咽頭痛などの症状がある場合
3:新型コロナウィルス感染症の陽性と判明した者との濃厚接触がある場合
4:同居家族や身近な知人の感染が疑われる場合
5:過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航並びに当該国・地域の在住者との濃厚接触がある場合
6:マスク着用、手指消毒、検温、ソーシャルディスタンス等、主催者の定める注意事項を守って頂けない場合
©「君は永遠にそいつらより若い」製作委員会
https://www.kimiwaka.com/(映画公式HP)
21.07.29
向田邦子さんに届けます。『向田邦子ベスト・エッセイ』感想募集!
21.06.21
営業部からのお知らせ
21.05.10
第37回太宰治賞受賞作が決定いたしました!
21.04.27
営業部からのお知らせ
21.04.05
スペシャルページに関するお詫びとお知らせ
音声データのダウンロードに時間がかかる状況となっております。
只今解決に向け対応中です。
対応出来次第、本ページおよび筑摩書房twitterにてご案内いたします。
ご不便とご迷惑をおかけし申し訳ありません。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
21.03.19
営業部からのお知らせ
21.03.18
WEBサーバーメンテナンスのお知らせ
※2/17 ワークシートを更新しました。「価値の窓」を追加してあります。
21.01.07
営業部からのお知らせ
20.08.07
「#ちくま1000「本」ノック」完結前夜祭!有終の美打ノッカー募集!!
筑摩書房の本を新旧問わず放っていくTwitter企画「#ちくま1000「本」ノック」。2018年2月14日より毎日こつこつとノックをつづけてきましたが、来る8月22日(土)、2年半の時を経ていよいよ1000 「本」を迎えます。そこで! 突然ではありますが、 #ちくま1000「本」ノック 完結前夜祭を催したいと思います。
1000 「本」めが放たれるその前に、みなさまによる有終の美打ノックでTLを埋め尽くしていただけないでしょうか?あなたのおすすめしたい筑摩書房の本を、ハッシュタグ「#ちくま1000「本」ノック有終の美打」を付けて、写真とコメントを添えてツイートしてください。
あなたのツイートが、誰かの「未知の本との出会い」に、「積読本の掘り起こし」や「愛読書再読のきっかけ」となるかもしれません。奮って猛打くださいませ!!
なお、1週間後の8月28日(金)の12:00時点でいちばんキャッチされていた(「いいね」されていた)有終の美打ノッカー1名には、猛打賞として以下の特典をご用意しています。
①現在制作中! #ちくま1000「本」ノックエコバック
▼▼▼ 詳しくはこちら ▼▼▼
●#ちくま1000「本」ノック 完結前夜祭!有終の美打ノッカー募集要項●
【有効打席(実施日)】
2020年8月21日(金) 0:00〜23:59のみ
【ノック方法】
①筑摩書房公式Twitterアカウント(@chikumashobo)をフォロー。
(猛打賞獲得の際に、公式アカウントよりDMでお知らせいたしますのでお忘れなく!)
②「筑摩書房」刊行の本からおすすめの本を選ぶ
③表紙や目次などの写真を撮る
(本文は著作権がありますので写さないようにお願いします!)
④書名、著者名、おすすめポイントや思い出などのコメントを書く
(誤字にはご注意ください!)
⑤Twitterにて、ハッシュタグ「#ちくま1000「本」ノック有終の美打」を付けて、写真とコメントを投稿する
【注意点】
下記については何卒ご注意・ご協力をお願いします。
◎ご自分のお手元にある本を使用してください
(本屋さんなどでの撮影は絶対に行ってはいけませんよ)
◎WEBサイトからの引用や画像コピーはNGです
(権利の侵害になってしまいますよ)
20.06.08
営業部からのお知らせ
コロナウィルス対策のため電話受付時間を短縮しておりましたが、
6/1より通常対応(平日9:15~17:15)に変更いたしました。
短縮期間中は大変ご迷惑をおかけいたしました。
変わらぬご高配の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。
20.05.20
営業部からのお知らせ
弊社営業部ではコロナウィルス対策に伴う業務調整に伴う電話受付時間を、
祝日を除く、月曜日から金曜日の午前10時から午後4時までと変更いたしました。
まだしばらくご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
20.04.06
営業部からのお知らせ
20.04.01
竹下晃朗『98歳、石窯じーじのいのちのパン』コラム集・ダウンロード
(A4判PDFで12ページあります)。
竹下晃朗応援コラム集
竹下晃朗『98歳、石窯じーじのいのちのパン』(2019/11/1発売)詳細
19.06.12
「#ちくま1000「本」ノック」 一日限定! 代打ノッカー募集!!
筑摩書房の本を新旧問わず放っていくTwitter企画「#ちくま1000「本」ノック」。2018年2月14日より毎日こつこつとノックをつづけてきました。
来る6月18日、筑摩書房は創業79年を迎えます。その日一日だけ、宣伝課はお休みを頂こうと思います。そこで、もしよかったら、これをご覧のあなたに一日宣伝部員になってノックをしてもらえないでしょうか?
あなたのおすすめしたい筑摩書房の本を、ハッシュタグ「#ちくま1000「本」ノック代打」を付けて、写真とコメントを添えてツイートしてください。
あなたのツイートが、誰かの「未知の本との出会い」に、「積読本の掘り起こし」や「愛読書再読のきっかけ」となるかもしれません。奮って猛打くださいませ!!
なお、1週間後の6月25日の12:00時点でいちばんキャッチされた(「いいね」された)代打ノッカー1名には、猛打賞として以下の3大特典をご用意しています。
①2019年6月18日 一日限定 宣伝課長 の称号を授与
②筑摩書房トートバック(黒)を贈呈
③「で、あなたは読んだの?」栞(ピンク)を贈呈
▼▼▼ 詳しくはこちら ▼▼▼
●#ちくま1000「本」ノック 1日限定! 代打ノッカー募集要項●
2019年6月18日(火)筑摩書房創業記念日 0:00〜23:59のみ
たくさんの代打、ありがとうございました!
①筑摩書房公式Twitterアカウント(@chikumashobo)をフォロー。
(猛打賞獲得の際に、公式アカウントよりDMでお知らせいたしますのでお忘れなく!)
②「筑摩書房」刊行の本からおすすめの本を選ぶ
③表紙や目次などの写真を撮る
(本文は著作権がありますので写さないようにお願いします!)
④書名、著者名、おすすめポイントや思い出などのコメントを書く
(誤字にはご注意ください!)
⑤Twitterにて、ハッシュタグ「#ちくま1000「本」ノック代打」を付けて、写真とコメントを投稿する
【注意点】
宣伝部員たるもの、下記については何卒ご注意・ご協力をお願いします。
◎ご自分のお手元にある本を使用してください
(本屋さんなどでの撮影は絶対に行ってはいけませんよ)
◎WEBサイトからの引用や画像コピーはNGです
(権利の侵害になってしまいますよ)
19.06.04
第36回太宰治賞 作品募集要項
「太宰治賞」の第35回は、おかげさまで、才能ある新人作家を世に送り出すことができました。第36回にも、既成の型にとらわれない、新たな文学の息吹きを伝える清新な作品が、多数寄せられることを期待します。
第36回太宰治賞の作品募集要項はこちらをご覧ください。
(A4判PDFで20ページあります)。
http://www.chikumashobo.co.jp/data/9784480843180.pdf
ラス・ハリス『相手は変えられない ならば自分が変わればいい──マインドフルネスと心理療法ACTでひらく人間関係』(5/26発売)詳細
19.02.05
『柳田國男全集』巻構成を変更いたします
読者の皆様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。何卒ご理解賜りたくお願い申し上げます。(編集部)
18.05.09
第34回太宰治賞受賞作が決定いたしました!
3月29日発売の榎田ユウリ『この春、とうに死んでるあなたを探して』の著者直筆サイン本を数量限定でネット予約販売いたします。
・ご応募の締切は3月20日10時59分となります。
・先着順で満数になり次第、受付を締め切らせていただきます。
・お1人様1冊限りとさせていただきます。
・お届けは発売後、3月末ころを予定しております。お申し込みはこちらから。(https://books.rakuten.co.jp/rb/15386350/)
(楽天ブックスにてお申し込みいただきます。お支払い方法等、楽天ブックスのサイトをご参照ください)
この件のお問い合わせは楽天ブックスまで。
満数に達したため、受付を終了しました。
本書は3月29日の発売となります。どうぞご期待ください。
内容紹介
矢口弼は38歳、元税理士。
離婚を経験して仕事にも疲れた矢口は、中学時代を過ごした雨森町にひとりきりで戻る。新しい住まいは、かつての同級生・小日向の営む喫茶店「レインフォレスト」の上階。外見は変わっても中身は子どものままに騒々しい小日向に矢口は面食らいながらも、少しずつ雨森町になじんでいく。
そんなふたりにもたらされる恩師の死をめぐる謎。先生の死は事故なのか? あるいは、生徒からのいじめを苦にした自殺?
23年前の真実を求めて、矢口と小日向は元クラスメイトを訪ねるが――。
【四六版並製/本体価格1300円+税】
著者紹介
榎田ユウリ(えだ・ゆうり )
東京都出身。主な著書に〈妖琦庵夜話〉シリーズ(角川ホラー文庫)、『夏の塩』をはじめとする〈魚住くん〉シリーズ、〈カブキブ!〉シリーズ(以上、角川文庫)、『ここで死神から残念なお知らせです。』『死神もたまには間違えるものです。』(以上、新潮文庫nex)など。また榎田尤利名義ではボーイズラブ作品を多数発表し、著作数は2018年で120を超える。
魅力的なキャラクター、繊細な心情描写、巧みなストーリーテリングによってジャンルを超えた人気を博す。
榎田ユウリ『この春、とうに死んでるあなたを探して』(3/29発売)
17.06.15
第34回太宰治賞 作品募集要項
17.05.29
瀬川至朗著『科学報道の真相』が科学ジャーナリズム賞受賞
日本科学技術ジャーナリスト会議による2017年度科学ジャーナリスト賞に、瀬川至朗著『科学報道の真相――ジャーナリズムとマスメディア共同体』(ちくま新書)が選ばれました。
「STAP細胞報道や福島原発事故報道の失敗、地球温暖化に対する報道の揺らぎ、その3つをテーマに科学報道の特色を分析し、その在り方を考察した好著。科学ジャーナリストを目指す人にとっては格好の教科書となろう」と評されています。
詳細はこちら→http://jastj.jp/jastj_prize
『科学報道の真相 ─ジャーナリズムとマスメディア共同体』詳細
17.05.09
第33回太宰治賞受賞作が決定いたしました
2017年5月8日(月)午後5時から、第33回太宰治賞(筑摩書房・三鷹市共同主催)の選考委員会が開かれ、厳正な選考の結果、受賞作が以下の通り決定いたしました。
第33回太宰治賞受賞作
「タンゴ・イン・ザ・ダーク」 サクラ・ヒロ
詳しくはこちら
16.10.07
野嶋剛著『台湾とは何か』が樫山純三賞(第11回)受賞
16.05.12
第32回太宰治賞受賞作が決定いたしました。
2016年5月9日(月)午後5時30分から、第32回太宰治賞(筑摩書房・三鷹市共同主催)の選考委員会が開かれ、厳正な選考の結果、受賞作が以下の通り決定いたしました。
第32回太宰治賞受賞作
「楽園」 夜釣 十六
詳しくはこちら
15.12.24
朝日新聞平成27年12月24日朝刊の記事について
15.12.22
電話・FAXで小社サービスセンターに注文される場合の送料の改訂について
15.12.01
電子書籍の無料ダウンロードを僭称する違法サイトにご注意ください
平素は弊社の電子書籍書籍をご愛顧くださいまして、誠にありがとうございます。
最近、弊社の電子書籍を無料ダウンロードできるかのように装った危険性のある違法サイトが確認されております。
そのような不審なサイトには、お名前やメールアドレス、クレジットカード番号等を登録なさいませんようご注意ください。
15.09.17
写真家のご連絡先を探しています。
ちくま学芸文庫では『土門拳 写真論集』(田沼武能編、文庫オリジナル)の刊行を企画しております。刊行にあたりましては、関連写真の転載のご許可をいただくべく最大限の努力をいたしましたが、ご所在が不明な著作権者の方がいらっしゃいます。
朝倉真佐男先生
東洋介先生
雨森康男先生
上田三郎先生
内木順先生
亀山正憲先生
河口義次先生
河又松次郎先生
木村朗先生
佐藤勤先生
沢田了一先生
島内吉康先生
杉村一勝先生
田村純一郎先生
遠沢利寛先生
中井三千三先生
永井光道先生
仲野元一先生
野呂高生先生
原島孝一先生
松田繁美先生
三田村茂先生
元谷賢太郎先生
現在のご連絡先等、お心あたりの方は、恐れ入りますがご連絡を頂戴くださいますよう、ご協力をお願い申しあげます。
●連絡先
筑摩書房ちくま学芸文庫編集部
TEL 03-5687-2676/FAX 03-5687-2677
15.07.30
第31回太宰治賞贈呈式のレポートを掲載しました
15.06.25
第32回太宰治賞 作品募集要項
15.06.24
第31回太宰治賞 「選評」と「受賞の言葉」を掲載しました
結城浩著『数学文章作法 推敲編』(ちくま学芸文庫)の電子書籍配信が2015年3月27日(金)に開始されます。もっと明確でよく伝わる文章を書くためのノウハウを、『数学ガール』の著者が伝授する『数学文章作法』シリーズ。その待望の第二弾が、ついに電子書籍端末でも読めるようになります。
『数学文章作法 推敲編』「はじめに」「第一章」のためし読みはこちら
これを記念して、応募者の方に、著者・結城浩さんの直筆メッセージカードとQUOカード1000円分をプレゼントいたします。ふるってご応募ください。
応募方法は、下記のとおりです。
【応募方法】
下記の手順でツイートをしていただいた方から抽選で5名様にプレゼントいたします。
(1)筑摩書房公式Twitterアカウントをフォロー
(2)Twitterで該当のツイートをリツイート、もしくは #数学文章作法 のハッシュタグをつけてツイート
※すでに筑摩書房公式Twitterアカウントをフォローいただいている方は、あらためてフォローしていただく必要はございません。
※応募対象期間は 2015年3月20日(金)~4月3日(金)です。
※当選された方にはTwitterのダイレクトメッセージでお知らせいたします。3日以内にご返信いただけない場合は当選が無効となりますのでご注意ください。
※キャンペーンの参加にはTwitterアカウントが必要になります。アカウントを削除された場合は当選が無効となりますのでご注意ください。
※キャンペーンの参加には筑摩書房公式Twitterアカウントをフォローしていただく必要があります。フォローをはずされた場合は抽選の対象外となりますのでご注意ください。
14.11.27
【プレゼント】結城浩さんのサイン本 ツイッターキャンペーン
キャンペーン期間中、Twitterで「#数学文章作法」のハッシュタグをつけてツイートしていただいた方の中から抽選で5名様に、結城浩さんのサインが入った新刊『数学文章作法 推敲編』をプレゼント!
応募対象期間 2014年11月27日(木)~12月8日(月)
つぶやく内容は「結城さんへの応援メッセージ」「『数学文章作法』への感想」「『数学文章作法』のお気に入りのフレーズ」など、なんでもOKです。どしどしご応募ください。
※当選された方には12月9日(火)に、Twitterのダイレクトメッセージでお知らせいたします。3日以内にご返信いただけない場合は当選が無効となりますのでご注意ください。
※キャンペーンの参加にはTwitterアカウントが必要になります。アカウントを削除された場合は当選が無効となりますのでご注意ください。
※キャンペーンの参加には筑摩書房公式Twitterアカウントをフォローしていただく必要があります。フォローをはずされた場合は抽選の対象外となりますのでご注意ください。
※書店での発売日は12月12日(金)です。
『数学文章作法』シリーズの詳細はこちら
14.05.07
第30回太宰治賞受賞作が決定いたしました
2014年5月7日(水)午後5時30分から、第30回太宰治賞(筑摩書房・三鷹市共同主催)の選考委員会が開かれ、厳正な選考の結果、受賞作が以下の通り決定いたしました。
第30回太宰治賞受賞作
「コンとアンジ」井鯉こま
詳しくはこちら
14.04.10
弊社公式ツイッター再開のお知らせ
一時公式ツイッターを閉鎖しておりましたが、社内の体制が整いましたので
本日4月10日(木)より再開いたします。
今後、積極的によりよい情報をお届けするため、
新たにソーシャルメディアポリシーを定め運営してまいりますので
どうぞよろしくお願いいたします。
ソーシャルメディアポリシー、及び公式ツイッターアカウント一覧は
こちらからご覧頂けます。
14.01.27
弊社公式ツイッター閉鎖のお知らせ
ちくま文庫 @chikumabunko1/ちくま新書 @ChikumaShinsho/
ちくまプリマー新書 @chikumaprimer)を閉鎖しました。
弊社および弊社出版物に関する情報については、
引き続きこちらの筑摩書房ホームページをご覧ください。
13.12.02
山下祐介著『限界集落の真実』が第9回生協総研賞研究賞受賞
島根県主催の第一回「古代歴史文化賞」にて、三浦佑之著『古事記を読みなおす』(ちくま新書)が「古代歴史文化 みやざき賞」を受賞しました!
詳細はこちら
【「古代歴史文化賞」とは】
古事記や日本書紀、風土記などに関する記述がある一般向けの本が対象。
島根県が古代史に縁の深い三重、奈良、宮崎の3県に呼びかけて創設した賞です。
「大賞」1点のほか、「みえ賞」「みやざき賞」「しまね賞」「なら賞」の4点の地域賞が設定されています。
他の受賞作は次のとおりです。
大賞=都出(つで)比呂志「古代国家はいつ成立したか」(岩波新書)
みえ賞=斎藤英喜「古事記はいかに読まれてきたか」(吉川弘文館)
しまね賞=関和彦「古代に行った男ありけり」(今井出版)
なら賞=近江俊秀「道が語る日本古代史」(朝日新聞出版)
尚、記念シンポジウム「日本の始まり 出雲・大和・日向・伊勢」が、11月17日、東京・有楽町のよみうりホールで開かれます。
13.08.01
amazon Kindle、楽天koboで電子書籍配信開始!
筑摩書房の電子書籍を、amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストアで販売開始しました。
ベストセラー作品や紙の本では読めなかった作品がお手持ちのスマートフォンや専用端末などで読むことができます。
今後も続々、販売書店様を増やしていきますので、どうぞお楽しみに!
●amazon Kindleストア
●楽天koboイーブックストア
13.05.08
第29回太宰治賞受賞作が決定いたしました
2013年5月8日(水)午後5時30分から、第29回太宰治賞(筑摩書房・三鷹市共同主催)の選考委員会が開かれ、厳正な選考の結果、受賞作が以下の通り決定いたしました。
「さようなら、オレンジ」 KSイワキ
詳しくはこちら
12.11.14
太宰治賞〆切迫る!(12月10日(月)です)
12.06.25
第28回太宰治賞の贈呈式レポートをアップしました
12.05.08
第28回太宰治賞受賞作が決定いたしました
2012年5月8日(火)午後5時30分から、第28回太宰治賞(筑摩書房・三鷹市共同主催)の選考委員会が開かれ、厳正な選考の結果、受賞作が以下の通り決定いたしました。
「うつぶし」 隼見果奈
詳しくはこちら
11.12.13
津村記久子さん、第28回織田作之助賞受賞!
11.11.25
太宰治賞〆切迫る!(12月10日(土)です)
11.11.11
筑摩選書創刊1周年! フェア開催中
11.10.11
長嶋有デビュー10周年!エッセイ集続々刊行!
11.09.06
「モリムラ先生の美術塾」開講! アートに関する質問大募集
11.08.31
「こちらあみ子放送局・01号」配布中!
11.08.23
第27回太宰治賞の贈呈式レポートをアップしました
11.07.15
『西洋哲学史の基礎知識』(有斐閣刊)執筆者のご連絡先を探しています
11.06.23
ショッピングカート一時休止のお知らせ
小社HPが販売業務を委託するブックサービス株式会社のシステム検証に伴い、下記の日程で、WEB受注を休止させていただきます。
WEBサイト休止期間
平成23年6月24日(金)22時〜平成23年6月28日(火)12時
※ 期間中は小社サイトからのカートの連携がご利用出来ません。
詳細はこちら
小社サイト上でショッピングカートをご利用のお客様におかれましては、
ご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解賜りたく、伏してお願い致します。
11.06.21
第27回太宰治賞の贈呈式レポートをアップしました
11.05.09
第27回太宰治賞受賞作が決定いたしました
2011年5月9日(月)午後5時30分から、第27回太宰治賞(筑摩書房・三鷹市共同主催)の選考委員会が開かれ、厳正な選考の結果、受賞作が以下の通り決定いたしました。
「会えなかった人」 由井 鮎彦
詳しくはこちら
カテゴリー
バックナンバー
- 2024年 07月( 2)
- 2024年 06月( 2)
- 2024年 05月( 1)
- 2024年 03月( 5)
- 2024年 02月( 2)
- 2023年 10月( 3)
- 2023年 09月( 1)
- 2023年 08月( 1)
- 2023年 07月( 1)
- 2023年 06月( 4)
- 2023年 05月( 4)
- 2023年 04月( 1)
- 2023年 03月( 6)
- 2023年 01月( 3)
- 2022年 11月( 1)
- 2022年 09月( 1)
- 2022年 08月( 1)
- 2022年 07月( 1)
- 2022年 06月( 3)
- 2022年 05月( 2)
- 2022年 04月( 1)
- 2022年 03月( 4)
- 2021年 12月( 3)
- 2021年 11月( 2)
- 2021年 09月( 2)
- 2021年 08月( 3)
- 2021年 07月( 2)
- 2021年 06月( 1)
- 2021年 05月( 1)
- 2021年 04月( 3)
- 2021年 03月( 2)
- 2021年 02月( 1)
- 2021年 01月( 1)
- 2020年 12月( 1)
- 2020年 11月( 1)
- 2020年 10月( 2)
- 2020年 09月( 3)
- 2020年 08月( 1)
- 2020年 06月( 2)
- 2020年 05月( 2)
- 2020年 04月( 2)
- 2020年 02月( 1)
- 2020年 01月( 4)
- 2019年 12月( 1)
- 2019年 11月( 3)
- 2019年 10月( 3)
- 2019年 09月( 1)
- 2019年 07月( 1)
- 2019年 06月( 2)
- 2019年 05月( 6)
- 2019年 04月( 2)
- 2019年 03月( 4)
- 2019年 02月( 5)
- 2018年 12月( 4)
- 2018年 11月( 4)
- 2018年 10月( 4)
- 2018年 09月( 1)
- 2018年 06月( 2)
- 2018年 05月( 5)
- 2018年 04月( 1)
- 2018年 03月( 3)
- 2018年 02月( 1)
- 2018年 01月( 3)
- 2017年 12月( 3)
- 2017年 11月( 2)
- 2017年 10月( 2)
- 2017年 08月( 2)
- 2017年 07月( 2)
- 2017年 06月( 1)
- 2017年 05月( 4)
- 2017年 04月( 1)
- 2017年 03月( 4)
- 2017年 02月( 1)
- 2017年 01月( 6)
- 2016年 12月( 2)
- 2016年 11月( 2)
- 2016年 10月( 3)
- 2016年 09月( 3)
- 2016年 08月( 4)
- 2016年 07月( 2)
- 2016年 06月( 4)
- 2016年 05月( 6)
- 2016年 04月( 2)
- 2016年 03月( 3)
- 2016年 02月( 4)
- 2016年 01月( 2)
- 2015年 12月( 5)
- 2015年 11月( 2)
- 2015年 10月( 4)
- 2015年 09月( 1)
- 2015年 08月( 2)
- 2015年 07月( 5)
- 2015年 06月( 4)
- 2015年 05月( 8)
- 2015年 04月( 4)
- 2015年 03月( 4)
- 2015年 02月( 2)
- 2015年 01月( 1)
- 2014年 12月( 5)
- 2014年 11月( 2)
- 2014年 10月( 4)
- 2014年 09月( 2)
- 2014年 08月( 2)
- 2014年 07月( 3)
- 2014年 06月( 5)
- 2014年 05月( 3)
- 2014年 04月( 5)
- 2014年 03月( 7)
- 2014年 02月( 3)
- 2014年 01月( 5)
- 2013年 12月( 4)
- 2013年 11月( 3)
- 2013年 10月( 2)
- 2013年 09月( 7)
- 2013年 08月( 2)
- 2013年 07月( 8)
- 2013年 06月( 2)
- 2013年 05月( 2)
- 2013年 04月( 3)
- 2013年 03月( 6)
- 2013年 02月( 2)
- 2013年 01月( 4)
- 2012年 12月( 2)
- 2012年 11月( 3)
- 2012年 10月( 5)
- 2012年 09月( 2)
- 2012年 08月( 2)
- 2012年 07月( 6)
- 2012年 06月( 3)
- 2012年 05月( 4)
- 2012年 04月( 4)
- 2012年 03月( 3)
- 2012年 02月( 2)
- 2012年 01月( 2)
- 2011年 12月( 1)
- 2011年 11月( 2)
- 2011年 10月( 2)
- 2011年 09月( 4)
- 2011年 08月( 5)
- 2011年 07月( 3)
- 2011年 06月( 4)
- 2011年 05月( 2)
- 2011年 04月( 3)
- 2011年 03月( 5)
- 2011年 02月( 4)
- 2011年 01月( 2)
- 2010年 11月( 1)
- 2010年 10月( 5)
- 2010年 09月( 5)
- 2010年 08月( 6)
- 2010年 07月( 10)
- 2010年 06月( 2)
- 2010年 05月( 2)
- 2010年 03月( 4)
- 2010年 02月( 8)
- 2010年 01月( 6)
- 2009年 12月( 7)
- 2009年 11月( 4)
- 2009年 10月( 6)
- 2009年 09月( 6)
- 2009年 08月( 4)
- 2009年 07月( 6)
- 2009年 06月( 8)
- 2009年 05月( 3)
- 2009年 04月( 4)
- 2009年 03月( 4)
- 2009年 02月( 12)
- 2009年 01月( 11)
- 2008年 12月( 5)
- 2008年 11月( 6)